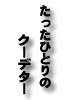���Ñ㍑�ƁE�הn�䍑�̔ږ�Ă͉��҂��H��
���d�ɂ���y�́A���̕���E�c�����K�̉e�l�Łu���{�l�̑�̓h���}�v�������n�߂Ă��܂����B
����ƐF��Ȃ��̂������čl�@���ʔ��������Ă͗������A�C�ɐ��鎖���������Ă͗��j�̒T���҂Ƃ͌����Ȃ��B
���ʂ̐l�Ԃ��v�l����ƁA�����g������ʓ|���������ĒP���Ȕ����̓����Ō����𒅂�������B
�܂��A���̐����������ׂ̈ɕ�������L�ۂ݂ɂ��āA�v�l���~���Ă��܂��������X�݂�B
�����������̖{���͂���ȊȒP�Ȃ��̂ł͖����A���̗��ɂ܂őz����y���Ȃ��Ɩ{���̐^���ɂ͒H�蒅���Ȃ��B
�܂�������[���l�����A�s�m���ȓ`���Ŗ������Ă���l�Ԃ͗]��m�I�Ƃ͌����Ȃ������m��Ȃ��B
�ŋߐ��Ԃł́u�ږ�Ă̕悪����o�����v�Ƒ呛�������Ă���B
�ޗnj�����s�ɍ݂�u����i�͂��͂��j�Õ��v������̌��ʁA�u�ږ�Ă������Ƃ���铯�N��̌�����������v�ƌ����̂ł���B
���������������_���猾�킵�Ă��炦�A�ږ�Ă��Î��L�E���{���I�͖ܘ_�̎��A���{�̌Õ����ɂ͂܂������L�ڂ������A�����̐��j�ł���鰏��i�S�O�\���j�́u���Γ`���̘`�l�̏��i�ʏ́E鰎u�`�l�`�j�v�ɋL�ڂ���Ă���݂̂̑��݂ł���B
���{�j�ɂ����Ǝ����������Ă���B
���{�̐_�b�̎n�܂�͒��ؑ嗤�ɋ߂���B�i�Δn�C�����j�E�R�A�n���i�����n�����{�C���j�A�����m�ɓ������y�шɓ������n���ɏW�����Ă���B
����́A�����̐_�b�������I�ɒ��ؑ嗤�̊���������n�C���ė����n�����������Z�����i�ڈΑ��j������ׂɈׂ��������_�ɝs�����z�̐_�b������ł���B
�@���𐭎��ɗ��p�����茠�͈ێ��ɗ��p����͓̂��R�̔��z�ł���B
��̑��i�吼�m�푈�j���푈���s�ׂ̈Ɂu�펀�����������_���Ő_�Ƃ����J����v�Ƃ܂��ɐ_�𗘗p���č����ɍ��荞������������������B
�o�_���卑��_�b�A��B�����h�E�����_�b�A��B���V��ː_�b�A�ɓ���������~�X�e���[�ȂǓn�����������{�ɏ㗤�������Ղ��L����čs���E�E�E�B
���̌�n�������̓��{�����ڎw���āA�_���V�c���_�����J�ɂ��_�b�̕���͋E���n���Ɉڂ��a���삪�������Đ_�b�̕���͍c���̂���ꏊ�ɂȂ����B
�`���_�b�̎���E�ږ�Ă̐��̂������m�łȂ��̂ɓ�����ږ�Ă̑��݂��m�肵����ŁA�u�ږ�Ă̕���������v�͊w�҂ɂ���܂��������Ȕ��z�ł���B
�����������{�j�ɑ���ԓx�́A���̑��݂��^���Ă�����j��̑n��l���E�������q�̑������L�ۂ݂ɂ���̂Ɠ����̑e���ȍl�����ł͂Ȃ����낤���H
鰏����L�ۂ݂ɂ������}���ɂ��葖�炸�A���̑O�ɂ܂��͔ږ�Ă��N�ł��邩�̓��������ׂ��ł���B
�u���i����/�����j�v�̌��ۂōl������݂蓾�Ȃ��u�s�v�c�Ȍ��ۂ��N�������v�Ƃ���鎖���u���i����/�����j�v�̌��ۂŁA�����̖ړI�͓���̐l�����J���X�}�i���l�j����n�����鎖�ł���B
���́u���i����/�����j�v�̌��ۂ����p�����Ɓu�_�b��M�̐��E�v�Ȃ̂����A�V����(�Ă�ނĂ��j�`������(����ނĂ��j�ɓ���c�����Ҏ[�����u�Î��L�v�Ɓu���{���I�v�́A���ɍc���ɋ��铝���̐�������⊮����u���i����/�����j�v�̕����𑽂��܂�ł���B
�܂�J���ׂ��́A���{�j�̈���펯�i���傤�����j�Ƃ���钆�ɁA�u���i����/�����j�v�̗��j��������O�̗l�ɍ��݂��A����������N�C�Y�ԑg���Łu�����v�Ƃ���Ă��鎖�ł���B
����͓��{�̐��j�E�L�I�_�b�i�Î��L�E���{���I�j�ɋL�q�������A�����̐��j�u�O���u�v�́u鰏��i�S�O�\���j�v�ɏ�����Ă����̏����̐��̂�ǂ݉������݂ł���B
�Ñ㍑�Ƃ̃��[�_�[�́A��p�ҁA��p�҂Ɠ`�������u�ږ���v�ɑ�\������V���[�}���ł���B
���̐_�̐��u�����v���A���Ɖ^�c�̋��菊�ł���@���������B
鰎u�`�l�`�i�����킶��ł�j�Ɂu�ږ���v�ƌ��������������B
���߂鍑�́A�הn�䍑(��܂�������)�ł���B
�הn�䍑(��܂�������)�́A�킪���̌Î��L�Ɠ��{���I�ɋL�q���Ȃ��A�����́u鰎u�`�l�`�ɋL�q���݂�v�ƌ�����̍��ŁA���̒n�������ɍ݂����A�����Ɋw�ҒB�͘_���̍Œ��ł���B
���ؒ鍑��鰏��ɍ݂�݂̂œ��{�̎j���ɋL�ڂ������ږ�����הn�䍑�̎���m��Ȃ����{�l�́A���̂��قڋ��Ȃ��B
�����A���{�̎j���Ƃ�����Î��L�E���{���I�ɍ݂��X�T�m�E�i�{�����j����z���i���Ȃ��Ɂj�͂��Ȃ�m���x���Ⴂ�B
���̊�ȏ��A���̓��{�j�̌���ł͂Ȃ����낤���H
���j�̐^���ɒH�蒅���ɂ́A����ɔ����Ă�������n�߂Ă͈Ӗ��������B
����ł́A���N�o���Ă��u��͓�v�ŏI����Ă��܂��̂ł���B
鰎u�`�l�`�ɋL�ڂ��ꂽ���X�ʼn��̑��݂�������Ă���̂́A�u�ږ�����הn�䍑�v�E�u�X�T�m�E����z���v�E�u���鎁���ɓs���v�̎O���̍������ŁA�܂肱�̎O���̍��������̓��{�ɉ����čL��E�L�͂ȉ����ł���\���������B
�����i�����j�̍c�邪�A�`���ƔF�߁A�`���ƔF�߁A����܂ő��������������邱���ږ���̖��́A�ʂ����ČŗL�̖��O�Ȃ̂��낤���H
�N���̘a���́u�������̏[�Ď��v�Ƃ͍l�����Ȃ����낤���H
�������L��`����O���ɍl����ƁA�הn�䍑(��܂�������)�̏������K���������{�Ɍ��肷����̂ł͂Ȃ����������ł���B
�������הn�䍑(��܂�������)�̏��݂���{�ɉ��肷��ƁA�L�I�_�b�i�Î��L�E���{���I�j�ɋ���u�_�����J�����v�̋�z���i���Ȃ��Ɂj�Ǝהn�䍑�i��܂��������j�́u�����Ƙa���v���N�₩�ɕ������ė���̂ł���B
�퐶����̏o�y�i�E�����i�ǂ������j�́A�퐶����ɐ������ꂽ�ޏ��^�̐����̍Պ�ŁA�I��ɐ���ɑn���O���I�ɂȂ�ƓˑR�����Ȃ��Ȃ�̂����A���̎������u�S���i�_���j�v�������̐M�Ɏ���đ��鎞���Əd�Ȃ��Ă���B
�퐶���������Õ������ւ̓]�����̗l���������ƌ�����ޗǁE㕌��i�܂��ނ��j��Ղ����ʂɏo�y�������̎킩��A���ؑ嗤�E鰍�����`������Ƒz����u�����i�_���j�̍��J���s��ꂽ�v�Ɛ�������A���̍��J���i�i�����ǁj�����̂��u�ږ�Ăł͂Ȃ����v�Ɗ��҂���Ă���B
�����Ŗ��Ȃ̂́A���{�̍l�Êw�҂̑唼���ŏ�����u�S���i�_���j�����ɓ`����ꂽ�v�Ɖ��߂��A���ؑ嗤�E鰍�����́u�n����������������ŗ����v�Ƃ͔��z���Ȃ�����ł���B
鰎u�`�l�`�ɓo�ꂷ��ږ�ẮA���́u�S���i�_���j��p���ďO��f�킵���v�ƋL�q�݂�A�u�S���i�_���j�v�͖퐶���ォ��Õ�����ւ̓]�����Ɂu�V�����M�v�Ƃ��āu�����̐M���쒀����`�ŗɎ����ꂽ�v�Ɖ�����Ă���B
�܂�A�������u�S���i�_���j�v���n���������ږ��Ɣ��Ɏ�������ŗ����̂ł���A�ږ�Ă͑嗤�̐V�����M���������u�n���l�v�ƌ������ɐ���B
�ږ���̏o�����A��y�͗ɓn�藈�����������ɋ��鏉���V���~�Փ`���́u���_�v�ƁA���Z���i�ꕶ�l/�ڈΑ��j�̎��R��p�M�i�̐_/�A�s�F�j�̏K���ɋ��錴�Z���i�ꕶ�l/�ڈΑ��j�x�z�́u���������o�����������_�i�����j�v�ƌ��Ă���B
���Z���i�ꕶ�l/�ڈΑ��j�x�z�ɍł��L���Ȏ�i�́A�ؕ|�̔O���������ĂЂꕚ�����鎖�ŁA����i��������/�������݁j�̏オ�_�ɁA�܂莁�_�i�������݁j�ɂȂ������Ղ���������B
�������_�̖��i�_�̌��Ёj�������ēy�n�����߁A�������߂��؋��͌��t�Ƃ��ĉi���c���Ă����B
�u�������^�e�}�c���B�v
���̈Ӗ����A�M���͍l���������L�邾�낤���H
�́A�ƌ����Ă����S�\�N�قǑO�̍]�ˊ��₻��ȑO�ɂ́u���߂鎖�i�������{�����j�v���A�u���i�}�c���S�g�j�v�ƌ��������A���̈Ӗ��͌����܂ł������u�Վ��i�}�c���S�g�j�v�ł���B
�܂�A���藧���̌ꌹ����A�_�̖��i�_�̌��Ёj�������Ď������{�������u���i�}�c���S�g�E�Վ��j�v�ł���B
����i���_�j�ƌ������̎������{���҂́A�_�Ƃ��āu�^�e�}�c�������i���čՂ���j�v�̂ł���B
���̂����Ƃ��炵������Ă��A��p���p�ŁA���́u�ؕ|�Ǝx���v���i�������B
�]���ď����̕������[�_�[��n�捑�Ƃ̃��[�_�[�́A�ږ���ɑ�\�����V���[�}���I�ȏp�҂��C���Ă����B
�����āA���̐�p���p�̃V���[�}���I�ȈЗ͂��ł����͂Ȏ҂��A�剤�i�������݁E��̓V�c�j�ɍՂ肠������̂ł���B
�����A��������i���_�j�̎������u�����Ƃ͂��Ȃ�������́v���A�K�����݂����B
����u�����{���́v�ł���B
�����ŁA��������҂��u�^�e�}�c���k�i���čՂ�ʁj�v�ҒB�ł���u�����{���́v�̎����A�u�}�c�����k�i�Ղ��ʁj�ҒB�v�ƁA�ĂԎ��ɂȂ�B
���̈ꎖ�������Ă��Ă��A�����҂��u�_�𖼏�����J���N��������v�̂ł���B
�V���[�}�j�Y���ɉ����āu�_���i���݂����j���v�Ƃ́A�ޏ��̐g�̂ɐ_���~�Ղ��A�ޏ��̍s���⌾�t��ʂ��Đ_���u�����i����������j�v���������ł���B
���R�A�ޏ����u�_���i���݂����j��v��Ԃɐ���ɂ́A�����̐_���~�Ղ���ׂ̎��f�s�ׂ��s�Ȃ��A�_���i���݂����j���Ԃ�U�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���̍ł������ɍs�Ȃ��A�i���A�z�C���ɓ`��������ꂽ���f�s�ׂ̏p���A���Ȃ킿�ޏ��ɉߌ��Ȑ����������ăh�[�p�~���������A�]������̃x�[�^�[�E�G���h���t�B�����ʂɔ��������鎖�ŁA�ޏ����I�[�K�Y���E�n�C�̏�ԁi��������ԁj�ɐ���A���̛ޏ��̗l�q������͂��_�̍~�Ղ�F�߁A�u�_���i���݂����j���v�Ɛ���B
�u�_������E�E�v
�܂茩��҂ɁA�_�̑��݂�[���������镽��ȏ�Ԃł͖�����A�u�_������v��������K�v���݂�B
�ٗl�ȏ�ɋ��������A����ŏ��߂Ď��͂ɐ_�̑��݂�[����������J���N���d�|���Ȃ̂ł���B
���{�̓Ǝ������ƌ����A���̍��ł͌×����珗�_�������̂����A���������Ƃ��̎��i�ɂ��Č���ł͍l�����Ȃ��������������B
����͐����̋V��������s�����ł���B
�ˑR���������b�������o���Ɩʋ�炤���������邾�낤���A�^�ʖڂȘb�Ȃ̂Ō���̔��z�͎b�炭���ɒu���ēǂݐi�߂ė~�����B
���̐_�O�����A�m���Ɂu����̐��_�v�z�Ƃ͊|������Ă���v�Ƃ��l�������m��Ȃ����A�ȒP�Ɍ��_���o���āu�����Șb���v�Ƃ͎v�킸�ǂݐi�߂Ē��������̂��B
���c�F���V�F���i���߂̂����߂݂̂��Ɓj�ٖ̈��������ɋ�������i�������j�̌̎�(�`��)�ȗ��A�����Ɋ��u����s�i�����傤�j�ɋ���_�Ƃ̃R���^�N�g�v�́A���{�̐M�j��ɘA�ȂƑ��������f�ޏ��̐_�s(���傤)�Ɏn�܂�R�������B
�܂荑�Ɠ���ɍł��d�v�Ȉٖ����̘a���ɋ��镽�a�̊m���ƁA���̌�̖L���i�����̎q���j�ɋ��閯���������ő�̐_�ւ̊肢�ł���F����f�Ȃ̂ł��邩��A�[���l���I�Ȃ��̂ɂ�����H�I�Ȃ��̂ɂ�������i�������j�̌����͐_�y���A�ޏ����̐_���ɂ͌������Ȃ����̂������B
���̗ǂ��E������^���E�s�^����ʂɂ��������Ƃ��āA�u����i�������j�v�ƌ����`�̐����͐_�ォ�瑶�݂����B
����i�������j�̐����͑���ɑ��镞�]���Ӗ����A�������̓I�ɏؖ������i�ł���B
�_�O�ɉ�����ޏ��̐����͐_�Ƃ́u����i�������j�v�ł���A�u�_�̌����v��ׂ̐_���ȍs�ׂŁA���̔w�i�ɂ͕����Ԃ̕��a���ȓ����̋L���ł���B
�]���āu�_�i������j�v�������ł��邪�A��𗍂܂��������̈���ɂ拒��u�_��i�����₭�j�v�Ƃ͏����Ⴂ�A�u����i�������j�v�̐����͂����܂ł��u���]�I�ȍs�ׁv�ƌ������ɐ���B
��a�̍��i���{�j�t�����̏��_�́A�_�̌��t��V�ォ����A�����i����������j�Ƃ��ĉ��E�̖��ɓ`����̂���ځA�܂��ޏ��i�V���[�}���j�������B
�����ɉ�݂����̂��A�_���Ƃ��ĕ�[���鐫���̋V���ł���B
�������ė~�����̂́A�����̕�����������ƈႢ�A�q��鎖������̖L���鎖���A���������Y�ݏo���_�̌b�݂ł���A���̍�Ƃ�_�̌�O�i�݂܂��j�Ŏ���s����[���Ă����v���肢�A�����ɛޏ���ʂ��Đ_�̐��i�����j���̂ł���B
�ܘ_���l���A���A�ޏ��ɉ��������Ă��ՁX�Ƃ͐M���Ȃ��B
�ޏ����_���i���݂����j��ɐ����ď��߂Ă��̌����i����������j���M�p�����B
���̌����i����������j��ׂ̃A���e�i���A�ޏ��̏��̂��̂��̂ŁA�I�[�K�Y���E�n�C��ԁi�_��/���݂�����j�̐_���ޏ����f�r�i���܂�j�����ɋ����āA�V��_�̐��������ė���̂ł���B
����̂ɐ_���Ƃ��ĕ�[���鐫���̋V�����^�ʖڂɗv������A�v�z�I��a���͖��������̂ł���B
������A���������@�艺����ƁA�����t�����̐����������i�����̒��j�̐_�i���ɒH�蒅���B
�����͐��̛ޏ���������ł͂Ȃ��B
�����n�̓�����e�Ղɂ���ɂ́A���l���M�p�����ΓI�ȋt�炦�Ȃ����͈ȊO�̗͂��K�v�ŁA����͓V�ォ��̐_�̐��ł���B
�������̐_�i����i�߂�ɂ������āA��������_�Ɛ����A���~��_�扻���Đ_�ЂƂ���Ɠ����ɁA���̍@�܁i������/�ȁj���A�V���[�}�����̏��_�ɔC�������i����������j�̔\�͂���������B
�܂菗�_�́A�������̍@�܁i������/�ȁj�ł���A�u�������i�_�j�̌��t�v���A�@�܁i������/�ȁj�Ɍ����i����������j�����钃�Ԍ��I�ȁu�y�e���E�J���N������n�܂����v�ƍl����̂������I�ł���B
���ꂪ�i�X�ɗl��������čs���A�������̍@�܁i������/�ȁj���琫���̋V��������s�������ޏ��i�V���[�}���j�ɑւ��B
���̏��̂̃A���e�i�Ō����i����������j��I�[�K�Y���E�n�C��ԁi�_��/���݂�����j�̐_����A�ޏ����f�r�i���܂�j���ׂ̋V�����A�������f(�����������セ)�ƌ����u�p�i���ׁj�v�Ɛ����ĉA�z��p�ɔ��W�A��ɖ{���ŋL�q����u�l�g�䋟�`���v�ւ̗��ꂪ�`������čs���̂ł���B
�M�̎n�܂�́A��p�ҁE��p���̃��[�h�ɋ�����̂ŁA�Ñ㍑�Ƃ̃��[�_�[�ł����p�ҁE��p�҂Ɏ���āA���ȁi���y�j�͏d�v�ȃA�C�e���������B
�܂�m�̓������킸�A���X�����̉��ȁi���y�j�́A��p��M�I�Ȍ��ʂƕ\����̂��̂ŁA���̉��ȁi���y�j�̋N���������͐M�ׂ̈̔�����Y������n�܂��ċ���̂ł���B
���ȁi���y�j�́A�l�̐S�����炬�ɓ������苻����������́A�S�n�ǂ��S���I���ʂ������炷�B
���N���P�ׂ̈̉��ȁi���y�j���ʂ����邻���ŁA�M�S�Ɖ��Ȍ��ʂ����܂��āA�_�̊�ւ������炷����͂���B
��������Âɍl����ƁA�����̊�ւ͉Ȋw�I�𖾂��i�݁u�����ł��Ȃ��_�̗́v�Ƃ͌��݂ł͌�������̂ɂȂ����B
�����A�i�����u�����ł��Ȃ��M�̌��ʁv�Ɛl�X�ɉ�����āA�M���W�߂�ׂɌ��ʂ������B
�����������ȁi���y�j�����{�ł͉�y��_�y�i���j�ƂȂ�A�M����������i�ƂȂ�B
�₪�Ă����͎���ƂƂ��ɓ������W���āA�|�\�̕���ɂȂ����B
����́A�킪���×��̐_�АM�Ɍ��炸�A�S�Ă̏@���ɉ��y�͌������Ȃ��B
���{�̗��j�́A�Î��L�E���{���I�̕Ҏ[���ŏ��̖{�i�I���j���Ƃ��āA���̓��e�����ɓ`�����Ă���B
�u�L�I�_�b�i�Î��L�E���{���I�j�v�̉��߂������Ă���̂́A��̖�������{�ƌ��������n��ɍS��u�����Ȑ���ρv����ł���B
�Ⴆ�ł��邪�A�Î��L�E���{���I�Ҏ[�̎��_�ł͂܂����B�i���k�n���j�͓����O�̉ڈi���݂�/�ꕶ�l�j���̓y�n�������B
�����Ē��N�����̐l�X�̕����A�����`�l�Ƃ�����a�������\������l�X�ƌ����̏�ł��߂������B
�V���~�i���j�Փ`���́A�c���̐����������`����ׂɑ�\��E�����V�c�i����ނĂ�̂��j�̍��ɕҎ[���ꂽ�u�L�I�_�b�i�Î��L�E���{���I�j�v����n�܂��Ă���B
�V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j�̑��ł���V���E�j�j�M�̖��i�݂��Ɓj���A���������i�A�V�n���i�J�c�N�j�E�V�E�ɑ���n��̍��j�̕�����āA�Î��L�ɋ���舯�������̓����ׂ̈ɍ��V�������u�}���̓�����������̂����ӂ��ɍ~��Ă���ꂽ�v�ƋL�������{�_�b�̐��b�ł���B
�܂�c���̑c�́u�V���畑���~�肽�_�̎q���v�ƌ����̂ł���B
�܂����{���I�ɂ́A����E�_���剤�i��������/�V�c�j�ܑ̌�O�̐�c�V���E�j�j�M�̖��i�݂��Ɓj���S���Ȃ�ꂽ���A�u�}���̓��������i���́j�̎R�˂ɑ���܂�v�ƋL����Ă���B
�������A���̓V���~�i���j�Փ`���́A���N�����̉���i���돔���j�̌����_�b�ł���u���덑�v�̎n�c�E��I���i�X������/����남���j���u�T�|��i�N�W�{���j�ɓV�~��b�E�E�E�Ǝ��Ă���v�Ƃ̎w�E���݂�B
�܂�A�u�L�I�_�b�i�Î��L�E���{���I�j�v�̈ꕔ�́A���N�����E����i���돔���j���玝�����ݗA�����ꂽ�`�����̗p�����H���ċL�ڂ����^���������̂ł���B
�����Ō�������i����j�́A���{�ŌĂ��C�߁i�݂܂ȁj�����돔���i���₵�傱��/����j�̔C�߉����̐��͔͈͂̎��ł���B
����i����j�܂��͉��돔���i���₵�傱���j�́A�O���I����Z���I�����ɂ����Ē��N�����̒��암�ɉ����āA�S�ρi�y�N�`�F/������j�ƐV���i�V����/���炬�j�ɋ��܂ꂽ�����]�i�i�N�g���K��/�炭�Ƃ������j����𒆐S�Ƃ��ĎU�݂��Ă��������ƌQ���w���A�V���ɂ����Ă͉���E����ƌ����\�L���p�����A�����E���{�i�`�j�ɂ����Ă͉����Ƃ��\�L����Ă����B
�ǂ������{�ɓn�藈�����������̑������A���̉��돔���i���₵�傱���j���C�߉����i�݂܂Ȃ���E����j�o�g�������ׂɁA�㐢�̓��{�l���ꎞ�j���ɔ����āu�C�ߓ��{�{�i�݂܂Ȃɂق�Ӂj�v�Ȃ錶�̓��{�̂��Ñ�j�ɉ����ď���ɑn��グ���^���������B
���́u�L�I�_�b�i�Î��L�E���{���I�j�v�̓V���~�i���j�Փ`����̋��X�܂ŕՁi���܂ˁj�����`�����g�D���A�V���i�Ă�ށj�V�c�i��l�\��j�̖����������p�i����̂����ʁj���g�D�����A�z�C���g�D���A�����i����ށj�V�c�i��\��j���A�z���Ƃ��Đ����ɒ���g�D�ɑg�ݓ���ēV���~�i���j�Փ`���̌��`�Ɋ��p�����̂ł���B
�ǂ��l���Č���A�Ҏ[�����̐����I�v�f���܂߁A�L�͈́A�����ԁA�������̓`����b�荞��ŁA�u�L�I�_�b�v�͕Ҏ[����Ă��锤�ł���B
�����l����A�l�@����̂Ɋy�ɂȂ�B
�]���āA�u�L�I�_�b�v�𐳊m�ȗ��j�ςƂ��č̗p����ɂ͓����B
�����ɂ��ւ�炸�A�u�L�I�_�b�v�̉��߂��u�����I�ɗ��p���悤�v�ƌ��������ȉ��߂����₽�Ȃ��B
�Î��L�E���{���I�Ҏ[�ɂ́A�S�\�N����S�N�������͂�����ȑO�̏o�������A�c���̐�����������������j�`���Ƃ��ĕҎ[����A��דI�Ɏ�����c�ȁi�킢���傭�j���Ă��܂��Y�펖�������B
����ł��ږ�Ăɂ��āA���덇�킹�̂ق���т��_�b�̓`���ɂ͑��݂���B
�V�Ƒ�_�i�V�Ƒ��_�j�́u�����/�����Ђ�߂̂ނ��v�Ƃ������_���i�ُ́j�������A�V�Ƒ���쏗���i���܂Ă炷�����Ђ�߂݂̂��Ɓj�ƌ���������������B
���́u�����/�����Ђ�߂̂ނ��v�́u�����v�͑��̂ł���u�Ђ��/���쏗�v�́u�Ђ݂��v�̎��Ƃ���u�ږ�Ă��w���v�ƌ������߂�����B
���{�l�ɂ͘c�u�A���ӎ��i�����ӎ��j�v�������T�O�I�ɐA���t�����Ă��āA���{�̍c���͍��M������u���N�l���c���̉łɂȂǂ���Ȃ��v�ƌ������Ɋ���I�Ȕ��z�ŁA���j���l���Ă��܂��B
�ߏ�Ȗ����ӎ�����A���{�l���u�M�������镨��v�ł���B
�������A����͂Ƃ�ł��Ȃ�����ł���B
�������`�l�i�킶��j�̏Z���ɒ��N���������{�̐��������܂܂�A�c���̑c��́u���N�����������ė����v�ƌ����̂������ł���B
���̌㒩�N�����Ɠ��{�̌𗬂��a���ɂȂ�A���j������Ŋe�X���ʂ́u�A���ӎ��i�����ӎ��j�v����Ă����͔ے肵�Ȃ����A����͓����u�`�l�i�킶��j�v���m�Ƃ��Ă̌𗬂��r�₦�Ĉȍ~�̎��ł���B
���{�̗��j����́A�唪�B�i�����₵�܁E���{�j�̍ł����A��B����n�܂����B
�Ï��ɂ��ƁA��B�A�u�����i�Ђイ���j�̍��v�́A�×��_�X�̂��킷�i������j���ł���B
���N�䕗�Ɍ�������ȊO�́A���g�ʼn��₩�ȋC��̒n�ƌ�����B
���́u�����̍������a�̍��̊���R�ɍ~�肽�v�Ƃ����_���A��قǏڂ������q���邪�A�e�l�̑c�A��ΎЂ̍Ր_�E��Ό��p�g���i���������݂݂̂̂��Ɓj�������B
�����̍��͌��݂̋{�茧�ł���B�{�茧�̓����A�啪�����ɉ����s������B
�̂͒����ԁA�u���i�������j�̏��v�ƌ����n���������B
�����s�̒��S���𗬂��܃�����̏B�ɂ���u����(�ނ���)�v�̒�����쉈���̓���k��ƁA�V���~�Փ`���̒n�u������v�Ɏ���B
���݂�����(�ނ���)�́A�����s�̍x�O�ɍ݂鉽�̕ϓN�������ЂȂт��Z��X�����A����ȉ^���������Ă��̕���ɉ��x������o���s�v�c�Ȓn���ŗL��B
���������̒n���A�c�X�Ƒ������u�V���~�Փ`���v�̎����̔��˂Ƃ��̓��N�]���ɁA�Ō�̎������I�����}���������̒n�Ȃ̂ł���B
��������(�ނ���)�̖��O�́A�퍑�����E��F�@�������t�������������A���̘b�͌�̏͂ɏ���B
����䒬�́A�V���~�Փ`���̒n�ł���B
�V���̌��́A�V�̈ꑰ�i���߂̂��������j�ł���B
�_�b�̐��E�ł́A�V���_�i���܂����݁j�Ƃ������B
�����ɂ́A�u����䋬�v�ƌ��������ȋ��J������A�ό��n�Ƃ��Ă��S���ɒm���Ă���B
���̒n�ɓV��u�V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j���A���̐��Ɏg�킳�ꂽ�v�ƌ����Ă���B
�R�Ԃ̒��ɂ́A�Â����獂���_�Ђ��Ղ��Ă���B
��_�̂́A���̐��̍ō��_�E�V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j�ł���B�V��ˁi���܂̂���Ɓj�`�����A���̍����̒n�ɂ���A��˂Ƃ����O�̏d�Ȃ荇��������_�̂Ƃ���V��ː_�Ђ��A�Ղ��Ă���B
���V���i�����܂��͂�j��A����i��݁j�̍����A���̍����̒n�ɉ��̐[���`���ƌ�����B�����i�{�茧�j�̍��ɂ́A���V���i�����܂��͂�j�_�Ђ�����B
�����ɍՂ��Ă����t���̕��@���A�����R���֓a�i�����イ����E�͂�����ł�j�ƌ����B
���ւ��{���ŁA��O�i�܂�F���j����Y�Ɂu�䗘�v���L��v�ƌ����Ă���B
���V���_�Ђ͐_�Ђł���Ȃ���A��t���̕��@�A�܂莛�̔q�a���������_���K���i����ԂE�Ȃ炢���킷�j�́A���O�M�ɍ��t�����M�̏�ł���B
�����č����i�������فj���猩�ē��̏��铌�̕����ɖk�쒬������A�V���~�Փ`�������x�i���̂����j�����т��Ă���B
�_�b�̍��E�������i�{�茧�j�̖k�����ɂ���k�쒬�i���P�n�S�j�̒n�ɉ��x�i���̂����j�͂���B
�����i�N���j�����̉��B���V���~�Փ`���Ő_�i�����ꂽ�ے��I�ȋL�q���A�Î��L�E���{���I�Ɏc�����R���������x�i���̂����j�ł���B
�W�����S��\�����[�g�������x�i���̂����j�ɂ̓j�j�M�m�~�R�g(�A���j�M�V�N�j�j�M�V�A�}�c�q�R�q�R�z�m�j�j�M)��˕�`��������A�Î��L�ɋ���Ə���_���V�c�ܑ̌�O�̐�c�E�V���j�j�M�m�~�R�g�͍��V�������u�}���̓����̍����̂����ӂ��ɍ~��Ă���ꂽ�v�ƋL����A���{���I�ɂ̓j�j�M�m�~�R�g���S���Ȃ�ꂽ�Ƃ��u�}���̓����̉��i���́j�̎R�˂ɑ���܂�v�ƋL����Ă���B
�V���~�Փ`�����I�����}�����̂����͂��̓`���̒n���������A���̘b�͂��̕���̖{�ҁi�c�����K�̉e�l�j���Ō�܂œǂ�ł���������Δ���B
�܂����x�i���̂����j�́A�����i���������j�ɋ�����{�����̎n�܂�̏ے��݂����ȎR�����A���i���ǂ�j�����Ɏ����i���������j�I���̒n���������x�i���̂����j�������̂ł���B
����ɂ��Ă��A���̐^������������邱�̓����i�{�茧�j�̍��n���V���~�Փ`�����N����A�y���I�v�̎����o�ēV���~�Փ`�����������̒n�Ŗ������Ƃ́A�s�v�c�Ȃ߂��荇�킹�ł���B
���̐��̍ō��_�u�V�Ƒ�_�v�͑��z�_�ł���A�{�茧�͐́A�����i�Ђイ���j�̍��i�܂�A���z�̒n�j�ƌ������B
��������̐^�������������A��D�̃��P�[�V�����Ɉʒu���邩������i�Ђイ���j�̍��Ȃ̂ł���B
���������̓V��˓`���ɋ���ƁA���n���x�z����u�V�Ƒ�_�v����˂��Ă����������́A�C���x�z�����_�A�u�{���V�j�i�X�T�m�I�j�̖��i�݂��Ɓj�̓x�d�Ȃ鈫�s�ɋ���v�Ƃ���Ă���B
�����Ȑ��E�ɍЂ��������炷��_�A�u�{���V�j�i�X�T�m�I�j�̖��i�݂��Ɓj�v�́A�����Î����Ă���̂��H
�����{���V�j�i�X�T�m�I�j�̖��i�݂��Ɓj�́u�x�d�Ȃ鈫�s�v�����̕���̃q���g�ŁA�ٖ������m�̎x�z�n�����ł���Α嗤�R�Ԃ̈��n�����i�V����/�������j�ƊC�m�����i���l��/�����j�̐}�������藧���A���ɔ���Ղ��B
�܂�A�嗤�R�Ԃ̈��n�����̑��z�_�E�V�Ƒ�_�i�A�}�e���X�I�I�~�J�~�j�ƊC�m�����E�{���V�j�i�X�T�m�I�j�̖����A�u���{�̔e���𑈂����Ă����v�Ɖ��߂ł���̂ł���B
�䍑�̍��̂ɂ��̂��Ă���u������v���A�����̍��E���̏��i�����j�߂��̑�ԊC�݂ɑ��݂���B
�����̍���ԊC�݁i�������s�k�Y���j���獂���Ɏ��钼���́A�����珸�藈�鑾�z�̒ʂ蓹�ł���B
�u�{���V�j�i�X�T�m�I�j�̖��v���A�����̗��ƊC�̋��ł����ԊC�݂��A�ʂ蓹�i�㗤�n�_�j�Ƃ��āA�u���s�ɋy�v�Ƃ��Ă��s�v�c�͂Ȃ��B
�u�{���V�j�i�X�T�m�I�j�̖��v�́A�x�z�����C�����Ȃ����ɕs���������āA�u�_�̎d�����T�{�^�[�W�����Ă����v�ƌ������A����̌��͂̋y�ԏ����A�{���n�ɂ��Ȃ��Ȃ��B
�]���āA�C�������ė��ẮA���s�ɋy���ɂȂ�B
���Ȃ݂ɁA�u�V�Ƒ�_�v�Ɓu�{���V�j�i�X�T�m�I�j�̖��v�̊Ԃɂ́u���ǁi�c�L���~�E�c�N���~�j�̖��v�ƌ�����i�Łj���x�z����_������B
���_�ł͂Ȃ����A�Â���͐̂̐l�X�ɂ͋��낵���̂ŁA�h������Ă����B
�{���V�j�i�X�T�m�I�j�́A�O�Ԗڂ̐_�Ȃ̂��B
�܂�O�M�_�i�E�Y�m�~�R�j�Ŋ���̗ǂ������́A�V�Ƒ�_�����ł���B
���ǁi�c�N���~�j���́A���z�̐_�E�V�Ƒ�_�i�A�}�e���X�I�I�~�J�~�j�ɑ��Ė���x�z����u���̐_�v�Ƃ���Ă���B
���������������̂܂ܓǂނƁu����ǂށv�A�܂葾�A����g���Ă��������̗�ɉ����ẮA�����͎��Ԃ�Ό��i�N�����j���i��_�����m��Ȃ��B
�u���{���I�E�Î��L�v�ɂ́A�]�茎�ǁi�c�N���~�j���̊������̂ŁA���ʂ�����Â���悤�ȕ`�ʂ͂Ȃ��A�j���������邪�A�䔄�i�Ђ߁E�����j�̕������}���`�b�N�ł͂Ȃ����낤���H
���̒n����сu��B�A�����i�Ђイ���j�̍��v�ɂ́A�u��ː_�y�v�̓`�������Ɏc���Ă���B
�V�Ƒ�_���A�B���Ă����Ă��܂����V��˂��u�V��͒j�i���߂̂������炨�j�̖��v�������J���鎞�ɁA�V�Ƒ�_���u�������H�v�ƁA�`�����̌��Ԃ��J���������̂��A���́u�_�y�i������j�̎n�܂�v�ƕ����B
���́A��˂Ɍ��Ԃ��J����������j�I���������ɂȂ����_�y�̌��^�́A�u�V�F�i���߂̂����߁j�̖�(�݂��Ɓj�̋������A���I��ȃX�g���b�v�_���X�v�A�ƌ����Ă���B
�V�F�i���߂̂�����)�̖�(�݂��Ɓj�́A�V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j�����(�V�Ή���/���܂̂���Ɓj���Ă������ɁA��˂̑O�ŗx�������_�ŁA�u�F��i�����߁j�v�́u�����v�̈ӂŁA����������Đ_�Ղ�i�_�y���j�����鏗�_�A�X�ɂ́u�_�߂����i���݂��������j�����̐_�i���������v�Ƃ���Ă���B
�����V�F���i�A���m�E�Y���m�~�R�g�j�̃X�g���b�v�_���X�̓`���ɒ��ʂ���ƁA�u����͎q���ɂ͋������Ȃ��v���́u�_���ȓ��{�̗��j�ɁA����Ȕ��i�Ђ킢�j�Șb�͎�����Ȃ��v�ƌ��O��`�̔��z���N���A���Ɏv�����́u���̕����ɂ͐G��Ȃ��Œu�����v���A�u�����������ɂ��Ă��܂��v�ł���B
�\�����̊�펖�i���O�j���茾���āA���̖{���ɐG�ꂸ�Ɏ����ς܂��Ă��܂��̂����{�l�̗d�����������A���̊�펖���u���j�̔F���ɂ܂ŋy�ԁv�Ɛ���Ə����������Șb�ł���B
�܂�ޏ��̐_�y���́A�V�F�i���߂̂�����)�̖�(�݂��Ɓj�̊��(�Ή���)�_�y�����`�ł���B
�L�I(�Î��L�E���{���I)�̋L�q����́u�_�������ĕ������v�Ɠǂ߂��V�F���i�A���m�E�Y���m�~�R�g�j�́A�_���̍Վ����s�Ȃ��ޏ��ł���B
�̖��i���{�l�j�́A�u��Z���i�ꕶ�l�j�Ɠn���n�����̍������v�ƌ����Ă��āA�V�F�i�A���m�E�Y���j�̕v�_�E���c���Ð_�i�T���^�q�R�j�͐�Z���i�ꕶ�l�j�A�@�_�E�V�F���i�A���m�E�Y���m�~�R�g�j�͓n���n�퐶�l�������B
�_�b�ɉ����ẮA���c�F���V���~�Ղ����m���ĉ_�ɏ���ď�V���A�u�r���܂ŏo�}�����i�n�������}�H�j�v�Ƃ���A���̎��V���i�n���l�E�i�������j�͉��c�F�ɑ��V�F�����u�g�҂Ƃ��Č��������i����E�����ɂ��Q��̈�̉��̋V�j�v�ƌ����B
����i�������j�̂��������_�́u�Η��̉����v�ɂ���A���̋��ɂ̏ؖ��`�̂��_�i������/�����j�ɋ���R���v���C�A���X�i�v���▽�߂ւ̕��]�j�̎��H�ł���B
�܂肱�̕v�w�i�߂��Ɓj��_�̖������܂��A�u�V�������̗Z�a�i����j�̏ے��v�ƌ�����ł���B
�אڂ��Ĉٕ����i�ٖ����j�̏�������������A���ꂼ�ꂪ���͊g���ژ_��ŕ������N����B
�u���i��/�ށj�v�͐�ׂ̈̂��̂ł���N���ɂ��g������̂ł���Ȃ���A���́u���ׁv�ƌ������O���������i�ނ����j�ɖ��������t�ł���B
����E����E���҂́u���i��/�ށj�v�̈Ӗ��ł��邪�A�{���͐ϋɓI�ɐ키�ׂ̌��t�łȂ����ׂ̌�b�i�����j�̂��̂ŁA�u���i�ق��j���~�߂�v�Ə����ĕ��i��/�ށj�Ɠǂ܂���B
�l�Ԃƌ��������������ςȏ������A�u���i��/�ށj�v�̗l�ɔ����ɋU��̐��`�����O�ɂ����������Ȍ��t�g���͌��\�����B
���������Α����ւ̏o���i�N���j�̗��R�Ɂu���Y�n�ݏZ�̎������̕ی�v�ƌ������ڂ͗ǂ��g��ꂽ�B
���ł����u�����i�ނ����j�v�ƌ������t���A�U�߂閵�i�ق��j�Ǝ�鏂�i���āj�̑������镐��̑o���l���������甭�������B
�����͖����i�ނ����j�ɖ������u���i��/�ށj�v�ƌ��������ݏo�����l�Ԃ����A�S���ɍU�߂閵�i�ق��j�Ǝ�鏂�i���āj�̑������镐����߂Ă����ɕ����Ȃ������������m��Ȃ��B
�����Đl�Ԃ���ɕ����Ȃ��{�����������������炱���A����i�������j�̋����Љ�C�f�I���M�[���A��a���̍��i��a���j���������͗B��ٖ̈������a�Z���̎�i�������̂����m��Ȃ��̂ł���B
���̕v�w�i�߂��Ɓj��_���A�V��i���c�F�j�ƃI�J���i�V�F�j�ɐ���A�㐢�ɓ`�������e�n�̍Ղ�́A�_�y���̖�(������)�Ƃ��Ďc�����B
�V��i�Ăj�́A�V�̌��i��E�����j�̈Ӗ��ŁA�`����Ă���ߑ��́A�V��A���炷�V��̕ʂ��킸�A�C���R���̈ߑ��p�ŁA�C�������_����̂ł��鎖����Ă���B
����(������)�̐��_�ɏ]���āA�u�킢���~�߂ăx�b�g�E�C�������悤�v�̐��_�ׁ̈A�_�y���̖�(������)�A�V��̕@�͒j�����\���A�I�J���̌��͏������\���Ă��āA���ׂ̂̈ɃT�C�Y�����킳��Ă���̂��{���ł���B
�Վ��Ƃ��āu�_�������ĕ����v����́A�V�������̗Z�a�i�����j�̏ے��_�I�ɏj���_�ւ̕�[�̕��ł���B
�ޗnj����������E���_�Ђɂ͓V��Ƃ����߂̏�i�x�b�h�V�[���j��������u���Ղ�v�����邪�A����������ېV�̕����J���O�́A�u���{�S���ō�����Ă����v�ƌ�����B
��������(������)�̐��_�́A���オ�����čs���ƁA�����G���𖡕��ɂ���ׂ́u���������v�ɕω����čs���̂ł���B
�����N(����߂̂���/����̍��J�Ɍg��鎁���̈��) �̑c�_�Ƃ���Ă����V�F�i���߂̂�����)�̖�(�݂��Ɓj�́A�����N�̎��́u�_�y�̎��ɋ����v�Ƃ��āA�{���ɕ�d���A��Ƃ��āu�_�y�Ɍg��������q�v�ł���Ƃ���A�e�n�ɐ_�y��|�\�̐_�Ƃ����J���Ă���B
���̎��V�Ƒ�_���x���̂Ɏg��ꂽ�̂��A�O��̐_��̈�u���@�i���^�j�̋��v�ł������B
�X�g���b�v�_���X��x��ȂǁA�_�l�ɂ��Ă͂����Ԃ�l�ԏL����b�ł���B
�܂�A�u�V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j�v���C�ɂȂ�A�`��������Ɂu�ϋq�̐_�X�v������ɂ́A�����̎d�|�����K�v�Ȃ̂��B
���̊�ː_�y�A���͌����̗��_�y�ɑ傫�ȈӖ�����������`�����������A����͒ǁX�M��i�߂�B
�������i�{�茧�j�E��ԕӂ�̃��A�X���C�݂͓V�R�̗Ǎ`�ł��邪�A�Ôg�ȂǂɏP����Ɣg�̍����͕���ȊC�ݐ��̐��{���琔�\�{�ɒB����B
���R�̖҈ЁA�܂�u�{���V�j�i�X�T�m�I�j�̖��v��{�点��ƁA�C�ӂ̖��ɂ͎n���ɕ����Ȃ��B
������Ёi�����j�߂���̂́A�ō��_�A�u�V�Ƒ�_�v�����Ȃ̂��B���̈�A�̓`���̗��ɂ́A���R�̖҈Ђ����łȂ��B���ꂽ���j�����锤���B
�����ł��邪�A�����A���������y�����������i��Z�n�������E�V�̈ꑰ�i�V�����ƌ��������n���j�ƌォ��C��n�藈���i�������i�C�m�����E���l���ƌ������n���j�́u�Η��̍\�}�v��\���Ă���ƍl������B�܂�A�㑱�̊C�m�i���������A�{���V�j�i�X�T�m�E�j�̈ꑰ�ƈʒu�Â����͂��Ȃ����H
�V�̈ꑰ�̎����A�V�_�i���܂����݁j�Ƃ��������A����ł͓V�̈ꑰ�S�Ă��_�ɐ����Ă��܂��B
���̎���́A�V�i���܁j�͋�Ɨ����Ӗ����Ă����B
�]���ēV�̈ꑰ�i�V����/�嗤�R�Ԉ��n�j�́A�����x�z���Ă����B
����ɑ��A�C���x�z���閯���������B
�ڂ����͌�q���邪�A���̊C�̖��i�C�m�����j�̌Ăі����A�F�P�i���܂��j�ł���A�ʖ��͔��l�i�͂�Ɓj�ł���B
�����A�݂��͑��e��Ȃ��������ō݂����̂��B
�����炱���{���V�j�i�X�T�m�I�j�ɊC�̎x�z�͔F�߂邪�A���̎x�z�͔F�߂Ȃ��B
���A�V�i���߁j�̕�����䔄�i�Ђ߁j�̕������t���_�������Ȃ��A��_�̐{���V�j�i�X�T�m�I�j�ɂ͕t���Ă��Ȃ��̂��A���l�݂����ł͂Ȃ����B
�����{���V�j�i�X�T�m�I�E�{�����j�̐��̂ł��邪�A���{�̋_���M�i�������j�́A���s�̔���_�Ђ{�ЂƂ��A��������ɐ����������M��w�i�ɁA�����̐_�ŁA�_�����ɂ̎��_�E�����V���i�S�d�e���m�E�j�y�ѐ_���̐_�E�{�����i�X�T�m�I�j���Ղ�A�u�a�ɑ����_���K���̐M�ł���B
���̐_���K���ł��邪�A���X�ݗ��̐_�X�M�Ɠn���̕����M�Ƃ́A���������h�䎁�̑Η��Ɍ���悤�ɕ��͏Փ˂ɋy�ԂقǑ��݂ɂ͑傫�Ȋu���肪�������B
�������̖��ɂ́A�����̖���������i�������j�œ�������m�b�������Ă����B
���̒m�b���g�����Ŗ������m������i�������j���l�ɁA�M��̐_�X�ƕ������K���i���イ�����j�����Ă��܂��������݂�B
�܂�A�����ł͗]�茩���Ȃ����݂����A�u�ꏏ�ɂ����Ă��܂��Α����͋N����Ȃ��v�ƌ����P���ȗ����ł���B
�{�i�I�ɐ_���K�����ׂ��ꂽ�͎̂����I�㔼���V���剤�i��������/�V�c�j�̌䐢�ɂ����āA�剤�i�剤�j�𒆐S�Ƃ��鍑���肪���������ɔ����A�_�����̎��_�ł������V�Ƒ�_�_�Ƃ��āA����獑����ɏd�p���ꂽ�_�X�������_�ւƍ��߂��A���̐_�X�ɑ��ĕ�����������h�ӂ�\���Ċi�t�����グ��悤�ɂȂ������ɐ_���K���͎n�܂�B
���ۂɂ́A���̐������@�𖡂���ĕ��@����삷��u��@�P�_�̒��Ԃł���v�ƌ������߂ɂ��A�u�_�������Ăі����Ⴄ�����œ���v�ƌ������߂ɂ��ޗǎ���̖������畽������ɂ킽��A�_�ɕ����̕�F���i�ڂ������j��t���܂łɎ������B
������{�n��瑁i�ق������Ⴍ�j�ƌ����A���{�̔��S���̐_�X�́A���͗l�X�ȕ��i��F��V���Ȃǂ��܂ށj�����g�Ƃ��ē��{�̒n�Ɍ��ꂽ�����i����j�ł���v�Ƃ����̂ł���B
����� �V�Ƒ�_�͕����ł͑���@���ƂȂ�A�����_�̑�\�i�ł��������_�i���_�_/�V�c�j���������F�i�͂��܂������j�Ȃǂ͂��̓T�^�I�ȗ�ł���B
�Ë��ƌ�������܂ł����A�V���剤�i��������/�V�c�j�̖����_�d�p�ɕ������������c��̒m�b���i������ł���B
�����{�����i�X�T�m�I�j�̎��ō݂邪�u���{���I�v�̏��`�Ƃ��ċL����Ă���f���j���i�{���V�j��/�X�T�m�I�̖��E�{�����j�́A�u�V���i�V�����j�̑]���Η�(�\������)�ƌ����n�ɋ����v�Ƃ���A�A�\�V�����́A�\�V�}����\�����Ƃ��������N�i�؍��j��ŁA�����E�{�����i�X�T�m�I�j�܂��͋�����Ӗ����A�؍��ɂ͊e�n�ɋ����R�ƌ������̎R�⋍���i�S�Y�j�̖��̕t�������Ȃǂ̒n�������݂���B
�܂�A�{�����i�X�T�m�I�j�́A���N�������o�R���ēn�������C�m�n�������i�C�l���E�����j���������ɐ���B
�C�m�����i���l��/�����j���N�����Ă���A��Z���i�V�̈ꑰ/�V����/�������j�̏W���Ŗ\��܂��B
�����Ő�Z�����͑��z�̐_�u�V�Ƒ�_�v�̌��ɒc�����āA�C�m�����̐N����h�����B
���̐킢�͉��S�N�Ƒ����A�u�W�����A�W�����v�ƊC�m�����̋����n�������čs���A�₪�āA���̊��������̑O�ɗ��҂͋����̑Ë����l����l�ɂȂ�B
�����܂ł��A�������Ă���͋����Ȃ��̂��B
���������̌�A�₪�ė��҂͘a���i����/�������j�Ɏ���A�C�m�������_�̎q���ƔF�߂�ׂ́u���̐ȁv���A��ː_�y�ł���̂��낤�B
���̘a���i����/�������j�������A�Â������I���A�u���a�̗z������n�ɖ߂����v�u�Ԃł���B
���̖ڏo�����ȂɁA�X�g���b�v�_���X�������ꂽ�Ƃ��Ă��A�s�v�c�͂Ȃ��B
�C�m�����͒�_�{���V�j�i�X�T�m�I�j�̎q���Ƃ��ĔF�߂��鎖�ŁA��Z���̒��ԓ��肵���̂ł͂Ȃ����낤���B
���̎�����A�u�C�̕������i���܁E���߁j�Ƃ��ǂޗl�ɐ������v�ƍl������A�[���ł���B
�]���āA�����y�ъ�˂̓�̐_�Ђ́A�V�̈ꑰ�Ɣ��l���̘a���̃V���{���Ȃ̂ł͂Ȃ����B
���������_�b�́A���Ȃ܂��������j���A���Q���J��Ԃ��Ȃ��ׂɁA�u���O�̐��E�v�ɕ����߂��c��̒m�b�ƌ�����B
�䂪���ɂ͌×����琭���̎����u���i�܂�/�Ղ�j���v�ƌ����\�����݂�A�B��Ƃ��Đ��������鎖���u���J��i�Ղ�j������v�Ƃ������B
�ڂ����͑�l�͂ŋL�q���邪�A�����Ɛ����̗��҂͉䂪���ł́u�_���v�Ƃ��Đ^�ʖڂɍl�����Ă��������̍��Ղ��c���Ă���B
�����Ė����a���ƌ�������i�������j�̐��_�����ő�́u���i�Ղ�j���v�ł���A�V���[�}�j�Y���ɖ������_�y���̐^���Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B
���́A�����̍���ԊC�݁i�������s�k�Y���j�̈�p�́A�L�O�̍��i�啪���j���F���_�{�i�F�������{�j�̌�_�̒n�ł������B
�����A�ׂ̉����s�i���̏��E�������̂��傤�j�́A���q���{����n���E�E�H����������܂ŁA�y���i�������j���̗̒n�ł���B
�ɐ��_�{�Ɏ����䂪�����̑��_�E�F���_�{�i�F�������{�j�͑啪���F���s�i�L�㍑�j�ɍ݂�B
�F���_�{�́A�����_�����_�i��������j�V�c���Ղ�_�ŁA�S���̔����_�ЁA�l���Ђ̑����̐_�l�ł���A�u�V�Ƒ�_���Ղ�ɐ��_�{�Ɏ����v�ƌ��������i���̍����_�Ђł���B
���_�V�c�̕�@�A�_���c�@�������ɍՂ��Ă���B
����ɂ́A�_���c�@�͉ˋ�̐l���Łu�ږ�ĂƂ̌��ˍ����Ōォ��n��ꂽ�v�Ƃ���b������
�܂��A�����_�����_�i��������j�V�c�ɂ��Ă��A����̌������ʂɉ����Ă͑��݂��̂��̂��s�m���Ȃ��̂ł����Ȃ��B
��\�ܑ�V�c�Ƃ���鉞�_�͎��ݐ����Z���ȍŌÂ̑剤�i�V�c�j�Ƃ������邪�A���_�剤�i�������݁j�E�m���剤�i�������݁E��\�Z��j������A�����̉����̗L�͎҂��W���������������A�����O�������i�_��/�a�/����j���ɂ����鐪�������̐_���n�n�Ґ��A�͓������̎n�c���ȂǏ��������藐��Ċ����Ȍ��ɂ͓����Ă��Ȃ��B
���_�剤�i�������݁j�E�m���剤�i�������݁E��\�Z��j������ɕt���Ă͎��т̈ꕔ���������_�V�c�Əd���E�ގ����鎖����A�����͈�l�̓V�c�̎��т��l�ɕ����ċL�q�����v�Ƃ��錩�����w�ҊԂɑ��݂��邩��ł���B
�m���Ƃ��Ēm����m���剤�i��������/�V�c�j�́A�u�l�Ƃ��}�i���܂ǁj���理������������Ă��Ȃ����ɋC�Â��đd�ł�Ə����A���̊Ԃ͌���ׂ̈ɋ{�a�̉����̊����������ւ��Ȃ������v�ƌ����L�I�̈�b�����剤�i��������/�V�c�j�����A���������P���̈�b�͑����ɂ��̐l���̐_�i���ׂ̈ɋL�I�i�Î��L�E���{���I�j�ɉ������ˋ�n�삳�ꂽ���e�ł���^�����Z���B
���_�V�c������̌�A��̐m���剤�i��������/�V�c�j�ł���m���吝���i���ق������݂̂��Ɓj�͍ł��L�͂Ɩڂ���Ă����c�ʌp���҂̓p���t�Y�q�i�����̂킫������j�c�q�ƌ݂��ɍc�ʂ����荇���A��ʂ��O�N�ԑ��������A�u�p���t�Y�q�i�����̂킫������j�c�q�̎��ɂ�葦�ʂ����v�ƌ����B
���{���I�ɂ͐m���吝���i���ق������݂̂��ƁE�m���V�c�j�ɍc�ʂ�����ׂɁu�p���t�Y�q�i�����̂킫������j�c�q�����E�����v�Ɠ`�����邪�A����ƂĎɍ\���ĉ\����T��u�c�ʂ̒D�������v�̐^�����A�u�c�ʂ̏��荇���v�Ƃ��đ剤�i��������/�V�c�j�́u���v���Y��ɋL�q���������Ȃ̂����m��Ȃ��B
����ɂ��Ă��A��_�ł��锤�����_�剤�i�������݁E�V�c�E��\�ܑ�j�͗��V�c�̂���l�Ȃ̂����A�F���_�{�̖{�a�̒����ɂ͒������Ă͂��Ȃ��B
�����ɂ��킷�̂́A�]���ʂɂ͒m���Ă͋��Ȃ���̍Ր_�A�u�䔄�i�Ђ߁j��_�i�����݂��݁j�v�ł���B���̍��E�ɁA���_�A�_���A�̗��_�͒����܂��܂��Ă���B
�䔄��_�i�Ђ߂̂����݂��݁j�ɂ��ẮA���̓��̌����Ƃł��ǂ��𖾂���Ă͂��Ȃ����A���_�剤�i�����������݁E�V�c�j�����ɐ����邩��ɂ́A���Ȃ�̑啨�i�����j�̐_�l�ɈႢ�Ȃ��B
���̕��я����A�P�Ȃ鑢�c���ԂɋN������u�C���M���[���v�Ƃ���w�҂����邪�A�����l����u�݂蓾�Ȃ����v�Ɣ���B
���̂Ȃ���{�ň�E��𑈂��ō��̐_�ЂŁA����ł͈��Չ߂��͂��Ȃ����H
���R�Ȃ���A�M����_�������ȏ�A���̕��я��ɂ͐_�o���g���A�R��ׂ����Ɍ�����肤�̂�����O�ł���B
�䔄��_�i�Ђ߂̂����݂��݁j�̐��̂�����Ȃ�����Гa�̑��c���ȂǂƂ��Ȍ��_���o���B
���̕ӂ�̍������炩�A����Ƃ�������邷��s���ł��L�����̂��͔���Ȃ����A���݂ł��F���_�{���g�ł��������䔄��_�i�Ђ߂̂����݂��݁j�̎Гa���u��̓a�v�ȂǂƌĂ�ł���B
���������̎Гa�̕��я��A�Гa�ɏ��Ԃ�U���������ł͔@���i�����j�ɂ��s���R�Ȉ�ۂ͐@���Ȃ��B
���̓�����͊ȒP�ŁA�����_�͕��̐_�l�ŗL��A���a�����̐�̎��_�ł���B
�܂茹���͍c���̉e�l�ł���B
����Ŏv���t�����̂��A�u�V�Ƒ�_�ϐg���v�������B
�����́A���a�̏ے��ł���V�Ƒ�_�́A�킢�̎��́u�ϐg�������p���A�䔄�i�Ђ߁j��_�ł͂Ȃ��낤���v�ƁA��y�Ȃ�ɑ�_�ɐ������Č����B
�V�Ƒ�_�͑��z�M�̐_�ł���A��n�̖L�����肤�_�k�����i�V�ꑰ/�V�����j�̏��_�ł���B
���̕��a�̏ے����A���\���{�����i�X�T�m�I�j�����V���ɂ���ė������A�V�Ƒ�_���j���ɒ��ւ��ĕ������ĈЊd�����B
�v���̌�p�����A�F���_�{�ɂ��킷�u�䔄��_�v�ł͂Ȃ����낤���B
���a�̐_�E�V�Ƒ�_�Ƒ����̐_�E�䔄��_���A�s���ɂ�����o���d�|�����B
���ɕ��a�ƍK�������̂��A����̖�ڂł���B
����ŁA����Ƃ��Ă͌��O�����҂�Ɍ��\�o���Ȃ��̂����炱���A���̑��݈Ӌ`������ł��Ȃ��B
����łȂ���A�䔄��_�i�Ђ߂̂����݂��݁j�͉i�v�ɓ�̑��݂ŁA�I����Ă��܂��B
����Șb���ł��邪�A����̓��{�ł��u���a���@�̌��O�v����A�R�����R���ƌĂׂ��u���q���v�Ə̂��ċ���l�ɁA���a�̐_�ɐ퓬���[�h�͎�����Ȃ�����ł���B
���̐��̗��t���Ƃ��āA������G�s�\�[�h������B
�����_���剤�i�������݁E�V�c�j�������ɐ旧���A�F���_�{�Ɋ�����ƁA�u�I�L�v�ɋL����Ă���_������A���_�剤�i�����������݁E�V�c�j����_�ł́A���オ�O�サ�Ă��܂��̂��B
�_���剤�i����ނ������݁E�V�c�j���_�Ƃ����߂�̂́A�V�Ƒ�_��u���đ��ɂȂ��B
����́A�䔄��_�i�Ђ߂̂����݂��݁j�C�R�[���V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j�Ǝv����̂��B
�O���_�i�~�n�V���̃��K�~�j�������邪�A���ɉ����āA���쑤�ɕ��a�̐_�A�V�Ƒ�_�Ɠ��i�̍ō��̌R�_�����݂���K�v���L�����͂����B
�_�b�̍��������v���ƁA���{�̕ϐg�̑��ɁA�ō��_���݂��Ă��ǂ��ł͂Ȃ����B
�F���_�{�̎�_�������_�ł���A�����_�͕��_�i��_�j�ł���B
�����Ĕ����_�͕�F�i�����_�j�ł���A�������傪�t�����F�ƂȂ�ƁA�����̊i�����_�ł���B
���_�i��_�j�䔄��_�i�Ђ߂̂����݂��݁j���������F�Ɠ���ƍl����ƁA�l������̂͂��ꂱ���䔄��_�i�Ђ߂̂����݂��݁j���u�V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j�̐퓬���[�h�v�ƕ������ė���̂ł���B
�������炪�̐S�ȏ������A�S�������Ђ̑��_�А��̓��ŁA��l���Ђ������_�ł���B
���_�l�ł����V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j������A�����_�̖��Ђ��S���ŕ��𗘂����ċ���͉̂��̂��낤���H
�����_�͂��̓y�n�̒���_�ł��邪�A��̐_�E�����_�̎�_���䔄��_�i�Ђ߂̂����݂��݁j���V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j�ł���A�����_���J�鎖�́u�V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j���J�鎖�Ɠ����Ȏ��v�Ɖ��߂ł��A�M�I�ɖ����������̂ł���B
�����䔄�i�Ђ߁j��_�i�����݂��݁j���ږ���Ɠ���l���̉\��������B
鰎u�`�l�`�Ɍ�����`�����̍��X�̈�ł����הn�䍑�̏����́A�u�ږ���v�ƋL����Ă���B
�����ږ���͓��{�̗��j���̐l�������A�ږ���͑嗤�E鰒鍑�������̉��i�I���j�������i������̉��j�ɏ[�Ă��\�L�ł͂Ȃ����낤���H
�䔄�i�Ђ߁j��_�i�����݂��݁j�͔䔄�i�Ђ߁j���i�q���m�~�R�g�j�Ƃ��Ă�A�����͔䔄�c���i�Ђ߂݂�/�q���~�R�j������Ȃ������߂��B
�l�܂鏊���A鰏��i�O���u�j�ɋL�ڂ��݂��Ęa���i�Î��L�E���{���I�j�ɋL�ڂ������u�ږ���v�ƌ����ŗL�̖������l���͑��݂����A�䔄�c���i�q���~�R/�䔄���E�q���m�~�R�g�j�Ȃ瑶�݂������ɐ���B
鰏��i�O���u�j�̋L�ڑS�Ă��u���v�̏[�ĕ\�L�ō݂�Ȃ�A��a���̍��i�����킲���̂��Ɂj�E��a���i��܂Ƃ̂��Ɂj�̓ǂݕ��̌ꌹ���A�הn�䍑(���}�^�C�R�N)�ł����Ă����̕s�v�c�������B
�ŋߐ��Ԃł́u�ږ�Ă̕�������o�����v�Ƒ呛�������Ă���B
�ޗnj�����s�ɍ݂�u����i�͂��͂��j�Õ��v������̌��ʁA�u�ږ���������Ƃ���铯�N��̌�����������v�ƌ����̂ł���B
���������������_���猾�킵�Ă��炦�A�ږ���͌Î��L�E���{���I�͖ܘ_�̎��A���{�̌Õ����ɂ͂܂������L�ڂ������A�����̐��j�ł���鰏��i�S�O�\���j�́u���Γ`���̘`�l�̏��i�ʏ́E鰎u�`�l�`�j�v�ɋL�ڂ���Ă���݂̂̑��݂ł���B
�ږ���̐��̂������m�łȂ��̂ɓ������ږ���̑��݂��m�肵����ŁA�u�ږ�Ă̕���������v�͊w�҂ɂ���܂��������Ȕ��z�ł���B
������ɂ��Ă�鰏��Ō������́u�ږ�āi�q�~�R�j�v���A���{�ł͉��҂��m�ɂ��Ȃ��Łu�ږ�āi�q�~�R�j�̕��v���������Ă�̂́A�y�����������ɘO�t��z�����̂ł͂Ȃ����낤���H
�����������{�j�ɑ���ԓx�́A���̑��݂��^���Ă�����j��̑n��l���E�������q�̑������L�ۂ݂ɂ���̂Ɠ����̑e���ȍl�����ł͂Ȃ����낤���H
鰏����L�ۂ݂ɂ������}���ɂ��葖�炸�A���̑O�ɂ܂��͔ږ�Ă��N�ł��邩�̓��������ׂ��ł���B
�הn�䍑�̍��Ƃ̉^�c�́A�ږ���̌����i�V���[�}�j�Y���j��w�i�ɍs�Ȃ��Ă����B
���̃V���[�}�j�Y���̍����A�������ׂ����݂��i�A�s/�̈Ӂj�������̂ł���B
�A�s�i��/���|���l�V�A��j�́A��Z�ڈi�G�~�V�j�̑�����h�������A�ꕶ���̗̎�́i�𑀂�w���ҁj�̑��̂ł���B
���̖��̓A�s�̖��i�A�s�~�R���c���j�ł���A�����c�q�i�q���R/�Ώ��c�q�j�Ƃ������B
�܂��הn�䍑�̏����u�ږ���v�͑��̂ŁA�ږ�Ăɂ͕ʂȌŗL�������������ł���B
���i����ȁj�͒����i�c���E�����E������j�Łu�j�����C�v�ł��邪�A�A�C�k��ł͛ޏp���i�݂����/�ޏ��E�݂��j�̎����I�C�i�E�J���C�ioyna �Ekamuy�j�ƌ����A���̃I�C�i�ioyna�j���u���i����ȁj�̌ꌹ�ł͂Ȃ����v�ƍl���Ă���B
���|���l�V�A��́u�A�s�i�̈Ӂj�v�ƃA�C�k��́u�A�s�F�i����e�E�̈Ӂj�v�͋��ʂ��Ă��āA�C���h�l�V�A��n�́u�A�s�i�j�v���������ł���B
��p�A��p�ɉ����ĉi���j�͏d�v�ȃA�C�e���ŁA���{��̉i�Ёj�́A�،�i�n���O���j�ł͉i�v���j�A����i�c�D���E�F���E�����j�ł͉i�t�H�j�ł��邩��A���u�q�v�Ɣ������鎖���u�A�s�v���a���āu�s�v�ɐ������\���������B
鰎u�`�l�`�i������j���Ӗ��������i�I���j��D�悷��u�ږ���i�c�����q�~�R/�s�~�R�j�v�Ə[�Ă鎖�͏[���l������B
�䔄(�q��)�͐_��̐_�i�����������ɑ��鑸�̂ŁA�㐢�̑�̕P�ɒʂ���B
�����ŋ�B�E�F���_�{�i�F�������{�j�ɒ����܂��܂��u�䔄�i�Ђ߁j��_�i�����݂��݁j�v���A�הn�䍑�̏����u�ږ���v�ŗL���Ă��s�v�c�͖����B
鰎u�`�l�`�́A�u�O���u�v�ƌ��������̐��j���ɑ��݂���u鰏��i�S�O�\���j�v�ɏ�����Ă���u���Γ`���̘`�l�̏��v�̗��̂ł���B
���{�ɂ����Ĉ�ʂɒm����ʏ̂��u鰎u�`�l�`�v�ƌĂ�ł����ł���B
�הn�䍑���ږ������Ȃ̂́A�ڂ����L�q�����̕����Ɍ�������Ȃ�����ł���B
�Î��L�E���{���I�ɁA�u�킴�킴�הn�䍑���ږ�����ڂ����������������v�ƌ����Ӗ��́A�הn�䍑���ږ�������͓n���O�̑c���̓`�����A��a�̍����הn�䍑�ł���u�䔄��_�i�V�Ƒ�_�j���ږ���ł���v�Ɖ��߂���A�킴�킴�ʂ��ږ�������グ�ċL�q����K�v�͖����B
�_�b�͌����ɗL�������ɁA��X�ׂ̈ɐ����I�ȏd�݂𒅂���ړI������B
���Ƃ���Ȃ��ږ�����V�Ƒ�_�Ɠ���l���ł���A�הn�䍑�����V���ŗL�����Ȃ�b�͍����I���B
���ޏ��A����q�A���c���Ȃǂ��u�q�~�R�v�Ɠǂ߁A�u�ږ���v��鰁i���j�̍����猩�āA�ډ��������J�̖�ȑ���������O��Ƃ����\�L�ł���A�B��̎����u鰎u�`�l�`�v�ɓo�ꂷ��̂́A���̏������͓��̍c���E�q�~�R�ɁA�ڂ̕������[�Ă��̂ł͂Ȃ����낤���H
����́A�ϐg��̐�̐_�A�䔄�_�q�i��_�j���i�Ђ߂݂̂��E�Ђ߂̂����݂��݁j�̖����A�ږ�āi�Ђ݂��j�Ɖ������Ă��鎖���������t���B
�E���ɑ�a���삪��������O�A���V���i�הn�䍑�j�́A��B�����̍��ɑ��݂����B
�����āA�C�m�����i�����j�E�{���V�j�i�X�T�m�I�j�̖��ɍU�ߍ��܂ꂽ�嗤�R�Ԃ����n�����i�V����/�������j�E�䔄���i�Ђ߂݂̂���/�הn�䍑�E�����j�͓V�̊�˂ł̎�ł����s���Ė����a�����ʂ������B
�{���V�j�i�X�T�m�I/�{�����j����z���i���Ȃ��Ɂj���הn�䍑�i��܂��������j�̘a���̌�A���הn�䍑���̖�������𗶁i��������j���đ�a���̍����u��a���i��܂Ɓj�v�Ɠǂ܂��A�}������ɑJ�s���ēs���F���_�{�c����B
�����̗��j���_��̎�����`�����Ă��āA���������͂�L���A���̌㓯�����C�ɖ{����u���C�m�����i�����j�n�����鎁�i��Ύ��j�ƍ������ċE���J�s�ւƌ����čs���B
���ł��́u鰎u�`�l�`�v�ɓo�ꂷ���הn�䍑�̏����E�ږ���́A�{���ɓ��{�̘`�̍��X�̑�\�҂������̂��낤���H
�������u�����Ɏc���Ă��邩��v�ƌ����Ă�����L�ۂ݂ɂ��A���j���ۂ̃V�b�|�̗l�Ɉꕔ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���ʓI�������I�Șg�g�݂���A���̐^���ɔ���Ȃ���ΐ���Ȃ����̂ł���B
�����̑嗤���̏�ł́A�הn�䍑�̏����E�ږ�����u���͂��Ƃ��ď]���Ă���v�ƌ����̂�鰒鍑���́u�����I�ߑ�]���v�ƌ������́A�[���ɍl�������������B
�הn�䍑�̏����E�ږ����鰒鍑�ƊO���W�i�𗬁j�������A鰍c�邩��u�e鰘`���v�ɔC�i�F�j����ꂽ�Ƃ��Ă��A����Ƃ͕ʂ�冒鍑����鍑�����݂����̂�����A���́u鰏��v�̓��e�Ƃ͕ʂ�冒鍑����鍑�ƊO���W�i�𗬁j�����ʂ̍������{�ɑ��݂��Ă��s�v�c�͖����B
���ؑ嗤��鰒鍑�A冒鍑�A���鍑�̎O�鍑�ɕ�������Ă����̂ł́A�e�X���ʂ̊O���W�i�𗬁j�������A�ʂ̓��{�ɑ��݂��鍑���u�`���v�ɔC�i�F�j���Ă��āA������̑�\�Ƃ��Ă���A�u鰎u�`�l�`�v�̋L�q��鰂ƊO���W�i�𗬁j�����הn�䍑�E�ږ�ĂɕЊ�����L�q�����Ă���\�����݂�B
���ɓ����̓��{�ɂ͑嗤�R�Ԃ̈��n�����i�V����/�������j���הn�䍑�Ƃ͕ʂɁA�C�l���n�i�����n�j�̍��A�Ⴆ�u��z���v��u�ɓs���v�����݂����B
���{�ɉ������P����{�����̐����ߒ��ŋN�������o�܂��A�n���n���������i���炼��/�_�k�R�x�����j�������i������/�C�m�����j�A���Z�ꕶ�l�i�ڈ�/���݂��j�O�b�̑������̒n���������ɋ��镔���Η�����̒m�b����a���ł���B
�O�b�̑������Ƃ́A�������i���炼��/�_�k�R�x�����j�n�̏ے����הn�䍑���ږ�āi�Ђ݂��j�ł���A�����i������/�C�m�����j�n�̏ے����A�_���剤�i����ނ�������/����V�c�j�̑c�E�X�T�m�E�i�{�����j����z���i���Ȃ��Ɂj�A�����������i������/�C�m�����j�n���ɓs���̉��E���鎁�i��Ύ��j�A�����ĉ������i���炼���j�E�����i�������j���n������ȑO����̐�Z���E�ꕶ�l�i�ڈΑ�/�G�~�V���j�n�̎O�����ɑ�ʂ����B
�����ĎO�����̈�n�A��Z���E�ꕶ�l�i�ڈΑ�/�G�~�V���j�n�̉������A�u���{�E���{�ꑰ�ł���v�ƌ������͂Ȑ�������B
����ł���a���̑�a��(���}�g�̍��j��F�߂Ȃ��̂́A�Î��L�E���{���I���V���~�Փ`�������c���j�ρi��������������j�ɓ��鍑�ƊςƖ����ςɔ����鎖��������ł���B
�܂�A�����̓��{���O�����O�b�̑������̒n������������A�������i���炼��/�_�k�R�x�����j�n�̎הn�䍑�̔ږ�āi�Ђ݂��j���䔄���i�Ђ߂݂̂��j���A鰎u�ɉ�����B��̓��{�̏����́A�嗤�u鰒鍑�v�́u�O���u����̍����I�ȑΏ��������v�Ǝv����̂��B
�܂�A�L�^�Ɏc���Ă��Ȃ������Łu�e���`���v�����݂��L�q���Ɍ������הn�䍑�̏����E�ږ���ƕs���ő������₦�Ȃ���z���̒j���̑��݂��A���ؑ嗤�O�鍑�̐��͑����ƘA�����Ă����\��������B
����̂ɓV��˓`���̐_�b�̋L�q�̗���ǂ܂��A�u鰏��v���L�ۂ݂ɂ��Ď��̘͂`���Q���הn�䍑�̑����ƌ��ߕt����̂́A�u�ɂ߂ė��\�Ȑ��v�ƍl���Ă��܂��̂ł���B
��y�̉��߂ł́A�הn�䍑�̏����E�ږ�����䔄���i�Ђ߂݂̂��Ɓj�̏[�Ď��ł���A�䔄���i�Ђ߂݂̂��Ɓj���V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j�ł���B
������A�ږ���ƕs���̊C�l���n�i�����n�j�̍��E��z���̒j�����{���V�j�i�X�T�m�I�E�{�����j�ł���A���\�Ȓ퉤�E�{���V�j�i�X�T�m�I�E�{�����j�ɍ������V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j���A����i�������j�������Ē��̗ǂ��o��i�����j�ɔ[�܂�_�b�̐��E�ɋ��ʂ��Ă���B
���̍��ł́A��i���ʁ����j�̕��������_�M���ɒʂ��A�������i���炼��/�_�k�R�x�����j�E�הn�䍑�肵�āu�_�����E��a�������N�������v�Ƃ���������n�i������/�C�m����)�E��z���i���Ȃ��Ɂj�̍����ɂ��g���Ă���B
�_�b�ɉ����ẮA�R�̖��E�V�Ƒ�_�ƊC�̖��E�{�����i�X�T�m�I�j�̖��́A����i�������j�̘a���������Ďo��_�ƂȂ����B
�����̒n�Ō���ɔj��A�����̓V��˂Ŏ�ł����s���A����i�������j�������āA�S�g�Ƃ��ɘa�����鎖�Łu���ғ���Ɍ��������v�Ƃ���Ȃ�A�h���}�`�b�N�ł͂Ȃ����B
����A�����͖����a���ׁ̈A����i�������j���Ȃ������A�V�ꑰ�̖��S����ׂɂ��A���_���ږ�āi�V�Ƒ�_�j����^�i���ǖ��j�ɗ^�����J��グ�A�u����͎O�Ԗڂɐ������v�Ƃ�����A���l�����{�����́A���X�̐����Ƃł���B
�퐶����i��悢�������j�́A�I���O�ܐ��I��������O���I�����܂łɂ����鎞��ŁA���̖퐶����i��悢�������j����̎O���I���̍���鰎u�i���Γ`�E�`�l�`�j�Ɂu�`�̏����E�ږ���v�̋L�q��������B
�L�q��������̂́A��S�O�\��N�̘`�̏����ɂ��g�Ҕh���Ɏn�܂�A�𐿂���鰂̖�����ږ�����u�e鰘`���v�Ƃ��āu����A�����Ȃǂ��������v�Ƃ���B
���̌��S�l�\�N��ɉ��x�������E�ږ���Ɋւ��L�q������A��S�l�\���N�ɂ��ږ���̍��i�הn�䍑/��܂��������j����z���i���Ȃ��Ɂj�ƑΗ��A���͕����i�푈�H�j�����Ă���B
��S�l�\���N�ɏ����E�ږ�������ɁA�j�����i������邪�����������A�ږ���̏@���E��^�i�܂��͑�^�j�������Ɛ����āu�Q�����������܂����v�Ə����L����Ă���B
�_�b�̐��E�ł͗L�邪�A�H���čs���ƈĊO�{�����k�炵�Ă��镔��������B
�L�q�ɂ��ƁA�V�̈ꑰ�́A���l���Ǝ�ł����s���A�V�Ƒ�_���X�T�m�I�̊Ԃ�����i�������j���Ȃ���A�u�V�E�䎨�i���܂̂����ق݁j�̖������܂ꂽ�B�v�Ƃ���B
���́A����i�������j���g�b�v���m�̐��������̈Ӗ��ł���Ȃ�A�X�T�m�I�̑���́A�ږ���̏@���E��^�i����j���L�͂ł���B
�܂�A���O�ɂ͈Ӗ�������B
�V��˂ɋ��鋆�ɂ̕����a���E�E����i�������j�̊T�O��O���ɐ�������ƁA�ږ���̌�p�E�@���u��^�v�̓ǂݕ��́A�u��ɗ^����v�̑��薼�ł���A�ږ���E��p��}�t�Ƃ�������i�������j�̘a�������H����ȑO�́u�ʂ̖����������Ă����v�ƍl������̂ł���B
�ږ���̎���A�הn�䍑�̍����߂��̂́A�u��^�i�܂��͑�^�j���v�Ɠ`������Ă���B
���̎��A�����E��^�i����j�́A�͂��\�O�Ƃ����B
��^�ƌ������O���炵�āA����u�n�߂ɗ^�����v�Ɠǂނ̂͋����߂��邩���m��Ȃ����A�ǂ߂Ȃ����Ȃ��B
�܂��A���̖����u��^�i����j�v���ł���A�����Ɂu�הn�䍑��^�����v�Ɠǂ߂Ȃ����������B
��������i�������j�Ő��܂ꂽ�V�E�䎨�i���܂̂����ق݁j�̖��̎q�����A�u���i���́j�x�ɂ��˕悪�݂�v�ƌ�����j�j�M�i���p�������Ȃ��̂ŃJ�i�����j�̖��ł���B
���̃j�j�M�m�~�R�g(�A���j�M�V�N�j�j�M�V�A�}�c�q�R�q�R�z�m�j�j�M)���琔���Ďl��ڂ��u�_���剤�i��������/�V�c)�ɂ�����v�Ƃ���Ă���ׁA�����_�����̎n�܂����z
���i���Ȃ��Ɂj���הn�䍑�i��܂��������j�́u�a���������ł͂Ȃ������̂��H�v�Ɠǂ߂�̂ł���
�_�k�����i�V�ꑰ�E�����n�j�̔��˂̒n�́A�����u�����嗤�암�A�_��ȁv�ƌ����Ă���B
�_��Ȃ̐l�X�̈�앶���A����ɂ܂�镗�K�A�`�����A�����グ��Ό����Ȃ��قǁA���{�̂��ꂼ��ɋ��ʂ�����̂������B
���̔_�k�����i�V�ꑰ�E�����n�j�������Ό��������Ėk�サ�A�����e�n�ɑ��Ղ��c���Ȃ��璩�N������쉺�A�C�߁i�݂܂�/�������j����A�X�ɑΔn���o�ē��{�̎R�A�n���Ƌ�B�k���ɏ㗤���ďW����z���A�₪���הn�䍑���`�������čs�����̂��B
�_��Ȃ̉Ƒ��̌n�͐̂��珗�n�ł���A�Ƃ͏������p���A�j���̕v�͐��Ƃ���ʂ��ė���ʂ����v�������B
�V�ꑰ���_�k�����i�����n�j�Ȃ�A���n�����ɂ��������̂�������O�ł͂Ȃ����B
���̓V�ꑰ���A���N�����Ɏ���܂łɔ_�k�����i�������j�Ƃ��đ嗤������~���Ă���A�ɓn���ė����l���B
����ɑ��āA�C�m�����i���l���E�����n�j�̔��˂́A���肪�ނ��������B
�C���h�l�V�A�A�|���l�V�A�A�~�N���l�V�A�Ȃǂ̓���̓��X�̌��Z�������A�u�����ɏ���ē��`���ɖk�サ�Ă����v�Ƃ�������L�͂ŁA���ꂪ��B�암�ɑ��������ɏ㗤�����̂��낤���B
�A���ܘ_�A�C�߁i�݂܂ȁj���ɋ����Ă͉����i�J���j����߁i�J�i�j�Ƃ��ĂԖ�ł����邪�A�C�߁i�݂܂ȁj�̍����̂��̂̍������_�k�����i�������n�j�ƊC�m�����i�����n/���߁E�J�i�j�͍��݂��A���{���l�ɔe���𑈂��V���i�V����/���炬�j�Ɍ㉟�����ꂽ�_�k�����i�������j�ƕS�ρi�y�N�`�F/������j�Ɍ㉟�����ꂽ�C�m�����i�����j�Ƃ̐��͑����͑��݂����B
����ŁA���l�n�́u�����v�̗l�Ɉ�U�����嗤�ő卑�i���鍑�j�����A�������g���ē��{�ɓn�����ė����ҒB������B
���ɓ`���Y�����{�`���Ȃǂ́A���̖��c�Ƃ���Ă���B
���̔_�k�����i�V�ꑰ�E�����n�j�ƊC�m�����i���l���E�����n�j�ƌ�����̂܂������Ⴄ�������A����̃��[�g���o�ċ�B�̒n�ő������A������ׂ̓y�n�������Ĕe���𑈂��B
���̑����̊��Ԃ��A�_��̎��ゾ�����̂��B
���{�̎����������i�|���l�V�A�j�n�����Ɖ������i�����_��Ȕ��˂̎R�̖��j�n�����̓�n�������݂���؋��́A�����ƌĂ�镶���̓ǂݕ��ɂ����c���c���Ă���B
�Ⴆ�Ό��i�͂�j�̕����́A�����i�|���l�V�A�j�n�́u�C�̖��v�����i�o���j���u�͂�v�Ɠǂ݁A�������i�����_��Ȕ��ˁj�n�́u�_�k�����i�R�̖��j�v�̌��i���F���j���u����v�Ɠǂނ̂ł͂Ȃ����낤���H
����Ȃ��C�F�E�R�F�̖��b�`�����A�������ė���̂ł���B
���{�ɓn�����������n�C�m�������A��B�k���Ř`�̍��X�̈�z���i�Ȃ����j��B
���̓z���i�Ȃ����j���A�n���n�Ȃ��畔�����Ⴄ�ږ�āi�䔄��_�E�V�Ƒ�_�j���w�������_�k�R�x�����E�������i���炼���j���הn�䍑�i��܂��������j�Ɉꎞ���͈������ꂽ�B
�₪�ēz���i�Ȃ����j�͋�B�암�Ő��͂�Ԃ��āA�C�m�������ƁE��z���i���Ȃ��Ɂj����������B
���̋�z���i���Ȃ��Ɂj�����͂𑝂��ċ�B�암�E�����E�l���E�I�ɔ����암�ɓ���L��Ȓn����x�z���A�ږ�āi�䔄��_�E�V�Ƒ�_�j�̎הn�䍑�i��܂��������j����������B
�����V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j���{�����i�{���V�j�j������i�������j�ɓ���u�V�̊�˂̉��v�ւ̌o�܂��A��吨�͂ɕ�����Đ�����`���嗐�ł���B
�`���嗐�̌��́A�u�ږ�Čn�̎הn�䍑�v�Ɓu�X�T�m�E�n�̋�z���i���Ȃ��Ɂj�v������̖��ɋ�z���������c���ė����{��E�_������ł����Ă��o�܂ł���B
���̓V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j�Ɛ{�����i�{���V�j�j�̐���i�������j�ɓ���u�V�̊�˂̉��v�ւ̌o�܂��A��吨�͂ɕ�����Đ�����`���嗐�i�킱���������j�ł���B
�`���嗐�̌��́A�u�ږ�Čn�̎הn�䍑�v�Ɓu�X�T�m�E�n�̋�z���i���Ȃ��Ɂj�v������̖��ɋ�z���������c���ė����{��E�_������ł����Ă��o�܂ł���B
���̌����n�C�m�������ƁE��z���i���Ȃ��Ɂj�ƌ���������ǂ����Ă��炦�Έ�ڗđR�ŁA��a���삪�i�߂��C�����Ƌ�z���i���Ȃ��Ɂj�͑傫���ւ�肪����B
�����Ĉɓ���������ɓ������ɋN���������������n�C�m�������ƁE�ɓs���i���Ƃ����j
���������A���̎w���ҁE��Ί���ꑰ����a������d����S���Ȃ���A�C�����̎w���҂ƂȂ�B
�C�����̃C���[�W�V���{�����V�灁�i�Ă�̂��ʁj�ł���A�����҂̓s�����ǂ��`����U��܂����C���҂̖ړI�������V��C�����̕ʖ����u���_�l�i���ʂ��݂��܁j�v�ƌ����B
�܂�A���{�ɓn�����������n�C�m�������z���i�Ȃ����j��A���̓z���i�Ȃ����j�͈ꎞ���͎הn�䍑�Ɉ������ꂽ���A�₪�Đ���Ԃ��ĊC�m�������ƁE��z���i���Ȃ��Ɂj�������A���̋�z���i���Ȃ��Ɂj�����͂��܂��Ďהn�䍑�������A����i�������j�ɓ����ė��҂�������ׂ��ē��{�̐��������_�����E��a����̊�b�Ɛ������̂ł���B
�₪�āA�V�̈ꑰ�E���l���A���́A�����{���ꍑ�ƂƂ��Ă̑�a����Ɏ���A�_�����J�i����ނƂ�����j�����̌o�܂�H���Đ��̒[��B����A�����̒n�u�E���v��{���n�ƒ�߂����A����V�c�A�_���剤�i�������݁E�V�c�j�����ʂ���B
�L�q�ɂ��ƁA���ʂɓ����Đ_���剤�i�������݁E�V�c�j�͋�B�́u�}���v�̒n���A�u���|�v����u�g���v���o�āu��a�v�ɁA�������Ƃ���B
�u��a�̍��v�̉����A�������u�הn�䍑�v�̉��Ɏ��Ă���̂��B
���̃��}�g�̉��ł��邪�A�������̔����Ŏׁi���[�j�n�i�}�[�j��i�g�D�j�Ɣ����������̂ŁA��a�͂��̏[�ēǂ݂ƁA��y�͍l���Ă���B
���̂Ȃ�A�ʏ�g�p����ɑ�a�̕����́A�_�C���Ƃ����ǂ߂Ȃ��B
�������̔����ł���i�^�@�[�j�a�i�z�H�j�ł���B
������A�_�C���i��a�j�Ɂu���܂��͒���v�����ď��߂āA�u���}�g�m�N�j��A���}�g�`���E�e�C�v�Ɠǂ܂���B
�����̓����a���i�_�����j�́A�����̉��Ƃ̘A���̂ŁA���̑�\���剤�i�������݁E��ɂ͓V�c�j�ł��邪�A�{���ł͕X�セ�̑��̗L�͕�������b���i���݂����j�ƌĂԁB
�u�ŏ��̒��삪�J���ꂽ�v�Ƃ����i�������E�������j�́A���݂̓ޗnj����s�S���������ӂ���w���n��̖��ł���B
�Z�S�N��㔼�܂ŁA�V�c�i�剤�E�������݁j�̋{�͂��́u�i�������E�������j�̒n�y�т��̎��ӂɂ������v�Ƃ���Ă���B
���ÓV�c�̖L�Y�{�ł̑��ʂ��玝���V�c�̑�̓����{�ւ̈ړ]�܂ł̂��悻�S�N�ԁA�剤�i�������݁E�V�c�j�̋{���u����鎖�������u���{�̐����̒��S�n�ł������v�Ƃ����B
�n���ɂ��Ȃ�ł��̊��Ԃ̑O����܂�œ��{�̗��j�̎�������Ə̂���B
���݂ł͖���������сA�����͊w�҂ɂ���Ă͂��̋ߗׂ܂ł��܂�ŔƎw�������������邪�A���㓖���͂�苷���n����������̂ł������l�ł���B
�Î��L�ɂ́A�卑��̖��i�������ɂʂ��݂̂��Ɓj�ʖ��单�l���A�u���������i�o�_�̍��E�������j�𒆐S�Ɏ��߂Ă����v�Ƃ���A��ςȑP���Łu������сA�����h�����v�Ƃ���̂��B
���̌�A�V�Ƒ�_�Ɂu�o���オ���������������B�v�Ƃ���B
���a�Ɂu������i���ɂ䂸��j���s��ꂽ�v�ƋL�q�ɂ͂��邪�A�����W�́A����Ȃ��B
�^���̏��A�E����ď�����ꂽ�̂��A���邢�͔[�����ď��鎖�̏o���鑊�肾�����̂��͓�ł���B
���́u�卑��̖��v�̎��߂�u�����̒����v�́u���Í��v�Ƃ��Ă�A���Â̈Ӗ���V��́u���V���v�ƁA�n���́u����i��݁j�̍��v�̊ԂɈʒu����̂ɁA�u�����i�Ȃ����Ɂj�v�����́u���Í��i�����j�v�Ɛ���A�����u�n��E���w���v�Ƃ�����������B
����ł���A�卑���͒n��E�̔e�҂ŁA���Ȃ��Ƃ��u�Ñ���{�̔����߂��ꂵ���剤�ō݂����v�ƌ������ɐ���B
����͓��{����́A�ے��I�Șb�̈�ł���B
�卑��̖��i�������ɂʂ��݂̂��Ɓj�͌����܂ł��Ȃ��L�͍����i���E�b���E����/���ɂʂ��j�B�𑩂˂�剤�i�������݁E��̓V�c�l�̎��ł���B
�܂�A���{�̘`�̍��X�̑����̍���i���ɂʂ��E�n���̉��j�𑩂˂�҂̖��̂��卑��̖��i�������ɂʂ��݂̂��Ɓ��剤/�������݁j�ƌ������ɐ���B
�������Ă����`�̍��X�̏����Ƃ̍���i���ɂʂ�/���j�̓���̏ے��I�ȑ��݂Ƃ����卑��i�������ɂʂ�/�剤�E�������݁j�̑��̂����܂�A���͂ł͂Ȃ����_���E�Ō�������ׂɁA�V�ƒn���̊ԁu���Í��i�����j�v�ɁA���{�͐������̂ł���B
�o�_�_�Ђ́A�����卑��̖��i�������ɂʂ��݂̂��Ɓj���Ղ��Ă���B
���݂Ɏ��鍡���܂ŁA���̑卑���c��Ƃ��閖�Ⴊ�_��Ƃ��čՎi���i���Ă���B
���̏o�_�_�Ђ̔q���@�́A���̐_�ЂƈႢ�A�u���A�l����A���v�Ɛ����Ă��邪�A���ꂪ�A�F���_�{�Ɠ����ł���A�S���ɓ��������̍�@�͂Ȃ��ׁA�傫�ȁu��v�ł���B
�o�_�̍��i�������j�̐��ׁA���B�i�R�����j�̓��{�C���ɁA����A�����S�u�{�����v�͂���B
�u�{���������̒n�v�ƍl������B
�{�������瓌�ցA�܂�o�_�����֖߂�ƁA����������S���c���ɏo��B
�����ɂ́A�{���V�j�i�X�T�m�I�j�A�������{�����i�H�j���Ղ鏬�ЁA�{���_�Ђ�����B
�{���V�j�̖��̌��i�݂��܁j���Ղ�_�Ђ́A�u���ɂ͂Ȃ��v�ƌ����Ă���B
���́A�I�B�F��Ɋi��̑�ЁE�{���̒j�_�Ђ�����B
������������A�F���_�{����ɐ��_�{�̗l�Ɍ�ɍ��c����F��Ɉڂ��A�u�i�グ���c���ꂽ�v�ƍl�������B
�{���A���c�A������̒������{�C���i�R�A�n���j�̑Δn�C���i�����j�̗��ꉈ���ɂ���B
���̊C���ŁA���̒n���͓~����r�I���g���ƌ����B
����A�C�m�������㗤���Z�ݒ����Ɂu�s���R���v�͖����B
�����̒���_�Ђ́A�n���I�������炷��ƁA���������i�o�_�̍��j�A�������卑��̖��i�������ɂʂ��݂̂��Ɓj�̓`���ƁA�����n��ɓ�����B
���c���̒������ׂ͏o�_�s�ł���B
�{���_�Ђ́A�قƂ�Ǐo�_��ЂƂ͓����n��̗��n�ŁA�{�������卑���̊֘A���Ɋm�M�����Ă�B
�卑���̈����������A�{�����i�X�T�m�I�j�`���Ɍq���肪�L���Ă��ǂ��������B
���������i�o�_�̍��j�̍ő�̐��͔͈͂́A�u�R�A�A�k���A�z�A�M�Z�ɋy�v�Ƃ���B
���ɁA�Ñ�̑卑�ł���B
���̓��{�C���݂���͒n�ՂƂ���卑�́A�����C���̗���ƕ�������B
�܂�A�o�_�̍��ɐ{�����i���l���j���������ɐ���B
����������ƁA�卑���ƁA�{�����̗��҂͓������H����ł���A���낪�����B
����́A�ږ���i�V�Ƒ�_�j�̏o���ɂ��Ẳ\���̘b�ł���B
�ږ�����הn�䍑�́A�����ɂ������̂��H
���{�j�̑傫�ȓ�ł���B
���{�̗��j�w�҂��Ƃ́A�l�X�Ȑ��\���Ă���B
�������Ȃ���A�����͋����ɁA����������{���̉���������i�����j���Ă���B
�����A�Ñ㒆���̎j���ƌÑ���{�̎j���̑o���ɁA���͖��m�ɓ���Ɣ��f�ł����ږ���炵���l���⎖�����L�ڂ���Ă͋��Ȃ��B
�܂��ږ���́A���{�ɂ�����u������̗��j�v�̎n�܂�ȑO�̓`���̉\��������̂��B
�ږ���ɊY������l�������m�Ȍ`�œ��{�̎j���Ɏc���Ă͋����A���{�̐l���ł��鎖���ؖ�������͔̂�������Ă��Ȃ��B
鰎u�`�l�`���`����`���E�הn�䍑�̊e�������A���{�̎j���ɑS�������Ȃ����ɂ��A�ږ�����p�����鐭���́A�u�O���I�����`������ɒf�₵���v�Ƃ����������B
�������A��y�̐��悤�ɁA�Ñ�E�L��`�̍����u���N���������܂�ł���v�Ɛ���ƁA�b�͐�������Ă���B
�܂荂�V���i�הn�䍑�j�́A���{�ɂ���ė��������������B�̉߂��Ă̌̋��A���N�������́u�ǂ����v�ł���A�ږ���i�V�Ƒ�_�j�́A�ނ�̌h������ꉤ�܂��͉��܂ł���\�������シ��B
���̋^����v��ƁA���炩�̎���Ō̋���ǂ�ꂽ�A�����ŗL�͂������ږ���̕����A�V�i���܁j�ꑰ�i�_�k�����E�������j���A���傤�Ǎ�������i�Ӊ�����}�Ɩё��Y�}�j�ɔs��đ嗤�����p�ɐ��{���ڐ݂����Ӊ�����}�̂��Ƃ��ɁA���J�̓��{�ɐ����ڐ݂��ė��āA�V���ɍ��i�S�����{�H�v�`��a����E�j���J�����B
�����āA�����������������������{������i�������j�Ɛ퓬�ŏ���������̓�����݁A���ꂼ��̖����̌̋����v���C���������߂Đ_�X�̍������B
���́A�B��̑����������ׂ̈̍��ӂ��A���P���ɂ��u�_�̍��Ɏ��Ȃ��̂͋��Ȃ��v�ƌ����A���_�I�M���W�̌��O�̍\�z�ł͂Ȃ������̂��H
�e����q�A���ԓ��ł̘̐b�����p����Đ_�b�ɂȂ�B
���R�Ȃ���A�l�X�ȋ��P�╔���I�Ȍւ���A�������̂��y���܂��Ȃ�����p���ړI�̌��ɁA�b�́A�u��肭�o���������b�v�Ƃ��č���鎖�ɂȂ�B
����̐_�b�̐��E�́A�[�����Ő��������Ă��邻�̖����̍��ӐS���ł���B
��y����a����������̂́A���̔����ȁu�@���v�������B
�u�L�I�i�Î��L�Ɠ��{���I�j�v�ɂ́A�����������̂��M�b�V���l�܂��Ă��邩�炱���A�ʔ����̂����m��Ȃ��B
�܂�u���{���I�E�Î��L�v�̓��e�ɂ́A�i�������������ꂼ��̉ߋ��̓`�����A�����I�z�����������Ȃ�����j���Ƃ��Ă܂Ƃ߂��A���j�̂��Ƃ������Ă��鋰�ꂪ�u�����ɂ���v�ƌ������ł���B
���̏�A�Î��L�E���{���I�̑傫�ȕҎ[�ړI�ɁA�����V�c�i����ނĂ�̂��E��\��j�̈ӎu�ł���u�V�c�i�剤/�������݁j�̐������v����X��������ׂ́u�v�f���݂��Ă̎��v�ƌ������������Ċ|����Ȃ����ɂ́A�Î��L�E���{���I�̋L�q���e���L�ۂ݂ɂ͎��Ȃ��B
�u�L�I�i�Î��L�Ɠ��{���I�j�v�𐳎j�Ƃ��Ĉ������ǂ����͂����������̎p���ŁA��y�͂܂Ƃ��Ȍ����҂ł͂Ȃ����炻�̕ӂ�����u�������B�������Ȃ��B�v�Ƙ_�c����C�͌��X�Ȃ��B
�X�T�m�E�i�{�����j�́A���C���̂悤�ɍU�ߓ������㔭���������̏ے��ł���A�䔄��_�i�Ђ߂̂����݂��݁j�́A���a�̐_�i�V�Ƒ�_�j�����_�ɕϐg���鎖�Ō㔭���������ɑR�����Z���́u�V���[�}���̓����ҁv�ƍl������B
�����A��Z���̖��������҂ƔF�߁A�S������ɂ́A�u��p�I�\�́i���́j�v���K�v�������B
�����āA���̎�p�I�\�̗͂v��������i�������j�ɋ����ė��҂��������Ă��A���̐��_�̒��ɖ��X�Ɛ����Ă����B
�N�����o���A���{�̐����{���_���剤�i����ނ�������/�V�c����j�̉��ɑQ�����������B
���������̓���剤�i�������݁j�A�L�͕������Ƃ̘A���̂ŁA�剤�i�������݁j�͊e�������̔F�ɂ��ō��ʂɉ߂��Ȃ������B
�����ŁA���ғ����̌�ɂ��̖��ӂ�͂�ő䓪���ė����̂��A�C�m�����E���鎁���i��Ύ����j�̕�u�����̐_�i���Ƃ���ʂ��̂��݁j�ƈꌾ��̐_�i�ЂƂ��Ƃʂ��̂��݁j�v�ƌ�����_�ł���A�����̐_�i���Ƃ���ʂ��̂��݁j�́u�_��L���ɑ��낤�v�ƌ�����p�ƁA�ꌾ��̐_�i�ЂƂ��Ƃʂ��̂��݁j�́u�_�̈ӎu�����v�ƌ��������i��p�j�̐_�l�ł���B
���������̒��玁��ɂ��n�������̗��j�I�o�܂���A���{�̌R���g�D�́A����u�����v�ƌ������̌������\�����鎄���i�R���j���P�ʂɐ���A���{�ɂ��������ȌR���g�D�̗��j���n�܂��āA���ꂪ�قږ����ېV�Ɏ���܂ł̉i���ɓn���Ċ�{�ƂȂ��Ă���B
�܂�A�`�̍��X�̎��ォ��A�u���������̒��v�𒆐S�Ƃ����R���g�D�i�����j���A���̂܂܃s���~�b�h���\�����ď������\�����Ă����B
�����āA���̏��������̎�������ۗL���Ȃ���ŏI�I�Ɍ܃����ʁi�܉������j�ɓ������A���̒��i����E�����݂��ǁE��̐b���j�B���W�����đ�a������\�����A�剤�i�������݁E��̒�E�V�c�j��u�����B
���̌o�܂���A�V���[�}���i��q�j�I�ɐ_�������č��Ɖ^�c���i��剤�i�������݁E��̒�E�V�c�j�́A�Ǝ��̌R���g�D���������A�����́u�閧�x�@�v���u����H��g�D�v�ł���A�z�C���g�D�ȊO�́A�����̎����i�R���j��K�v�ɉ����Ē��W����`�Ԃ�����ċ����B
�剤�i�������݁E��̒�E�V�c�j�́A���a���F��A�L��������č������߂闧��ł��邩��A�Ǝ��̌R���g�D��ۗL���鎖�́A���̑��ݗ��O�ɉ����ē���܂Ȃ��B
�܂�A���͂������Ȃ����O�̑剤�i�������݁j�̖�ڂ́A���Ɠ���ׂ̈ɋF�鎖�ł���A���݂��c���ɑ��`����A����ɂ��s�Ȃ���u�_���V���v�̊�b�́A���́u��p�A���f�̏W�听�v�ƌ�������̂ł���B
�]���āA���㎞��ō��������ϑJ���Ȃ�����A�����̏����A�`�̍��X�̊ϔO�����̂܂ܑ������āA�n��̌ď̂����̂܂܁u�����̍��v�ƌĂсA���̒����u�������E����E�����̎�i���݁j�v�ȂǂƌĂ�ŁA���̒n�����߂钷�������i�R���j��ۗL�����܂܂̌`�Ԃ��A�����ېV�܂Ŗ��c�𗯂߂Ă����̂ł���B
��
|
 �y�Ñ㍑���E�הn�䍑���ږ���z��Җ{���E��ؕ����\���y�[�W�y�T�C�g�i�r�z�ɖ߂�B
�y�Ñ㍑���E�הn�䍑���ږ���z��Җ{���E��ؕ����\���y�[�W�y�T�C�g�i�r�z�ɖ߂�B �y�Ñ㍑���E�הn�䍑���ږ���z��Җ{���E��ؕ����\���y�[�W�y�T�C�g�i�r�z�ɖ߂�B
�y�Ñ㍑���E�הn�䍑���ږ���z��Җ{���E��ؕ����\���y�[�W�y�T�C�g�i�r�z�ɖ߂�B