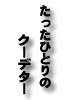���d�ɂ���y�́A���̕���E�c�����K�̉e�l�Łu���{�l�̑�̓h���}�v�������n�߂Ă��܂����B
����ƐF��Ȃ��̂������čl�@���ʔ��������Ă͗������A�C�ɐ��鎖���������Ă͗��j�̒T���҂Ƃ͌����Ȃ��B
���ʂ̐l�Ԃ��v�l����ƁA�����g������ʓ|���������ĒP���Ȕ����̓����Ō����𒅂�������B
�܂��A���̐����������ׂ̈ɕ�������L�ۂ݂ɂ��āA�v�l���~���Ă��܂��������X�݂�B
�����������̖{���͂���ȊȒP�Ȃ��̂ł͖����A���̗��ɂ܂őz����y���Ȃ��Ɩ{���̐^���ɂ͒H�蒅���Ȃ��B
�܂�������[���l�����A�s�m���ȓ`���Ŗ������Ă���l�Ԃ͗]��m�I�Ƃ͌����Ȃ������m��Ȃ��B
���{�̗��j�ɂ��u���v�Ɓu���v���������Ă���B
�n�������̒��͐�̒n�̓����̍������������ׂɐ_�𖼏���Ό��͂����荪���ɂ����B
�@���𐭎��ɗ��p�����茠�͈ێ��ɗ��p����͓̂��R�̔��z�ł���B
��̑��i�吼�m�푈�j���푈���s�ׂ̈Ɂu�펀�����������_���Ő_�Ƃ����J����v�Ƃ܂��ɔ��𗘗p���č����ɍ��荞����������B
�u���i����/�����j�v�̌��ۂōl������݂蓾�Ȃ��u�s�v�c�Ȍ��ۂ��N�������v�Ƃ���鎖���u���i����/�����j�v�̌��ۂŁA�����̖ړI�͓���̐l�����J���X�}�i���l�j����n�����鎖�ł���B
���́u���i����/�����j�v�̌��ۂ����p�����Ɓu�_�b��M�̐��E�v�Ȃ̂����A�V����(�Ă�ނĂ��j�`������(����ނĂ��j�ɓ���c�����Ҏ[�����u�Î��L�v�Ɓu���{���I�v�́A���ɍc���ɋ��铝����⊮����u���i����/�����j�v�̕����𑽂��܂�ł���B
�܂�J���ׂ��́A���{�j�̈���펯�i���傤�����j�Ƃ���钆�ɁA�u���i����/�����j�v�̗��j��������O�̗l�ɍ��݂��A����������N�C�Y�ԑg���Łu�����v�Ƃ���Ă��鎖�ł���B
�Ƃ͌����A�`���E�`���̗ނ́u���v�����m��Ȃ����A�����ɂ͂��́u���v���L�߂��҂̈Ӑ}���݂������ŁA�������W�߂čl�@���鎖�͎��R�ȍs�ׂł���B
�V�q�剤�i�Ă�������/�O�\����V�c�j�������̎�i�Ƃ��āA�����������p�i����̂����ʁj��o�p�A��������A�z�C���g�D��ݒu�����B
���p�i�����ʁj�̉A�z�C���g�D�ɁA�V�q�剤�i�Ă������݁j�͓��ꍑ�ƂƂ��Ă̋��ʔF���ƐM�S�������������閧�x�@�����H��@���Ƃ��Ċ����������ċ����B
���̔閧�x�@�����H��@�ւ��A�����V�c�i����ނĂ�̂��j�͐����ɓV�c�ƒ�������s���̒����ł��钆���ȂɁu�A�z���v�Ƃ��Đݒu���Ċ��p�����B
�S�`����n�삵���u����v���u�A�z�����A�z�C���g�D�v�̈Ӑ}�́A�u���O�̎v�z�F���̗U���v�ł���B
�č��̍����f�搻��Łu�������Ɏc�E�ȃC���f�A���̏P���v��`�����Ŕ��l�̔Ƃ������~�Ȑ����J���@�𐳘_�����āu���l�͐����������v�ƍ����ɔF���������̂Ɠ��l�̑_��������B
�א��҂����O�Ɍ��z�▲���������A���̖��O�̍s�����ՁX�Ƒ���ׂɑn�삳�ꂽ�u�t�F�C�N�`���v�̊g�U��i��M���ĖړI��B������B
���̎����ƈႤ�`���_�b�̝s���̗��z�Ɉ˂�s���̗ǂ��b��Ŗ��O������Ő��킵����铝����@�͓ƍوא��҂̓��قȎ�@�ł���B
���̓ƍوא��҂̓��قȐ��@�́A�R�ɉR���d�˂Ė��O��j�łɓ����u�푈�v�ƌ������j�I�ߋ������̂Ől�X�͘b�ɏ���Ă͂����Ȃ��B
�䂪���ł́A�������̂��āu���v�ƌĂԕ��K�����邪�A����͖{�����́i�Ԃׂj�����Ӗ��ł͂Ȃ��B
������u���́i�Ԃׂj�v�Ǝ��̂͗��j�F���̌��@�ł���B
���͂��́u���v�A���ɗR�����������_�̎��ł���B
���͂܂�T�i�������݁j�ŁA�T�_���ɉ����ĘT���u�_�̎g���ł����v�ƌ����v�z�͂ǂ����痈����?
�ǂ��������E�C�����ɂ��̌����L��B
�߂��āA��w�̔��B���Ă��Ȃ�����A�����̊Ԃł͎���_�Ёi���K�j�Ɠ������炢�C�����t�i�R���j�͏d�v�ȑ��݂������̂ł���B
�́A�a��\�����ʉ���́u�M�i�����j��v�ƍl�����A�f�p�ŐM�[�������͋���Ă����B
�܂�A�R�[�����ɂ܂ŕ�������C���̎R���́A�~�肩�����M�i�����j����������ׂ́A�u�����̗���b�゠�鋒�菊�v�������B
�����C�����̎R���B�́A�n�������l�X�Ȓm���Ə@������g���Ď��f���s���A�����̕���������ĐM�������������B
����������A��Ղł���B
���̊�Ղɂ́A���݂͎��m�̎����ƂȂ��Ă���A���m��w�̐g�َ̂̒h���ɂ�鎡�Ì��ʁA�j�����ÁA�Ȃǂ��܂܂�A�����Ƃ��Ă͌��I�ȉ��ʂ��u��Ձv�Ǝ����������������B
�܂��C���i�R���j���t�́A�f��u�u�b�V���}���v�̂��Ƃ����m�̏Ռ����A��ՂƂ��ĐM�Ɍ��т���U���������B
���R�Ȃ���A�l�Ԃ͖��m�̌��ۂɈؕ|��������B
�����A�����������Ïp�́A�嗤���疧���n�����Ɣ��ɂ����炳�ꂽ�C�����t�A�C���m�i�R���j�̓Ɛ肷�銿����p�ł���A�����́A�u���ꂾ��l�́A�̂ɐG�ꂽ�����ŕa���������v�Ƒ傰���Ɍ��`����A�M�̑ΏۂƂȂ����B
���ꂪ�A���ォ�̎����o��ƁA���O�̐S�̒��ň�l�������A���݂ł͓��m��w�̐g�َ̂̒h���ɂ�鎡�Ì��ʁA�j�����ÂƂ͂��̑��݂�m����A���т��鎖�͖����B
�܂��A�_�O���J�i�������j�ɉ�����C�����̑喃�i�����ʂ��j�́A�C�����́u�F��E���i���j���s�v�ł��g���Ă����B
�喃���i�}���t�@�i�j�́A�^�������̉��c�E�`�x�b�g�����i���}���j�̒n�ł����q�}�������n����Ŏ��R�Ɏ������Ă����ł���B
���R�Ȃ��疧���E�C�����t�i�R���j�́A�喃���i�}���t�@�i�j���āi���j�ׂ���̉����z�������l��������p�������N�������������ΐM�Ҋl���ɗ��p�����B
�喃���i�}���t�@�i�j�œ�������Ό��o�����A�����f���Ő^�ʖڂȐl���قǁu�M�̊�Ձv�Ƒ�����͎̂����̗��ł���B
�܂薧���ł́u���i���j���s�v�̓����̒��ŁA���ƏC�����t�i�R���j���@���Ȃ�����F���V�����ׂ��ċ������͓����҂����m��Ȃ��B
�����ŁA�����E�C�����́u�R���v�́A���̎R�x�M����R�x�̎�u���{�T�v�Əd�ˍ��킹�āu�_�̎g���v�ƌh�i����܁j���čs�����B
�]���āA���̍���ɗ���Ă��閧���́u�k�C�E�k�l�M���̎g���v���T�M���ŁA�o�T���I�I�J�~����_�p�ƌ����P�ǂ݂̈Ӗ�����������B
�������C�����͍z����̍Ő�[�m������g����Ȋw�҂ł���A�@����ʂ��Đ��_���P�A����J�E���Z���[�������B
�����ɁA�ނ��C�����̐��̂����p���C�߂��u�e�̊����v�ŗL�鎖�́A�Öق̍��ӂ̏�ō݂����B
���̋�i���ʁ����j�̕��������_�M���ɒʂ��A�������i���炼��/�_�k�R�x�����j�E�הn�䍑�肵�āu�_�����E��a�������N�������v�Ƃ���������n�i������/�C�m����)�E��z���i���Ȃ��Ɂj�̍����ɂ��g���Ă���B
���������̒�����a�����̐_�X�ł���A�C�����͂��̎g���ł���B
�u�h���Ƌ���v�͐_�̌��_�ł��邩��A�T�M���������������_�������̈Ӗ����m�������B
�k�l�E�k�C���V�V�䒆��_�i���߂݂̂Ȃ��ʂ��̂��݁j���C�����A�z�C�����t�͐M�オ�u���_�̎g���v�ŁA�����͒�̖������u�H��@�ւ̊����v�ł���Ȃ�A����]�ˊ��̖��{�B�����u���{�̌��v�ƌĂ�鎖������Ȃ�ɗR��������B
�܂��A�����ɂ͌��͂̎��Ǝ����ێ��̓�ʐ������邩��d�����������A�u�����̌��v�ɂ́u���_�v�̈ؕ|���h�̈Ӗ�������A�܂���j��ǂ��m��Ȃ��ƌx�@�E���@�́i�Ԃׂj�̈Ӗ��Łu���v�ƌĂ�ł��܂��ԈႢ��Ƃ��B
������A���������ƌĂ��ɑ��������R���������L�͂ȋN�������݂���̂ŕ��L����B
�剻�̉��V�ȑO�i�Õ������j�ɁA�������{�E�g�p���鎖���u�Ɓv�Ƃ��A���̔\�͂������Ē��������Ɏd�����u���{���i���ʂ��Ђׁj�v�ƌ��������������B
�×�������q�����̎g�p�ړI�Ƃ��āA���{���i���ʂ��Ђׁj�͑��݂��Ă����̂ł���B
�u���{���I�v�ɂ��A�ܕS�O�\���N�i���Փ�N�j�ԑq(�݂₯)�̑�ʐݒu�������ē����������{���i���ʂ��Ђׁj�͍��X�ɐݒu���ꂽ�B
�ԑq(�݂₯)�Ƃ͌Õ�����ɐ݂���ꂽ�y�n��l���̎x�z���x�̈�ŁA��a���������ڎx�z�����y�n�̎����w���B
��y�́A�u�Ԃ͒��Ԃ������A�q�͒��ł�\���v�Ɖ��߂���B
�����ԑq�i�݂₯�j�́A�p�̑剤�i��������/�V�c���\�Z��j�ɋ��钆���W�����̍s���g�D���v�̈�Ƃ��āA�n������̊m���ȐŎ��m�ۂƊ������˂��o��@�ւł��邪�A����ɂ��Ă��p�̑剤�i��������/�V�c���\�Z��j�͂����ԑq�i�݂₯�j���x�̃A�C�f�A���ǂ��v���t�����̂��A����Ƃ��������炩���x���������̂��낤���H
���̌p�̑剤�i��������/�V�c���\�Z��j�̓�͌�قǂ�������i�c�����K�̉e�l�j�Ō�Љ��ς�ł���B
�u��a���������ڎx�z����v�ƌ������́A�����̏o�撓�ԋ@�ւł���B
�����ɓ��A�������������̓��A�n�́u�Ԑڎx�z�����̖����v�ƍl������B
��������u�~���P�v�Ƃ����n���Ɓu�C�k�J�C�v�Ƃ�����̒n���̋ߐڗ�̑�������A���{�����ԑq�i�݂₯�j�Ƃ̊ԂɂȂ�炩�̖��ڂȊW�������������z�肳��A���݂ł́A���{���i���ʂ��Ђׁj�͌���p���āu�ԑq(�݂₯)�̎�q�����Ă����v�ƌ��������L�͂ɂȂ��Ă���B
�ԑq(�݂₯)������i����j�̊ւ��͕s�������A����Ёi�_�Ёj���{�i�݂�j�ƌĂԎ��Ɗւ��͂���̂��낤���H
�Õ����̋L�q�ɂ́A���ՓV�c�̑O�ォ���ԑq�i�݂₯�j�̐ݒu�L��������������悤�ɂȂ�B
�ԑq(�݂₯)�̔��W�����{���i���ʂ��Ђׁj�̐ݒu���傫����^���Ă��������l������B
�Ȃ��A�ԑq�i�݂₯�j�̍L��W�J���A��́u���E�S�E�����̊�b�Ɛ����čs�����v�Ƃ̎w�E������B
���{���i���ʂ��Ђׁj�����������i�Ƃ��݂̂���j�ɁA�����{�A�i������̂��ʂ��Ђ̂ނ炶�j�A�C���{�A�i���܂��ʂ��Ђ̂ނ炶�j�A�ጢ�{�A�i�킩���ʂ��Ђ̂ނ炶�j�A���܌��{�A�i�����݂̂��ʂ��Ђ̂ނ炶�j�̎l�������݂��������`����Ă���B
���i�݂���j�ƌ������͍̂����͓y�n�̑������Ӗ����A�A�i�ނ炶�j�͘A���̎��\���B
�܂�A�L�͐����������o�g�̑�a�����̗L�͍\�������o�[�ŁA�剤�i�������݁E��j�ɑ������b���i���݂����j�Ɠ��l�ȈӖ��ƍl������B
�u�����{�I�v�ɋ���ƁA�����{���́A�����s�䓙�̍Ȃł���A���������q�i�����c�@�j�E�k���Z�̕�ł��鑡�]��ʌ����{�O����A���ϐe���i����������̂��A�����V�c�̑��q�j�̕�ł��鐳�O�ʌ����{�L�����Ȃǂ��y�o����A�V���V�c�`�ޗǎ��㒆���ɂ����ėL�͂Ȏ����ł����������m���Ă���B
�㐢�A�ԑq(�݂₯)�̎�q�Ɏn�܂������{���E���{���́A��Ɍ���������ƂƂ��ɁA�ԑq(�݂₯)�́u��q�v�ɂ��|���ė������|���������A�u�R�������Ƃ��Ă̐F�����߂čs�����v�Ǝv����B
���̎�������̂��A�L���ȑ剻�̉��V�̈������ƂȂ����h������ÎE�̃N�[�f�^�[�i�����̕��j�̎Q���҂Ƃ��āA�C���{�A�����C�⊋��t���{�i�ጢ�{�j�A�ԓc�̖��������鎖�ŗL��B
���̌R���������{�����c���̌����Ƃ͈قȂ���������A���n����i����j�̉B���g�D�u�A�z���v���g�D����A���̌�A�c���i��������j�M���i�c���̌����j�ł��������������Ɏ���đ����鎖�ɂȂ�B
������ɂ��Ă��A���{���i���ʂ��Ђׁj���A�z�t�́A�����ɂƂ��Ă��_�i��j�̎g���������ł���B
���_�́u�_���O��āv�����́u���v�ɂȂ��Ă��܂����̂́A���Ɏ����������A�u�h���Ƌ���v�̋C����������������ł���B
�����C�����t�̑g�D�A���͂�������ɂ͏o���Ȃ������ׂ��d�v�Ȗ����A�u�剤�i�������݁E�V�c�j�̖����v��ттĂ����B
�܂茢�_�ɂ��āA�{���ł͂��̐M�ɏd��ȈӖ��������Ă���̂����A���̘b�͓ǎ҂̓�����Ƃ��čŌ�̏́u�ېV�̑�ƁE�A�z���f�]���v�Ɏc���Ēu���B
����\�����錾�t�́A���㒆����i�k����E���ʌ�j�ň�ʓI�Ɏg����̂́u��i�R�E�j�v�ł���B
���{��ł͂��́u��i�R�E�j�v���u���E���ʁE�P���v�Ɣ���������ǂ肷�邪�A��Ƃ��Ďg���̂́u���v�̕��ŁA�Ⴂ������B
����ƁA���́u���v�ƌ��������̕��́A�������A�����ŏo���オ�����̂��H
���́A�u��i�R�E�j�v�Ɓu���v�A���������̕��������A�嗤���́u�鍑�̔e�ҁv�����㎞��Ŗ����I�o�����Ⴄ�ׂɁA���{�ƒ����ł͎���̗���̒��Ŏ�͂Ɏg�������������ꂽ�̂ł���B
�嗤�ł́A��Ƃ��āu������v���u�N�E�P���v�ŁA�u������v���u��i�R�E�j�v�炵���B
�������ɂ���C���̐��n�ɁA���_�_���E�O���_�Ђ�����B
�O���_�Ёi�݂݂˂���j�́A�_�Ж{���̕ʕ\�_�Ђł���A���Њi�͌��Ёi����������j�ł���A�����_�ЁA��o�R�_�Ђƕ��Ԓ����O�Ђ̈�ŁA��ʌ������s�O��ɂ���_�Ђł���B
�i�s�剤�i����������������/��\�j��V�c�j�̓������s�̍ۂɁA�V�c�͎Вn���͂ޔ���R�E���@�R�E�_��R�̎O�R���܂łāu�O���{�̎Ѝ����������v�Ɠ`����B
a href="http://jiyodan.exblog.jp/7957275/"target="_blank">�ɓ����ɗ��߂ɂȂ��������p�i����̂����ʁj�����̎O��R�ŏC�Ƃ����A�O�@��t�E��C���ω��������u�����ƎO���_�Љ��N�ɂ͓`������B
�������i�s�剤�i����������������/��\�j��V�c�j�́A������{�����i��܂Ƃ�����j�_�b�̕���ɓo�ꂷ��݂̂Ŏ��݂��^�⎋�����V�c�ł�����B
�J���Ă���̂͐����{�ɍł��L�����z���錢��̌��_�ł���B
���ꂪ�A����̓����{��������̈�Ƃ��Ĉׂ����A�z�C���̎R�x�M�̊����ŁA�����{�ȓ��ɍL�������B
�����������R�n�A���͍��O��R�n��сA�ɓ��������R��A�b�㍑�i�R���j��M�Z���i����j�̎R�x�n�тȂǂ̒n��́A�I�I�J�~�i�T�j�M�����_�M������ł���B
���̃I�I�J�~�i�T�j�M����_�M�͏C�����̎R�x�M�ł��邩��A�V�̌����V��i�Ăj�Ƃ��ւ�肪����B
�����ēV��i�Ăj�ƌ��_�͌Ăѕ����Ⴄ�����̓����u�C�k�v�ł���B
�V��i�Ăj�C���������c�F�i�T���^�q�R�j���V�F���i�A���m�E�Y���m�~�R�g�j������i�������j�̌Î��ɏK���u�l�g�䋟�`���v�X�Ɏd�|��������g�D�������B
�u���̂��Łv�ƌ����Ă͉������A�����P����R�E�����łȂ��u�C�k�v�Ɠǂ܂���������ɂ��čl���Ă݂��B
��a���̍��i��a�̍��j�͑����̓n���������e�n�͂Ő���A�`�̍��X���������Ă����O�g�����̓I�ȓ����K�v�Ƃ��Ă����̂����A�����̖����ꂵ�ĒP�ꖯ���ɗZ������ɂ�����i�������j�ɋ���l��I�����ƈӎv�a�ʂׂ̈Ɂu���ʌ�v���K�v�������B
���{��̃��[�c�ɂ��ẮA�A���^�C�N���� �A�����ꓯ�n�� �A���N�ꓯ�n���A�I�[�X�g���l�V�A�i�~�N���l�V�A�j��N�����i������N�����j �A�N���I�[���^�~������Ȃǂ��u����܂łɏ�����ꂽ��v�Ȑ��v�Ƃ���A�e�����咣����w�҂̊ԂŐF�X�Ƙ_�c�������A�ǂ�������͐����ł���A����ȕs�m���Ȃ��̂�P���ɂǂ�����ɌR�z���グ�悤�Ƃ���̂͊ԈႢ�ł���B
�܂��A������ꂽ��v�Ȑ����ɗႦ��ƌ����̏����Ȑ�B�i�x���j�ł���A����炪���{�ō������Ė{���i���{��̃��[�c�j�Ɛ��������̂ł���B
�܂�A�x�����������Ė{���Ɛ��������_�A�ꕶ������퐶���ֈڍs���錾��I�ߒ��ŋN���蓾�������A�܂��Ɂu���{��̃��[�c�v�ł͂Ȃ����낤���H
�����ŕ����͑嗤�������g�p���A��Z�n�ꕶ�l�i�ڈ�/���݂��j�̗ގ������ɑ嗤�����i������j��Ƃߍ��킹����A��Z�n�ꕶ�l�i�ڈ�/���݂��j�̌�Ӂi�����E��b�j�ő嗤�����i������j�̓ǂݔ����������鎖�ŁA���ǂP�ǂ݂́u��a���̍��v�Ǝ��̌��t�𐬗��������B
�܂�A�ٖ����E�����̑o�����ӎu��ʂ��Ղ��l�ɉ��ǂP�ǂ݂p���鎖�ŁA��ɓ��{��Ƃ��Đ�������u�|��@�\���������ꕶ�����Ƃɂ��đ��d�������錾�t�i��a���t�j�v��҂ݏo�����B
���̉��߂Ő�������ƁA�A�C�k�� �̌��́u�Z�^�iseta�j�v�ŁA������̌��i�P���j�E��i�N�D/�R�D�j�Ƃ��Ⴄ�u�C�k�v�Ɣ�������ꌹ������Ȃ��B
�ڈi���݂��j�̌��t�E�A�C�k��ŁA�u�A�C�k�iaynu�j�v�́u�l�ԁv�̈Ӗ��ł���B
�A�C�k�ꂪ���~�N���l�V�A�ꂩ��̂��̂Ƃ���ƁA�u�l�ԈȊO�̓����܂��͏��^�l�������A�����͂����ƍL�`�̓����v���w���������t�Ƃ��āu�A�C�k�iaynu/�l�ԁj�v�́u�A�v����������̂��A�C�k��́u�C�k�iynu�j�v�ł͂Ȃ��̂��낤���H
�悭���ׂ���ł͂Ȃ��̂ŁA�m�͂Ȃ��B
���{�ɉ����Ă͌��Ɋւ���M�ɐ[�����̂�����A���̎��́A�_�ЂɕK���u�����i���܂��ʁj�v���݂鎖�ł��A�T�_�ЁA���_�������݂��鎖�ł��A�ے肷�鎖�͏o���Ȃ��B
�_�Ђ̎Q���ɒ������鍝��(���܂���)�́A���̐_�Ђ́u��_�̌��_�v�ł���B
����(���܂���)�̋N���̓C���h�ƌ��������L�͂ŁA���X�͎��q�̌`�����Ă��������̓��{�l�͂����m��Ȃ������ׂɁu���Ɗ��Ⴂ�����v�Ƃ���Ă���B
�������Ȃ���A���{�̐M���l�@����ɁA���q�𗬗p���������m��Ȃ����A�u���i�T����_�j�̕������������v�ƌ����M��̈ӎu���������̂ł͂Ȃ����낤���H
�Ñ�̓��{�A�`�̍������Q����͂𒅂��A�u�吨�͂ɔ��W�����v�ƌ�����u��z���i���Ȃ��ɁE���������̕�̂ƍl������j�v�͊C�m�n���������n�ŁA���́u��z�i���ȁj�v�Ɠ��{�̌��_�M�ɊW������A�S���ɂ���_�Ђɍ����i���܂��ʁj�����鎖�̗��R������悤�ȋC������B
�����ŁA�e���O�i�V���E�Ă��j�̘b�����Ēu���B
�V���́A�V�̌��i��E�����j�̈Ӗ��ł���B
�����āA���̕`����Ă���ߑ��́A�V���A���炷�V��̕ʂ��킸�A�C���R���̈ߑ��p�ł���B
�����Ȃ�M���͒����ɋC���t���ł��낤���A����́A�C�������_����̂ł��鎖����Ă�����̂ł���A�������V���́A�u�l�g�䋟�`���v�ɂ����ދ���̏ے��ł��������B
���̕���ŒǁX�������čs�����A���{�̏��������́A�����Ƃ͕ʂɁu�����E�C���M���v�����̃��[�c�Ɛ����Ĉ�܂ꂽ���̂ł���B
�����E�C���M���͕ʖ��E���_�i�T����_�j�ŁA���̏ے����V�̌��i�V���j�������B
���_��T��ƁA�����ė�����̂�����B
�A�W�A�V�q���Ɏ���āA��i�N�H�E�E�R�E�E���j�͐_���g�킹�������̑��_�ł���B
�܂�A���{�ōL�܂������ɑ���M�A�u���_�i�T����_�j�M���v�́A�n�������k�l�����M����ʂ��āu�A�W�A�V�q���̐M���e�����Ă���v�ƍl������B
���Ȃ݂ɁA�V�q���̑������璆���k���A�����A�W�A�A�����[���b�p�Ɍׂ��鍑���A���Œz���グ�������S���̍c��`���M�X�E�n�[���i�e���W���j�́u�����̑����I�I�J�~�v�ƌĂ�ċ��ꐒ�߂�ꂽ�B
�`���M�X�E�n�[���i�e���W���j�̗F�l�ł���A�����S���R�̎l�叫�R�������W�F�����A�W�F�x�A�N�r���C�A�X�u�^�C�̎l�l�͑��h�ƈؕ|�̔O�����߂āu�l��i�X�D�B�N�H�E/�l�C�̌��j�v�ƌĂ�Ă���B
��a����́u�r�������������v�ɂ���ďo�����������p�i����̂����ʁj���C�����g�D�́A���̒�i�剤/�������݁j�̑s��Ȗ�����ттđ�a����x�z���̍��X�ɎU�����B
������ɂ��Ă��A���ꂩ���y���L�q���邱�́u���{�̗��j����E�c�����K�̉e�l�v�̒��ł́A�u���E��i�N�H�E�E�R�E�j�̐_�̑��݁v�͌������Ȃ��B
�сi�ɂ��j�ƌ��������́A�u�_�ɑ���������v�ƌ����Ӗ����݂�B
�����ďn��ɁA���сi�����ɂ��j�ƌ������t������B
�܂萶�сi�����ɂ��j�Ƃ́A�u�������܂܂́A�_�ɑ���������v�ƌ����Ӗ��ł���B
�����Ĉ���ł́A�n�����������Z�������ڈi���݂��j�𐧈����āA�����ׂ̈ɑs����V���~�Փ`�����ł����グ�āA�x�z�K���́u���_�i����j�v�Ɛ������B
���܂ł̓��{�j�́A�W�c�܂��͓���̌l�̗��v�ׂ̈ɐl�g���]���ɂ��鎖�ŁA�_�̎x�����肤�T�O�Ő������܂܂��сi�ɂ��j������A���̖������ŕ����̊����Ɖ��߂���Ă����B
���������_���n���s�����₻�̖���̌��͎ҁE����ł���A���сi�����ɂ��j�̈Ӗ��̓Z�N�V�����Ȃ��̂ɕς���ė���B
������u�l�g���](����)�v�܂��́u�l�g�䋟�i�ЂƂ݂������j�v�Ə̂��Đl�Ԃ�_�i����l�j�ւ̐���(�����ɂ�)�Ƃ���玮�������B
�Ñ�A��a���̋g���㗬�̎R�n�ɍ݂����ƌ��������Ƃ��̏Z�����A�����i�����^�����^����^Kunisu�̉��ω��j�ƌĂԁB
���̐l�X�������l�i�����тƁj�ƌĂсA�{���̐߉�(������)�ɎQ��A��(�ɂ�)�������A�J�𐁂��A����(�����Â�)��ł��ĕ����́i�ӂ�������/�n���`���́j��t�����B
�܂�̕����Ȃ��сi�ɂ��j�Ɨ玮�i�_���j�͒����̋{���M���Љ�ɔ��˂��āA�n���s�����₻�̖��Ⴊ����̎x�z�n��̐_�ЂɁA�u�_�y���v��u�l�g�䋟�i�ЂƂ݂������j�l���v�Ƃ��ē`�d���H���ꂽ�B
���̕����ǂ܂�Ă���M���́A�_���E�c���Ɏg���u���ߓ�̗R���v�������m���H
���ߓ�Ƃ́A�V�̊�˂ɉB�ꂽ�V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j���V�F���i���߂̂����߂݂̂��Ɓj�̃X�g���b�v�_���X�̓��킢�ɂ��Ċ�˂������J���A�O��`������������͗Y���i��͉��̑�/�������炨���݂̂��Ɓj����˂������J���ēV�Ƒ�_��A��o���A�V�Ƒ�_�̂܂��Ɂu���肭�ߓ���������炵���v�ƌ����_�b�����́u���ߓ�̏��߂��v�ƌ����Ă���B
���ߓ�́A�u�K�v�āi���肭�߁j��v�̗��������̂ƌ����A�v�āi���߁j�́u�o���v���Ӗ����Ă��鎖����A����Ɓu�K���o����v�ƌ������ɐ���B
�_���ȓ`���ɉ����āA�V�Ƒ�_���u���肭�ߓ���������炳���v�E�E�E���̈Ӗ�������̂͂������������낤���H
����ȉ��߂�����ΉR�Ōł߂��ǎ��h�́u�K�v�āi���肭�߁j������炵���̂͊�˂̓�����̕����v�Ɣ����͂��邾�낤���A���́u�V�̊�˓`���v��������Ɂu�ٖ������m������i�������j�V���̓^���`���v�ƍl����u�K�v�āi���肭�߁j��v�ɐ_�㐾��i�����������j�V���́u���A���ȈӖ������߂��Ă���v�Ƃ����߂ł���B
�܂�u�K�v�āi���肭�߁j��v�Ɋ|����ꂽ�V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j���A�{���V�j�i�X�T�m�I�j�̖��i�݂��Ɓj�ɋ�����Ĉٖ������m�̐���i�������j�V�����������A�u�ٖ����̘a�������������v�ƌ������X�����b�����m��Ȃ��̂ł���B
������ɂ��Ă��_��̓����͌��݂̂悤�ɐ���邷��ׂ����̂ł͖����A�����a���̐���i�������j�V����܍��L���̋F��̏ؖ��Ƃ��Ă̐����V���͐_���Ȃ��̂Ƃ��đ������Ă����̂ŁA�����猻�㕗�Ɏ�炸�_��̓����̐ς���Łu�K�v�āi���肭�߁j��v�̓`�����Î���H��ĎÂ�����ĖႢ�����B
�܂��A���オ�������Ă���̂��ߓ�Ƃ́u���A�i���߁j��v�A�܂��́u�W�i���߁j��v�Ƃ������A�ꖼ���u���ߏ���v�Ƃ������B
����͕W��i���߂Ȃ́j���Ӗ����錾�t�ŁA����Γ꒣��̌ꌹ�ł���A�c�ʍc���E���M�̎҂���ʂ�r�����Ēn����L���鎖���w���ĕW��i���߂Ȃ́j��n��v�ƌ�����ł���B
�܂肵�ߓ�́A�_���̏ꏊ�Ɖ��E�̋��������ׂɒ����Łu�����߂��v�̈Ӗ������B
����͐_�Ђɉ����āA���O�̋��E�܂��͏o���֎~�̂��邵�Ɉ����n����ŁA�_�O��_�����s���ꏊ�ɂ����Ƃ��͐���ȋ��ł��鎖�������A�ƒ�ŐV�N�Ɍˌ��ɂ���鎞�ɂ́A�Ђ��������炷�_��s��ȕ������ɓ���Ȃ��悤�ɂƂ̈Ӗ������߂��Ă���B
���̎��A��˂ɉB��U�����V�Ƒ�_���x���̂Ɏg��ꂽ�̂��A�O��̐_��̈�u���@�i���^�j�̋��v�ō݂����B
�X�g���b�v�_���X��x��ȂǁA�_�l�ɂ��Ă͂����Ԃ�l�ԏL����b�ł���B
���{�̗��j�̏����A�_�b����́u�����̔閧�v������i�������j�ɂ���B
��������i�������j�A�V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j�ƒ�N�ł���f���V�j���i�����̂��݂̂��Ɓj�̊ԂŎ����킳�ꂽ���ɂȂ��Ă���B
�{���A���e�ł���Z��̊Ԃł킴�킴����i�������j���s���K�p�ȂǂȂ��B
�����Ō�������i�������j�̊T�O�ł��邪�A�V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j���f���V�j���i�����̂��݂̂��Ɓj�́A��������i�������j�ɋ����āu���߂ČZ��ɐ������v�Ɖ��߂��ׂ��ł���B
�܂���{�����́A���{�ɗ������Ă����ٖ������m���A���n����Z���i�ꕶ�l�E�ڈΑ��j����������ō������A���Ƃ�������B
���̊�{�I�T�O������i�������j�ɏے������_�b�ɂȂ��Ă���B
���̏ꍇ������i�������j�̎����I�ȍ��ӂ̋V���͉��ł��낤���H
�ٖ������m���A�ȒP���L���ɐM���W���\�z���Ĉ�̉������i�͈�����Ȃ��B
����́A�����ɋ�����̓I�ɋ����������ɋ����ċ��ɂ̐M�������������A�蒅�����鎖�ł���B
���̌��ʂ͖��炩�ŁA����ɂ͍��������q�����a������B
���̊����A���͂�w�i�ɂ���������z�ꉻ�ł͂Ȃ��A�o���́u���ӂɋ���n��o���m�b�v���A����i�������j�������̂ł���B
���Â̐́A�l�Ԃ͏����ȌQ��P�ʂŐ������A�Q��Љ���\�������B
���̌Q��Љ�m���A���킸�ɋ�������ɂ͐����ɋ����̉������������ɗL���ł���A�����̓s�x�ɗ������s���ČQ��͑傫���Ȃ��đ������Ƃ��`�����ꂽ�B
���O�܂ő����Ă�������Ƌ}���Ɍ݂��̐M���W���\�z����Ƃ��Ă̕��@�́A�����ɋ�����̓I�ɋ����������������đ��ɖ����B
�܂�A�H���m�ۂׂ̈ɓ꒣�葈���ɂ��E�����������R�̎���ɁA���ɂ̈���ɑ�������̂��A����i�������j�̊T�O�ł��闐���Ƃ��̌�̌��ʂƂ��Ă̍����ɂ��Q��̈�̉��ł���B
���́u�Q�ꂻ�̂��̂��Ƒ��v�Ƃ���B��̎�i�Ƃ��Ă̒m�b�ɁA�٘_�͖����͂��ł���B
���݂̍��ƈӎ��A�����ӎ��A�܂��A���ӎ��E�����ӎ��̌��_�́A��������i�������j�̊T�O�ł���B
���̍ł����n�I�ȓ��̂̌����ƌ����V����ʂ��āA�ނ�͋��ʈӎ����������A���S�ƐM�����\�z���鎖�ŁA�Q�ꓯ�m���u���ԁv�ƔF�߂鎖���o����̂��B
�ܘ_�A���̎��ォ��l�ƎЉ�̂����ݍ����ɂ�銋���͂������B
�������Ȃ��炱��́A�l�ƎЉ�̑o�����������킹�Đ�����l�ނ̉i���̃e�[�}�ł���B
�����́u�Q��Љ�̕��a�I�����v�ƌ����Љ��D�悷������i�������j�̍s�ׂ́A����̌l�v�z����͗����o���Ȃ����ł��낤���A�B��L���ȕ��@�Ƃ��ď����ӎ��i�Љ�j��D�悵�Ĕ��������̂ł���B
���̐��_�I�Ȗ��c���A��Ɂu�l�����l�g�䋟�v�ƌ����c�Ȃ��������ӎ��i�Љ�j�̋]���I���_�ɂ܂ōs���߂��Ă��܂��A���ɓI�ɂ́u���U���_�v�ɂ܂ōs���Ă��܂����B
�����̊ԂɁA�j���̌������w���B��Ƃ��āu���Ղ������B�v�ƌ����p�@������B
�{���A�M�S�[�����̏����̊ԂŁA�_�̔�����������ꂸ�g���Ă������̌��t�̈Ӗ��́A���̂Ȃ̂��낤���H
�����q�����̍s�ׂ��A�u�ӂ�����Ȃ��́v�ł͂Ȃ��A�u�_���Ȃ����v�Ƒ������Ă�������ɑ��Ȃ�Ȃ��B
���X�u���ݏo���v�ƌ����s�ׂ͐_�̐�����ƂŁA������肤�s�ׂ��u���Ղ�i�����j�v�Ȃ̂ł���B
�C���t���ƁA�_�O�ŋ����錋���̌��_�������Ɋ_�Ԍ����B
�A�z�M�i�������f�j�́A�_��`���j�ɉ������V�F�i�A���m�E�Y���j�����c���Ð_�i�T���^�q�R�j�ٖ̈�������`�������̊�ɐ��������a�ƖL���̎��f�i�F��j����n�܂��āA�V��E�̍ō��_�E�V�V�䒆��_�i���߂݂̂Ȃ��ʂ��̂��݁j�̈ӌ��i���j�����Ɂu�����i����j�v�𐬂��n��̍ō��_�E�����i���Ƃ���ʂ��j�̐_��ꌾ��i�ЂƂ��Ƃʂ��j�̐_�́u��_���i�����j�v���K�����Ă���B
�������V���V�c(�Ă�ނĂ�̂��j�̂��ӎu�������p�i����̂����ʁj���J�������̉A�z�M�i������f�j�ɂ́A��ɏC�s����A�������O�@��t�E��C�����{�Ɏ����A�������������̉e����F�Z�����f���Ă����B
�����C�����́u�����E�R�x�M���v�̃��[�c�����A���ؒ鍑���o�R�������ƏK�����ē`������y���q�}�����R���́u�锇���̍��X�̃q���Y�[���N���v�ł��鎖�͊ԈႢ�Ȃ��B
���X�O�@��t�i�����ڂ�������/��C�j���������玝���A�����o�T������̐���ςɓ��ěƂ߂Đ^�������𗝉����悤�Ƃ��鏊�ɖ���������B
�O�@��t�i�����ڂ�������/��C�j���������玝���A�����o�T�ɂ́A�q���h�D�[���̌o�T�������܂܂�Ă���������A�^�����������܂ꂽ�B
�����炱���q�}�������Y�̍��������{�ɓ`���A�g��ɑ�\����R�x�M�ƍ��͓��{�ł���̂̂��̂Ɛ������B
�q���h�D�[���́A�V���@�_�̌�_�́E�����K�i�j���_�j���i�����j���M�ŁA�l�X�͐������Ă���V���@��������̓������猩�Ă���`�ɂȂ��Ă���B
���T�E�J�[�}�X�[�g���ݏo�������ɑ��Ă����炩�ȐM�̋��`���A�O�@��t�i�����ڂ�������/��C�j�̎�œ`������̂ł���B
���̐��ɑ��Ă����炩�ȐM�̋��`���A�A�z�C�����t�̎�ɂ���đS���Ɍ��`����_���ƏW�����Đl�g�䋟�̋V�����j���_���J��_�����o���B
�O�@��t�E��C�����{�Ɏ����A�����o�T�̒����C���h�E�q���h�D�[���̉e�������o�T�������܂܂�Ă��āA���{�̏��������̐����Ƀq���h�D�[���̖��������Ƃ������I�ȋ��`���������Ă��ē�����O�������̂ł���B
�k�l�E�k�C�M�́A�k�ɐ����V�̂̒��ŕs���̈ʒu�Ɍ����A���ʂ������u�݂�����ׁv�Ƃ��Đ��E���Ő_�i�����ꂽ�k�ɐ����܂�Ղ�ł���B
�Ñ�o�r���j�A�n���Ȃǐ��A�W�A�����n�т̗V�q�����̊ԂłɋN���������ʂ������_�u�k�l�E�k�C�i�k�ɐ��j�v�ւ̐M���A�C���h�ƒ������o�ĕ����Ƌ��ɉ䂪���ɓ`�������B
�u�݂�����ׁv�̖k�l�E�k�C�M���A�u�D�ꂽ�ڂ����v�̈Ӗ��̖����M�ƏK�����Ĉ�̐_�ɂȂ�A�ܕS�N�ォ��Z�S�N��ɂ����Ă̕������ȑO���n���l�Ɣ��ɓ��{�E��a���̍��ɓn�����A�i�������{�Ƃ��Ėk�C�����_�E�V�V�䒆��_�i���߂݂̂Ȃ��ʂ��̂��݁j����_�Ƃ��Ă���B
�����́u�D�ꂽ�ڂ����v�̈Ӗ����A�u���ʂ���v�ɒʂ��A�����p�i����̂�����/��Ώ��p�j�����������������̉A�z�g�D�̏C�����̍������ׂ��M�Ƃ��Ċ��p���ꂽ�B
���̖k�C�����M�́A�����̉A�z�g�D�𐬗������������p�i����̂����ʁj���N�������C�����Ɛ[���ւ���Ă���B
�A�z�C�����́A�剤�i�������݁j�̓������L�߂�ׂ݂̍閧���������ė̋��X�Ɋ����͈͂��L���čs���B
���̉A�z�C�����̑S���I�Ȋ����̍L����ƂƂ��ɁA���̂��S���ɐl�g�䋟�`���ƁA�u�k�l�E�����M�Վ��E�k�C�Ձv���L�����čs�����B
���������ɖk�C��Ղ��A�j�_�Ə��_�Ƃ̔N�Ɉ�x�̈����������������ďj���k�C�ՂƂ��ēs�̒���E���ԂŐ���ɗ��s����B
�M����O�ɍL�܂�ɂ́A�u���v�ɂ܂ō~�낵�Ă������łȂ��ƒ��X��������Ȃ��B
���̖����M�i�݂傤�����j�A����ł͐D�P�ƕF�����N�Ɉ�x�̈���������ށu���[�`���̍Ղ�v�Ƃ��Ė���Ȍ`�̏����s���Ƃ��Ďc���Ă��邱�̖k�C�ՁA�u�j�_�Ə��_�Ƃ̔N�Ɉ�x�̈����v�Ɉ��i���ȁj�ގ��������ɁA�_�ɂ��₩��_���Ƃ��Ă̗����Ղ������B
���͂��̕ӂ�́u���v�������M�����O�Ɏ����ꂽ�d�v�|�C���g�Ȃ̂����A�����M�ɂ͎��ɃG���`�b�N�ȓ��e�́u�Վ��E�k�C�Ձv�����݂����B
�܂�u�k�C�Ձv����ɑS���ɍL�����āA�����̊Ԃő��ɐ����̎����u���Ղ������v�ƌ����邭�炢�����Ƃ��Ă͈�ʓI�ȏK���ŁA���̌㖾���ېV���{�������܂�܂ŐM�s���Ƃ��đ������u�Èŗ����Ղ��v�̌��^����������ł���B
���{�ɉ����鏊���i������j�����Q���̍Ղ�s���̃��[�c�́A�k�l�����i�����j�M�������i���Ɓj�ł���A�A�z�C�������_�M���̉e�����Ă��邩����̖{���́u�����Ղ蕶���v�ł���B
�܂�A���O�i�{���͂����̐��~�̂͂��������m��Ȃ����H�j�q���i���j�������鎖���L����F��_���ł��邩�炾�B
�Ⴆ�A���s�E�F���́u�ÈōՂ��v�A���ł����ÈłŌ�`��S�����x�ł��邪�A�͈̂ÈłŁA����\�킸�j�������ʂ���ׂ̏ꂾ�����B
������������͉������������ł͂Ȃ��A���{�S���ŕ��ʂɑ��݂��鎖�������B
�����܂ōs���Ȃ��Ă��A�Ⴂ�j�����߂��荇�������Ȃ��`�����X���A�u�Ղ�v�̈łŗL�������͔ے�o���Ȃ��B
�Ղ莖�͓����̈Ӗ��ł�����A�u���Ղ�������v�͐����̉B��ł�����B
�Ղ��ʁi�}�c�����k�j�Ƃ́u����i���_/����_�j���Ղ����v�ƌ����Ӗ������A�܂�́u�����ɏ]��Ȃ��v�ƌ������ŁA���̕ӂ�̖��S�𗶁i��������j��ƁA����i���_/����_�j�̍Ղ�Ɏ��A�_�̑O�̈Èłŗ������s�Ȃ����ꎖ�Ԃ��A����Ӗ��u���̔��R�S���ׂ��鎖�v�ƌ����ǂݕ����f����̂ł���B
�������������K���������ېV�܂ő����A�ېV��̋}���ȕ����J���i���ĕ����̓����j�Ő��{���֗߂��o���ďI�����}���Ă���B
�������A�u�����킴�킴����ȉߋ��������Ԃ��Ȃ��Ă��E�E�E�v���{���ŁA���������ߋ��͑��������ɐ���A�₪�ď����čs�����̂ł���B
�S���Ⴄ����̉��l�ς�����o���A�u��c������Ȃӂ����炾�����Ƃ͎q���Ɍ����Ȃ��v�ƌ�����ł���B
�s���̈����ߋ��́u�����������v�ɂ���ׂɁA���ɓI�ȕ��@�Ƃ��āu�G��Ȃ��Œu���v�ƌ�����@������A�ϋɓI�ȕ��@�Ƃ��Ă͕������e�̍앶������l������B
�Ӑ}�������Ă��V���Ă�����A�₪�Ď��̗���Ɣ��Ɋ������������Ă��܂����̂ŁA���ӂ��ׂ��́A���Ƃ����݂������ł��A��Ɂu�L���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ɣ��f���ꂽ���̂́A�������B���i������j���A���͎҂⏊���i������j�펯�h�ƌ�����l�X�̏퓅��i�ł��鎖���Ȃ̂��B
���̕������ꊪ�ł��q�ׂ����A���_�I�ɉ������A�n�������Ɛ�Z�ꕶ�l�i�ڈΑ��j�����{�œ������A�x�z�K���̎����Ɣ�x�z�K���̓ꕶ�l�i�ڈΑ��j���\�����ꂽ�B
���̓����ߒ��̒��ŁA�n�������̐�i�����͓ꕶ�l�i�ڈΑ��j�̕������쒀���čs���̂����A���R�Ȃ��珉���̔�x�z�K���̓ꕶ�l�i�ڈΑ��j�ɂ͎����B�̏K�����������悤�Ƃ���푰�Ƃ��Ẵv���C�h������B
���ɕ��������܂��g�D���������R���x�X�N�����Ă���B
��i�������g���ė����n�������̕������@���ɗD��Ă��Ă��A�ꕶ�l�i�ڈΑ��j���ɂ��푰�Ƃ��Ẵv���C�h�������ďK������������ӎ������݂��邩��S�Ă��x�z�K���̎����Ɠ����K���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
��x�z�K���̓ꕶ�l�i�ڈΑ��j�̑����Ƃ��ċ������_�����ɒu�����Ɠ����������Љ����\������čs���B
�ܘ_�A�x�z���̎����̕��ł�������Ƃ��ĎR�[���܂ŐM����̂Ƃ����C�����t�i�R���j��h�����Ď����ւ̋����[�֊��������邪�A������א��ґ��ɂ��Č���Γꕶ�l�i�ڈΑ��j�o���̎푰�͔�D��I�ŏ]���Ȕ�x�z�K���ɂ���̂��]�܂����B
����ŏC�����t�i�R���j�́A������H�̎����Ƃ͂܂������ʂ̑P�Nj���E�������_��ޓ��Ɏ{�����B
�܂肱�̋������Љ�̃��[�c�́A���݂ł��L�菟���Ȉٖ���������Ԃɉ������Җ������A�Ǝ��̕����Љ���\�����ē����ɒ�R����\�}�ł���B
�����Ă���͓��N�ɗ]��i���ԁA������H�́u�����Љ�v�Ɣ�x�z�K���̓ꕶ�l�i�ڈΑ��j�́u�������Љ�v�ƌ����ٕ��������{�ŋ������čs�����ɂȂ�B
���Ⴂ���Ă͍��邪�A�����A���K���Ȃ����X�S�̂̌܃p�[�Z���g���łȂ��Ɛ��藧���Ȃ��B
�܂�x�z�K���̎����Ɣ�x�z�K���̍\���䗦�͌o�ϊw�I�Ɍ��܂��Ă��邩��A�͂��ȃE�G�B�g�����Ȃ��x�z�K���̎����̗��j�͕K���������{�����̗��j�Ƃ͌�����Ȃ��̂ł���B
�A�z�C�����A���O���@���I�Ƀ��[�h�������͊ԈႢ���Ȃ��B
�ܘ_�A�����̌����I�Ȍ��ۂƂ��ĕ��p���C�߂��u�e�̊����v�ł����C�����m���A���̋����������ׂɊ��҂��鑺�����������B
���R�̎��Ȃ���A��H�ɉ��������������o���Ă�����Ɉ������̂́A�����̊��o�ł͎��ɓ���O�������B
������ӂ�ƁA�������ɑ����Ɏ��t�����鋰�ꂪ���邩��A�����ɍŒ���̑I�������m�ۂ���ɂ́A������~�ޕ����Ȃ����u�������B
�����͂�����_�i�T�j�l����̎����A�u���Ղ�v�ƌĂ̂����m��Ȃ��B
����̓��{�ł́A�����ΐ����ɑ���}�X���f�B�A�̒��������b��ɐ��邪�A�ߋ��̗��j�ɍ݂��Ă͊������f�B�A�������ɗ��p���ꂽ���j�����݂���B
�����������j�̈�ԏ��߂ɓo�ꂷ��̂��A�V���E��a���쐳�����̌[�ւ�ړI�Ƃ����V�����Փ`�����ނƂ��镨��ō\�����ꂽ�u�_�y�i�_��/���݂���E������j���v�ł���B
����Ύ����Ɍv�Z���ꂽ�������f�B�A�Ƃ��āu�V�����Փ`���v�Ɏ��m�O�ꂳ���邱�̕���E�_�y�����A�S���ÁX�Y�X�Ɏw���E�z�������g�D���A�z�C�����C�����t�B�������B
������������ׂɁu�_�ƃR���^�N�g���鎖�v���A���n�M�ł���A�z���f�ŁA���ׂ̈ɂ͐l�X��[���ɓ�������Ă�����B
���̌`���Ƃ��Đ_�y���A�ޏ������`�������B
�u�_�y�l�i������тƁj�v�Ƃ́A�ޏ����̊y�퉉�t��S������l�B�ŁA�n���i�������j�Ƃ������B
�ܘ_�A�n���i�������j�͉����̐_�E������ɂ������Ă����̂ŁA����ΉA�z�C���N���X�̎҂̎d���ł���B
���̊y�퉉�t�ɏ���ĕ����̂��u����(��������)�v�ŁA�ޏ����S������B
�A�z�C���ɉ����āA�ޏ��_�y�̛ޏ��̐g�̂́A�{���u�ˁi���j�肵��v�ł���B
�ޏ��_�y�E�ޏ����́A�_�y�̌��`�Ƃ���������̂ŁA�{���u�_�}���̈ˁi���j�肵��v�Ƃ��Ă̛ޏ����A�_�|�����̏�ԂɂȂ�ׂɋ߂���̂ō݂����B
�_�����Ƃ́A�_���ł͜����Y��(�������ڂ���)�̐Ⓒ������ԂŁA���@�ł͒E���i��������j�ƌ�������Ō����G�N�X�^�V�[��ԁi�n�C��ԁj�̎��ł���B
����ɉ����Ă��l�X�ɗx��D���Ղ�D���������̂�������O�ŁA�f�B�X�R�_���X�ł��~�x��ł��閾�����x��x�[�^�E�G���h���t�B�����]���ɍ�p���Ĕ��S�n�ǂ��_���V���O�E�n�C�̋�����Ԃ������B
�����_�����̏�Ԃ��A�u�x�[�^�E�G���h���t�B���v�ƌĂ������z�����������傳�������ď��߂Ď��f�̈З͂����闝���������B
���̍ł�����̂��A�V��ˁi���܂̂���Ɓj�`���̗��_�y�̌��^�A�u�V�F�i���߂̂����߁j�̖�(�݂���)�̋������A���I��ȃX�g���b�v�_���X�v�A�ƌ����Ă���B
�܂�A��˓`���͌��n���f�̌`���P�i�Ƃ����イ�j�����n�삾�����B
�����̏���Ɋւ��Ă��{���̌��n�I�Ȃ��̂́A�_�ԁi���݂킴�j�A�܂�_�̜߈ˁi�Ђ傤���E���Ձj�����p���̂��̂ł��������瑊���Ɍ����������B
�������A�����̕����̌`���͉�y�̂悤�ɗD���ɂȂ��āA���̈Ӌ`���u�_�����Ԃ߁A�_�ӂ�a�߂�v�ƌ����l�ɕω����ė��Ă���B
��������ޏ����͏��ؐ�������A��A��A�����A��q�Ȃǂ̍̂蕨����ɁA�_�O�ŐÂ��ɕ������̂ł���B
�������A���n�I�Ȍ`���ł́A�ޏ����g�����X��ԂɂȂ�l�ȁu����������^�������̏���ɋ��߂�ꂽ�v�ƍl�����Ă���B
�܂�A�g�����X��Ԃ̃_���V���O�E�n�B�i�����i�[�Y�E�n�C�j�Ɋׂ�Ղ������o���鎖���v������Ă����B
���̍ő���̂��̂��A�ޏ����̉�����ɂ����������ɂ��������_�������̏�ԂƂȂ���f�ł���B
����Ȋw�ɉ����Ă����̃W�������͑��݂�F�߂Ă��āA�G�N�X�^�V�[��ԁi�n�C��ԁj�Ƃ͜����Y��(�������ڂ���)�̐Ⓒ������ԂŁA�@���I�V��Ȃǂł͒E���i��������j�Ƃ��������A���̏@���I�V��ɉ�����G�N�X�^�V�[��Ԃ̍ۂɑ̌������_��I�ȐS���ł́A�u�_�}�����͐_������v�ɑ������������u���z�E�\���A������ԂȂǂ̌��ۂ��v�Ƃ���Ă���B
���A�����i������j�ł͏��i�j���B/�j���C�j�Ɣ������鏗���i����ȁj�́A�A�C�k��ł́u�I�C�i�v�Ɣ������A�A�C�k��̃I�C�i�J���C�ioyna kamuy�j�́u�ޏp�̐_�v�Ɖ��߂���Y�o�����_�ł���B
���́u�ޏp�̐_�v�́A�A�C�k���b�N�� �iaynu rak kur�j�ŁA�l�ԁE�L���E�_ �i�܂蔼�_���l�j�ł��邩��A���n�_���ɉ�����ޏ��̌��^�����m��Ȃ��B
�y��Ɋւ��Ă͓J�A���ہA�Ղƌ����̂���Ȃ��̂ł��邪�A������{���̐_�y�Ƃ��Đ������ꂽ���̂̉e���ō݂��āA�{���́A�u�۔��q�i�ۏ��ł��炵�Ĕ��q�����j���x�̊ȒP�Ȃ��̂ł������v�ƍl������B
���q�Ƌ��ɉ̂���͕̂������̋{��̐_�y�ł͕��w�I�ʼn�ȁA���������Ƃ͂܂������W�̂Ȃ��l�Ȃ��̂��D�܂ꂽ���A���_�y�ł͒��ڐ_�X�̍~�Ղ��}����Ӗ����q�ׂ����̂������Ή̂���B
�܂肱���炪�A��̖����A�z�C�����^�����������䂾�����̂ł���B
��������́A�����A�z�t�������Ƃǂ��ւ��������A���̉e�����ǂ��ω����čs��������ǂ��Č������B
�����ŁA���͂Ŏ��グ���e���O�i�V���E�Ă��j�̘b���A�O�����ł��Ēu���B
�V��i�e���O�j�́A�V�̌��i��E�����j�̈Ӗ��ł���B
�v�������ׂė~�����B
���̕`����Ă����V���̈ߑ��́A�V��A���炷�V���̕ʂ��킸�A�������C���R���̈ߑ��p�ł���B
�����܂ł��������A����́A�C���ƌ��_������ł��鎖����Ă�����̂ŁA�������������C�������_���V���ł���B
�����ēV��́A�u�l�g�䋟�`���v�ɂ����ދ���̏ے��ł��������B
�ޗnj����������E���_�Ђɂ��V�����������̏�i�x�b�h�V�[���j��������u���Ղ�v�����邪�A����������ېV�̕����J���O�́A�u���{�S���œ����l�ȍ�����Ă����v�ƌ�����B
�܂�A���_�Ђ��V�����������̏�i�x�b�h�V�[���j�������闢�_�y���d�|�����̂́A�C���R���������đ��ɖ����̂ł���B
�A�z���̃X�[�p�[�X�^�[�א��i�������傤�j�́A�`���̐l���ŗL��B
���̓`���̑��݂��A�C���A�z�̖{���������Ă���B
��̑啨�C�����A�א��i�������傤�j��t���A�ޗǎ��㏉���Ɍ��ꂽ���ɂȂ��ċ���B
���ꂪ���R�M�̌��ɂȂ����̂����A�ǂ�����̐����C�����B�̑n��炵���B
�`���ɂ��ƁA�z�̑哿�i�����̂����ǂ��j�ƌ������א��i�������傤�j��t�͉z�O�̖����ÁA���݂̕���s�O���В��A�������y���̋߂��Ő��܂ꂽ�B
�\�l�ŐD�c���̉z�m�R�ŏC�s���A���S��N�i����N�j�����V�c������썑�Ƃ̖@�t�ɔC�����A���̌㎵�S�\���N�i�{�V���N�j�A�O�\�܍̎��A���������������̖������āA���ꍑ���R�ɓo�薭�����F�����������B
�������o�ė��鏈���C�����炵�����A���ꂪ���R�M���̎n�܂�ŁA�u�\��ʊω������R�̐_�l�ɂȂ�v�ƌ�������܂ŗ���ƁA���̍��A������������O�@��t�i��C�j�̎����A���������̌o�T�ɒ�������킹���l�Șb���B
�哿�i�����ǂ��j�����ʏ\��K�̍ō����ł���B
���̍ō��ʂ̎҂��A�u���݂��m�F�ł��Ȃ��v�Ƃ͂ǂ����������낤���H
�܂�A�u�z�̑哿�v�͑��݂��Ȃ������̂ł͂Ȃ��̂��B
�א��i�������傤�j�͗L���ȁu���i����j�̍s�ҁi���p�E�����ʁj�v�ɑ����A�R�ł̃X�[�p�[�}���̗l���C�����ŁA�C�s�̖T��S���Ɂu�א����J�����v�ƌ����_�Ђ⎛�́u��{�\�����ɂ��Ȃ�v�ƌ����A�X�����R�_���Ɩ��̕t�����_�Ђ͖k�C���A�{��A������̂����l�\�l����玵�S���z����B
�����̍��m�ɋ����ւ́A���O�̐M���W�߂�ׁA�u�A�z�C�������͂����v�ƍl������B
�������Ȃ���A�א��i�������傤�j�͓`����̐l�������ŁA�����ȕ����i���j�j�ɂ́A���݂��m�F����ɑ���鉽�̋L�ڂ������B
�C�s�����Ȃ���S���ɐ_�Ђ��J���́A�ʏ�Ȃ�u�݂蓾�Ȃ����v�ł���B
���̂Ȃ�㗝�̎ҁA�C���R���B�̎d���łȂ���A����ȂɍL��ɑ��ՂȂǎc���Ȃ��B
�א��i�������傤�j�͋��낵�����͂������l�X�Ȋ�ւ��N�����Ă���̂����A���̓��e���ƂĂ��l�ԋƂƂ͎v���Ȃ����̂ł���B
�����Ƃ��A�����Ő�[�̉Ȋw�m�����������҂��A���m�Ȗ��l�����������炢�A�u���삪�Ȃ��v�ƁA�o�߂��ڂŌ���ƁA����Ȃ�̊�ւ͂������̂��낤�B
�ʂ����Ă���قǂ̎��͎҂��A�����̉A�z���Ɋւ��������A���݂��������낤���H
�א��i�������傤�j�ɂ͌��݂ł��������A�_�b�I�`�����̗��������邪�A�C���R���B�́A�����M�̊��N��_�����u�q�[���[�n��̗����v�����������m��Ȃ��B
�悵�����炵���l���������Ƃ��Ă��A�}�����҂̗ނ͑����֒�����Č�̐��ɓ`���A���ꂪ�M�̑ΏۂɂȂ�̂��펯�I�ł���B
�]�ˎ����ɂ́A���N�߂����O�����|�̐����剤�̈Ӑ}���鎖���������݂����B
���ꂪ���悢��ߑ�ɋߕt���āA���钩���d�g�����ׂ����A�d��\�����������B
�C�����t�B���e�̒���@�ւ����������A���݂��B���v���ŗL�����̂ɂ͊ԈႢ�͖����B
���̉B�ꂽ�ړI�̈���A���Ɖ^�c�̍ő�e�[�}�u�剤�i�������݁E�V�c�j�̖����v�̐��i���������ɋC�t���ׂ��ł���B
�e�̍��Ƒg�D�u�A�z�t����R���H�}�v�ɖ�����ꂽ�������A���������̂����H
���ꂱ���A������n���������ׂ́u�����Č����I���P���Ȏ�@�v�������̂ł���B
�֓����T�_�����\�Ƃ���́A�����O��_�Ђ̂ЂƂu�O���_�Ёv�ł���B
�T�_���ɂ����ĘT���u�_�̎g���v�ł���ƌ����v�z�͂ǂ����痈�����A�ǂ��������E�C�����ɂ��̌����L��B
�����āA�C�����̍s�����u�l�g�䋟�`���v�̎���Ɏ������Ȃ��B
�剎�A��ցA�T�A�������̉��g���o�ꂵ�āA���l���ꂵ�߁A�M������ꂽ���l���u�l�g�䋟�v������A���ꂪ�u�l�g�䋟�`���v�ƂȂ��Č㐢�Ɏc�����B
���̍��͓̉����̑��̗d���E�������̗ނ́A��T�̏��A�R�x�M�������p�����C���s����A��̑m�����M�̕z���̎�i�Ƃ��ė��z�������̂ŁA����틳��I���b�Z�[�W�A�܂��͉����̖ړI�B���ׂ̈ɏo�����Ă���B
�l�g�䋟�Ɋւ��n�����b�̓��e�ɂ��ẮA�u�B�̖��b�A�䉾���v�ƕЕt���Ă��܂���ΊȒP�ł��邪�A����͉�y�ɂ͏o�������������B
���́A���b�ɉB���ꂽ�^���ɂ͏d��ȈӖ�������B
������`����������A���b�͑��݂���B
����̊��o�ōl���A�u�������ꂵ�Ă��邩��v�ƌ����āA����b�Ƃ͌���Ȃ��B
�_��I�Ȗ��b�ɂ́A���͓���Ȑ^�����B����Ă���B
�ܘ_�A�����������Ȃ��g���̒Ⴂ����̎ҁA���̂��͂����茾���Ȃ��ア����̎҂́A���b�ɉB���Č㐢�ɑ��������Ȃ��B
����������c�̐Ȃ��ӎv���A�ǂݎ���Ă��̂��A�㐢�ɐ�����u�l�̓��v�ł���B
�e�n�ɓ`���u�l�g�䋟�`���v�̑����ɂ́A���_���V��i�Ăj���u�P�����v�Ƃ��ēo�ꂷ��B
�V��i�Ăj���u�V�̌��̈Ӗ��v�ł��邩��A������V��i�Ăj�����_�ł���B
���_�͓��{�T�i��_�j���C�����t���d�ˍ��킹���R�x�M�ł��鏊����A�u�l�g�䋟�`���v���C�����y���C�����t�Ɛ[���ւ���Ă��鎖�͗e�Ղɑz���o����B
�����ċ��ʂ��鑽���́A����Ⴋ�������u�l�g�䋟�v�ł��肻����~�o����̂����_�i�C�����t�j�̖����ł���B
�������ӂ�������O��M�ɓ����̂́A���`�ɋ���[�֎�i�ł���B
�܂�A���́u�l�g�䋟�`���v���̂��̂��A�C�����ɖ��O�̐M���W�߂���ʂ������Ă����B
�B���̓`���A�P�Ɂu���킳�̗��z�v�ƌ�������ł͂Ȃ���̐���ттĂ������炱���A���O�Ɂu�����̋���v�Ƃ��ĐM����ꂽ�^���������B
���{���s������엢�E�Z�g�_�Ђ́A�l�g�䋟�i�ЂƂ݂������j�̍�@���_���Ɛ��������̂ŁA���g�̏�����_�ɋ����� �u��銯���Ղ�v�ł���B
����������ꂽ�䋟���̉�����Ǝ��l�̏��������ɐ_�O�ɐi�݁A�_�Ɍ�������B
���āA��w�̔��B���Ă��Ȃ�����A�����̊Ԃł͎���_�Ёi���K�j�Ɠ������炢�C�����t�i�R���j�̑��݂͏d�v�������B
�́A�a�������M�i�����j��ƍl�����A�M�[���f�p�ȏ����͋���Ă����B
�܂�A�R�[�����ɂ܂ő����^�ԏC���̎R���́A�����̗���b�゠�鋒�菊�������B
�����C�����̎R���B�́A�n�������l�X�ȍz����A���̖�w�m���A���_�P�A�ɗv����@���m������g���ď����̕������肢�A�_�̎g���Ƃ��ĐM�������������B
�����ł́A�����E�C�����́u�R���v���A�����R�x�M������R�x�̎�u���{�T�v�Əd�ˍ��킹�āu�_�̎g���v�ƌh���čs�����B
�]���āA���̍���ɗ���Ă��閧�����k�C�E�k�l�M���̎g�����T�M�ŁA�o�T���I�I�J�~����_�p�ƌ����P�ǂ݂̈Ӗ�����������B
�u�M������������v�ƌ������́A����Ԃ��u�M�����҂𑀂��v�ƌ������ł���B
�ߋ��A�A�z��������Ă܂ŏ@���Ɛ�p���u���Ƃ�������v�ƌ������j�́A���̖ړI�����邩�炱�����݂����B
�����Ĉ������A�e�n�̎R���Ɍ��p�����u�l�g�䋟�`���v�̎d�|���l�͂����C�����́u�R���v�ƍl������B
�\�o���i�ΐ쌧�j�����̎R����(��n��_��)�̉��_�ގ����l�g�䋟�`���ł́A�u���ク��v�ƌ����ł��C���R���i�C�����t�j��f�i�����锒���T�i���_�j���o�ꂷ��B
�̂��鑺�ł́A�������R���_���֔���������l���l�g�䋟�ɍ��o���̂����N�̉i�������K�킵�ł������B
����N���A��{�̔��H�̖�^�Ƃ̉����ɗ������B�u�������o���v�Ƃ̂������ł���B
���H�̖�������Ƃł́A�����̎R���_�Ђ֖��N����������l���l�g�䋟�ɍ��o�����˂A�u���ɍГ�~��|����v�ƌ����̂��B
�����l�g�䋟�A�e�q�̏�ɂ����Ă͔E�тȂ����A�����̎Љ�́u�����������i����������`�j�v�Ŗ��̒呀�����n��̈��S�����D�悳��A���ۂ���Α��������Őe�q���ɐ����Ă͍s���Ȃ��B
�i���������y�n�̏K���ł͂���A�������Ȃ��l�g�䋟�����A�ƂĂ����߂���Ȃ��B
���̉Ƃ̎�͒Q���߂����A�u���Ƃ����Ė��������鎖���o���Ȃ����̂��v�A�Ǝv�Ă̋���A������g�̊댯���A�茩���A�R���_�Ђ̎Гa�ɔE�ѓ����ėl�q��T���Č����B
����ƁA��������N�O�i�����݂E�[��j�̍��A�Гa�̉����牽��琺����������B
�u����͉�����H�v
���H�̖�������Ƃ̎�́A�C�t����Ȃ��l�ɋߕt���A���܂��B
����ƁA�l�g�䋟��v�����Ă���d���Ǝv�����҂��ق̈Â��Гa�ɐQ�]��ŁA�u�����Ղ�̓����߂Â������A�z�㍑�i�V�����j�̂��ク��́A�����V���\�o�̒n�ɐ���ł��鎖�͒m��܂��B�v�ƙꂢ�Ă���B
�u���߂��B�v�Ɩ��ɖ�𗧂Ă�ꂽ�Ƃ̎�͊�B�ǂ����d���́A�u���ク��v�Ƃ�炪�����炵���B
�ڂɓ���Ă��ɂ������قǂɉ�����A�艖�ɂ����Ĉ�Ăė����厖�Ȗ��ł���B
����������ׂȂ�A�ǂ�ȉ����ɂ��v�i�����j�肽���B
���H�̖���˂�ꂽ�Ƃ̎�́A��������������S�ŁA�l�g�䋟��v�����Ă���҂�����Ă���u���ク��v�Ƃ́A���҂Ȃ̂��A������������B
�d���Ǝv�����҂������u���ク��v�́A�ǂ����z�㍑�i�V�����j�ɋ���炵���B
���̕��́u���ク��v��m��R���Ȃ��������A�d���������Ȃ�Γe���p�A�u���ク��v�Ȃ�҂́u��������悤�v�ƁA�m����������v���ʼnz��֏o�������B
�u���ク��l�͉����ɂ����ł��ˁH�v
�z�㍑�i�V�����j�ɏo���������̕��́A�u���ク��v�̏��݂��q�i�����ˁj�����A�悤�₭������ł����B
����͑S�g�^���Ȗтŕ���ꂽ�u�T�v�ł��������A���̕��͕|�����Y��ĕK���ŋ����i�����B
�ߒQ�ɂ���Ȃ�������H�T���ɗ������e�́A�����v���S��͂��ク��ɂ��[���ɓ`������B
���̕��������b���A���������߂�̂ɑ��u���ク��v�͐[�����Ȃ����u�������ȑO�ɁA��������z��֎O�C�̉��_���n���ė��Đl�X�ɊQ��^�����̂ŁA���̂�����C�܂ř��E���Ă�����B�v�Ɩ��̕��ɍ������B
�u���ク��l�Ȃ炻�̉��_��ގ��o���邩�ˁH�v
�u�����A�Ō�̈�C�ɂ͓������Ă��܂������A�\�o�̒n�ɉB��Ă��낤�Ƃ͖��ɂ��m��Ȃ������B
����ł́A���ꂩ��s���đގ����Ă�낤�B�v�ƁA�u���ク��v�͉����Ă��ꂽ�B
���̕��́u���ク��v�̌��t�Ɉ��g�������A�ӂƋC���t���Ƃ������Ԃ������B
�u�L��������܂��B�����A��������l�g�䋟�ɍ��o�������������Ă��܂��B�v
�u����ł́A�\�o���i�ΐ쌧�j�����֒����ɏo�����悤���B�v�ƁA�u���ク��v�͖��̕��e�Ɂu�w���ɏ��v�ƌ������B
���̕��e���u���ク��v�̔w���ɏ��ƁA�u���ク��v�́u�t�����v�ƕ����オ��A�C�Ɍ������ƊC������낵���������Ă��n�߂��B
�u���ク��v�͖��̕��e���A�g�̏��̂悤���Ă��āA��������̗[���ɂ͎����֒������B
�u�킵���A���̐g����ɋ�����B�v
�Ղ�̓��A�u���ク��v�͖��̐g����ɓ��C�i����тj�ɐ��݁A��ɐ����Ă���_�O�ɋ�����ꂽ�B
���̖�́A�\���J�̖�ł��������A�d���Ƃ��ク��̑����́A�J���̉��܂ł��������悤�ɉ����������A�Гa���ӂ��Ă��܂����̌������ł������B
�����A���̐l�X�͘A�ꗧ���Ă��킲��Гa���ɍs���ƁA��ɐ��܂��Ĉ�C�̑剎���œ|��d���̐��̂�m�����B
�u����Ⴀ���܂����B�������͑剎����������B�v
�u���ク��l�̂������ŁA���N���l�g�䋟���Ƃ��B���肪����������B�v
���l�́u���ク��v�̉��_�ގ��Ɋ�B
�������A�u�T�v�́u���ク��v���܂��A�₽���[(�ނ���)�ƂȂ��ĉ�������Ă����B
���̐l�X�́A�u���ク��v����������A��������āA�l�g�䋟�̌`��i��������j�ɎO�C�̉��Ɉ��݁A�O��̎R�Ԃ��R���Ђɕ�[���鎖�ɂȂ����B
���́u���ク��v�̕���A���͓n��������������p���Ă���^���������B
�����̖��b�ɁA�u�J�N�G���v�ƌ����u�l���v�Ƃ��u�����v�Ə������̗d��������B
���ꂼ��u(�l����)�l�鉎�v�A�u���i����j���v�̈Ӗ����B
���͕Q�ɒʂ��A�v����ɏ����̎��ŁA��������Ɓu�����i����j�����̗d���v�ƌ��������ł���B
���̗d���A�����ł͎q�����c���ׂɐl�Ԃ̏��i����j���A�u�����̎q����s�܂���v�Ɠ`�����Ă���B
��A�̗쌢�`���ɓo�ꂷ��������A�l�g�䋟�ɖ���v�������������A�z������B
�k���O���̉z���i�x�R���j�A�\�o�i�ΐ쌧�j�A�z�O�E�ዷ���i���䌧�j�́A����@������ɂȂ�܂ł͑א��i�������傤�j�ɑ�\����锒�R�M�i�R�x�C�����j�̐��n�������B
�܂�A�l�g�䋟�`���̌��T�������ɂ���A������A�w���C���R�����A���炩�̖ړI�Łu���p�����v�Ƃ���̂������̖������߂��낤�B
����ɂ��Ă����̖��b�̃q�[���[�A���т̘T�E�E�u���ク��v�Ƃ͌��������߂���B
�C���i���グ��j�Ɓu���ク��v�ł͑��_������Ȃ������ł͂Ȃ����H
���̓`���A���ク��i�C���ҁj���ڈΖ铐�i�S�K�y�w偁j�̏ے��I�ȁA���̓��A���Ȍ����`���Ȃ̂����m��Ȃ��B
�u�����i���j���Ē݂邵�|���ɋ����E�E�E�j�O�A�V�����Ⴋ����𐬂��ĖL����F�肷�B�v
���̔��i���j�����u���ߓ��v�ł���Ȃ瑦�������́u�K�v�āi���肭�߁j��v�Ɋ|����ꂽ���ɐ���A�����ɂ��������f�̎��s���f����B
�������̐_��i����/���������j�ɉ����ẮA�������̂��̂��u�_�Ƃ̃R���^�N�g�i��M�j�v�ł���A�ޏ��A�����͂��̔N���������͂��̐_�Ƃ̃R���^�N�g�̔}�̂ł���B
�Ղ�ɋ����ẮA���̐_�Ƃ̃R���^�N�g�̔}�̂ł����ޏ��A�����͂��̔N���������̑O�ɁA�u�����v�悤�v�ƁA�_�Ƃ̃R���^�N�g�i��M�j�ׂ̈ɔ��i���j����ĐK�v�āi���肭�߁j��Œ݂邳�ꂽ�����ɁA�V�����Ⴋ���̒j�O�̍s�o����̂ł���B
�����_�y�i�������ق�����j�Ə����i������j�u���{�_�b�v�Ƃ̊W�ɂ��ẮA�N���٘_�͖������낤�B
�����A�����_�y����鎞�A�����Ēʂ�Ȃ�������́u�_�b�v������B
���ꂪ�����ɓ`���u�S���`���v�ł���B
�E���ւ̓���(�_���剤�̓����H)����A�������~�P�k�i�O�ѓ��얽�j�́A��ɐ_����N�i����ނ������݁E�_���剤�E����V�c�j�ƂȂ�J�����}�g�C�����q�R(�_�`�ɔg����Ö��E�_���{�֗]�F��)�̌Z�ŁA�����_�Ђ̍Ր_�ł���B
���̃~�P�k���A�u�A�����M�̗��v�ɋ����\�����B
�������A���R�̓��A�ɏZ��ł����u�r�Ԃ�_�v�S���i���͂��E�ڈΑ��H�j�͎R������A�������P�E�E�m���i�L�ڕP�B�c��x���_�̑����j�i����j���ăA�����M�̗��̓��A�ɉB�����B
���鎞�A�~�P�k�������������Ɛ�݂Ɋ��ƁA��ʂɔ����������f���Ęb���|�����B
�u�~�P�k�l�A�S���ɕ߂炦���Ă���E�m�����������������B�v
���ʂɉf���o���ꂽ�E�m���̎p�ɏ��������߂�ꂽ�~�P�k�́A���ɂ����s���J��Ԃ��S���i�ڈQ�����H�j�̓��������ӂ���B
�u�S�z�ɂ͋y�ʁB�����K�������o���B�v
�~�P�k�́A�l�\�l�l�̉Ɨ��𗦂����S�����U�߂��B
�S���͊e�n�����������A���R�ɖ߂낤�Ƃ������Ń~�P�k��ɒǂ��l�߂��A���i���j�ɑގ����ꂽ�B
�������A�����͗d���ł���B
�S���͉��x���h�����悤�Ƃ����ׁA�S�[�͎O�ɐ蕪�����ʁX�ɖ������ꂽ�B
�����S���`���A�P���ɕ����悭�݂菟���ȁu���Ƃ����v�����A����ɂ͉��Â̐�Z�����Ƒ嗤�n���������̍R�����`�ʂ���Ă��āA���̐�Z�����̖���B�����̒n���Ɠ��́u���鐩�𖼏��l�X�ł͂Ȃ����H�v�Ƃ������ċ���B
����k�ł́A�~�o���ꂽ�E�m���̓~�P�k�̍ȂƂȂ�A�u���l�̎q�����������v�ƌ����B
���̌㖖�Ⴊ�u��X���������߂��v�Ƃ���Ă���B
�����A�������炪���ŁA�����S���́u�M��v�ɂ���đ����̔�Q���o��l�ɐ������B
���ׁ̈A�u�S�����M��v��Â߂�ׂɁu���N�ԗ�Ղ��s���l�ɐ������v�ƌ�������ł���B
�����E���|���Ղ�́A�V��ꌎ���{�i����\�O���j�̂��̓��Ɏ���s�Ȃ�����n�F��Ղ�ł���B
����N�̖L�������Ď���s�Ȃ���N���̐_�����A�q���_���Ƌ��ʂ��Ă��Ă��s�v�c�ł͖����B
�u�����i���j���Ē݂邵�A�|���ɋ����E�E�E�v
�y�|�����z�́A�×���萫�����Ӗ����錾�t�ł���B
���̈ԗ�Ղ̕��K�ł́A�߂��ĉi�������g�̉������l�g�䋟�Ƃ��Ă����B
�����u�l�g�䋟�`���v�Ƃ��ē`���u�S���`���v�̐l�g�䋟�̗l���́A�����Ƃ���{�`�̈�ł��鉳���̔��݂�ӂ߂ł���B
�f�����̐l�g�䋟�i���я����j���A�_�Ђɐ݁i����j���Ă��镑��ɉg���o���A��Ŏ�������ɔ��i���j���Ă��̓���A������肳���Ĕ��i���j����������ɃK�b�`���i�i���ځj��B
������{������o���Ĕ��i���j���������̎��Ɍ��сA�i�i���ځj��Ȃ�����́i���炾�j�̓��[�̎��͂��{���s�Ɋ����či�i���ځj���Ĕ��i���j���A���r���J�����ē��点��B
�V�䂩�琂�ꉺ��������Ō���ɔ��i���j���������̘r�̌��іڂ����i��j�킦��B�l�g�䋟�i���я����j�ɏ㔼�g��O�ɓ|�����č������ɓ˂��o�����O���i�܂������j�݂̌`�ɂ����A���i�Ȃ킽���j�߂��r�����ɓ͂��l�ɔ��݂�ɒ݂�B
�u�����i���j���Ē݂邵�|���ɋ����E�E�E�j�O�A�V�����Ⴋ����𐬂��ĖL����F�肷�B�v
���ꂪ�i�����A�����̐l�g�䋟�̕��K�������B
�����A�퍑����ɂȂ��āA������閺��s���i�ӂт�j�Ɏv�������E�b��@�ہi�����������j�̖��ɂ��A�C�m�V�V���u�����̑�p�Ƃ���v�ƁA���f�l�������v�����悤�ɐ������B
�b��@�ہi�����������j�́A���h�����i�������ɂ݂̂�����j�E���h���̉Ɛb�œ������E�����Ɖ��̍��l�̎�E�����e�r���b�㎁�����ł���B
�ꑰ�̓�������b��s���S�i���R�����j�ɓ���ďZ��㍑�E�e�r���̎x�����b�㎁�ŁA��B�ɖ߂��ē��������ɓy�����A���h���d�b�ƂȂ����ꑰ�Ɠ`������B
���Ė��́A�����_�y�ɂ��A�z�t�̎��f�l�����F�Z���c���Ă���_�ł���B
���̓`�����̂ɍ����_�y�Ƃ̌��ѕt�����o�Ă����ł͂Ȃ����A�ԗ�Ձu���|�Ձi���������܂�j�v�͒��ڂɒl����̂��B
�����ɂ��C�����̎d���炵���`��������ł���B
�܂����́u�l�g�䋟�v�́A�_��̎��ォ��̓`���Ɋ�t���A�퍑����̍b��@�ہi�������j�̖��߂�����܂ŁA���g�̉����������鎖���������ċ����B
����ƁA���҂����S���`���𗘗p���āA�u�l�g�䋟�v�̃V�X�e�������グ�A���Ȃ��Ƃ����S�N�Ԃ́A���ꂪ�p�����Ă������ɂȂ�B
�u���̓`���̒��Ŏn�܂����v�Ƃ�����S���̈ԗ�Ղ������ɓ`����Ă��āA�����_�ЂŎ���s����u���|�Ձi���������܂�j�v������ł���B
���|�i���������j�́u�|���v�̈Ӗ��́A�l�˂��i�l������ɒ݂邳��ĂԂ牺��������Ԃ��l�g�䋟�j�ł���B
��ւƂ��āu�l�g�䋟�v�̉����̑���ɁA�Гa�ɒ����Ō��킦�Ē݂艺���邩��ŁA�P���ɍl����ΈȑO�́u�l�g�䋟�̖������킦�Ē݂邵�Ă����v�ƍl�����A�A�z���f�I�ȓ�����������̂ł���B
�����ňꌾ�A���Ɋւ��i�F�C�̂���j���j���͂������Ɠr�[�ɁA�����������ɒ���Ƃ��펯��U�肩�����Č��ߕt���A�������悤�ȉR���ł����グ�鐨�͂�����B
�S���`���ƁA�b��@�ہi�����������j�����ށu���|���Ղ�i�[�����т̍Ղ�j�v�ɂ��Ă��A�u�b��@�ۂ̐l�����̂����b�v�Ǝj�����Y�펖�ɔP���Ȃ��Ď咣����B
���������̐l�g�䋟�́A�y���̂̐_��������̃~�P�k�i�O�ѓ��얽�j�̓`���u�S���`���v����n�܂邻�̒n�̐l�g�䋟�V���Ƃ��Čp������A�퍑����̍b��@�ہi�����������j�ɓ����Ă���B
������s������u�l�g�䋟�V���͖��������v�ƌ���̋K�͏펯��U�肩�����Ĕj�]������������������A�p�������C���������ߕt���̘_�|���咣����B
����������S���`���ƍb��@�ہi�����������j�`���̑O�i�E�S���`�����̂ĂĒu���āA��������u�[�����т̍Ղ�i�����|���Ղ�j�v���@�ہi�������j�̐l�����̂���n���b�Ƃ͖����Ȃ������ł���B
���ɁA�����n���ɓ`��錢�_�̓`���i�쌢�̓`���j���グ��B
�Ӑ}���ĉB����Ă��邪�A���p����Ĉ₳��Ă��閯�b�`���̗ނɂ́A��̐��ɓ`���������낵���^�����B����Ă��鎖�������B
�����l�g�䋟�`���ɋ����������́A���̂������̗L�͎҂̖�������ŁA�܂����̏����ɗ�O�͖����B
�q���b�g����ƁA����͐_�̎g���u���_�v����V��������������ׂ̋V���Ȃ̂����m��Ȃ��B
���̐́A�ԉ��V�c�i���\�ܑ�E����V�c�̑O�̒�j�̎����̘b�ł���B
�M�Z��P�x�̂ӂ��Ƃɂ�����P���ŁA��������Ƃ��Ȃ�����ė�����C�́u�����R���v���ܕC�̎q�����Y�B
���̘a�����A���ߐ[���l���ŁA�����R���̐e�q�̕�炵�Ԃ��������Ă����̂����A�₪�Ďq���B���ꌢ�Ƌ�ʏo���Ȃ����Ɉ�������A��e�Ǝl�C�̎q���͎R�֍��R�ƋA���čs�����B
�������ǂ��������Ȃ̂��A�ܕC�̒��ł��ЂƂ��킽���܂��������������q����������C�������Ɏc���Ă����B
�u���₨��A���̎q�i���j�����u���čs���ꂽ�̂��H�v
�����Ɛe�q�ɖڂ������Ă����a���́A�����s�v�c�Ɏv�������̂́A���̈�C�����Ɏc�������������������ňꏏ�ɕ�炷���ɂ���B
���P���̘a���́A���̎q�i���j���u���������Y�i�������Y�j�v�Ɩ��Â��Ď����݈�Ă��B
����A���B�n���i���]���E�É����j�̌����h�ӂ�ɁA���l�ɖ����l�g�䋟��v�����A����ɏ]��Ȃ���ߗׂ̓c�����r�炵�āA����������炷���낵���_�������B
�H�Ղ�̍��ɐ���ƁA���N�̗l�Ɂu���̋��鑺�̉Ɓv�̌ˌ��ɁA���H�̖�𗧂Ă�̂ł���B
���̔��H�̖�̘b���A���ނƎv������̂����\�L�͈͂ɓ`������Ă��鏊����A�b�̏o�錳�͍L�͈͂Ȋ����������g�D�̑��݂��M�킹��B
�Y������Ƃ�����A����͂�͂�A�z�����C���g�D�́u��p�ړI�v�Ƃ����l���l���Ȃ��B
��𗧂Ă�ꂽ�Ƃ͖������̈��_�ɍ����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�n��̈��S���l�����D�悳��铖���́u���������̎Љ��i����������`�j�v�ł́A�e�͋��������ł��l�g�䋟���������Ȃ���ΐ���Ȃ��B
���l�B�́A�u�w�ɕ��͑ウ���ʁv�Ǝd���Ȃ����̈��_�̗v���ɏ]���Ă͂������A��͂薺���тɍ����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����Ƃ̎҂̔߂��݂͌����l�������قǂ������B
���̗d���𑊑ł��œ|�����̂��u���������Y�i�������Y�j�v�ƌ������i�_�j�������B
���܂��܉��]���E�����h��ʂ肩���������̏C�s�m�����̐l�g�䋟�ɓ���A�悸�͂��̗d���̐��̂��m���߂�ׂ������\���̍Ղ�̖�ɔq�a�̉��ɔE�э��݁A�u�M�Z�̎������Y�ɒm�点��ȁB�v�ƌ����d���̋��т����ɂ���B
�d�����u�M�Z�̎������Y�Ȃ�҂�����Ă���v�Ǝv�������̏C�s�m�́A���̐l�g�䋟�ƌ�������Ȋ��킵�ɋꂵ��ł��錩�t�̐l�X���~���ׁA�����A�������Y��{�����ɏo��B
���̑m�͐M�Z������{�������A�Q�����鑺�Őԕ䑺�i������s�j�́u���P���ɂ��錢���������Y���v�ƌ����b�����ɂ����m�́A�������B�����̋����i���Ď������Y�����ׂ��A�ӂ������Č��P����K�˂��B
���P����K�˂Č���Ƌ����ɗ��h�Ȍ��������B
���P���́u���������Y�i�������Y�j�v�͐������A�₪�Ă����܂����쌢�ɐ������Ă����̂��B
�u�Ȃ�قǁA���̗쌢�Ȃ�d���������̂����Ȃ�����v�ƁA���̏C�s�m�͊m�M�����B
���P����K�˂����̏C�s�m�́A���P���̘a���ɉ���Č��t�Ō����������^�������A�������Y�̎�����肵���B
�����m�������P���̘a���́A�ϖ��ׂ̈Ȃ�Ǝ������Y�̉��B���t�s�����������ꂽ�B
���̏C�s�m���u���������Y�i�������Y�j�v���ĉ��B���t�ɖ߂�ƁA�܂肵�������h�͂��̔N�̔����\���̍Ղ���}���Ă����B
�Ղ�̓����̖�A�l�g�䋟��H�炨���Ƃ���d���Ɏ������Y�͖ґR�Ɖ����ɏP�����������B
���̗d���Ǝ������Y�Ƃ̐킢�͐��܂����A���ѐ����u�����܂Ō��t�̒��ɂ܂ŋ����킽�����v�ƌ����B
�����A�����ɂ͑傫�ȔN�V�����࿁i�q�q�E���ȁj�̉����������܂݂�ɂȂ��ĉ�������Ă����B
�����͂��Ɏ������Y�ɂ��ގ����ꂽ���A�������Y���[����A�����̍��̎R�_�Ђ̏��Łu���₦���v�ƌ����B
����炱�̘b���A�u�\�o�̂��ク��`���v�Ɨǂ������������邪�A������M�B�͌ˉB���C�����i�ˉB���E�p�Ƃ��Ă��j�̖{���ŁA�����i������j�R���M�i���_�M�j�̐��n�������B
���������Y�A�����͑����Y�ƌĂ��쌢�̓`���͈ȏ�̗l�Ȃ��̂����A�M�Z���i���쌧�ɓߒn���j���牓�]���i�É������B�n���j�ɂ����ėގ����������̓`�����c����Ă���A���̈��͑��̗ޘb�Ɣ����ɈقȂ��Ă���B
�܂��܂�����A��_���T�����_�M���́A�u�A�z�C���̊�{���v�Ɖ�y�͍l���Ă���B
�܂�œ���̑g�D���A�Ⴄ�y�n�œ����p�^�[�����g�p�����悤�Ɏ��Ă��āA�����ɁA�A�z�C���̉e�������B�ꂵ�Ă���̂��B
���m�R���R���w���琼�ֈ�L�����[�g���]��s�������ɁA�������̑�ΐ_�Ђ�����B
���̐_�Ђɂ��A�l�g�䋟�̓`�����c���Ă���B
����͂���܂��u�������v�ƌĂ��쌢�̘b�ŁA�\�o���i�ΐ쌧�j�����̗쌢�`���u���ク��v�≓�]���i�É����j�����h�̗쌢�`���u���������Y�i�������Y�j�v�Ɨǂ�������������B
���������`���̓p�^�[�������Ă��鎖����A���̕ӂ�̌o�܁i�������j���C���R���̉e���`�����̂��B
�́A����N�ɁA�k�ߋE(�O�g�E�O��E�A�n)�n���̈��鑺�Ő_�B���������N�������B
���q�̒��Ɍܐl�A���l�Ǝ��X�ɍs���s���҂��o�Ă��đ������o�ő{���Ă��A�s���s���҂̏����͔���Ȃ��B
�����̒͂߂Ȃ��_�B���ł��邩��A�u����͐_�̂��{��̉Ёi�킴�킢�j�ł���v�Ƃ̌��_�ɂȂ�A�_�̓{���Â߂�ׂɎ��q�̘A�������k�����l�g�䋟�������鎖�Ɍ��߁A�����������čՂ�̖�ɋ����鎖�ɂ����B
���̑��ł́A���N�Ղ�̖�ɐl�g�䋟��������_���͑����Ă����B
���̎�茈�߂ł��邩��ۂƂ͌������A���l�͗�N���������l�g�䋟�������Ă����B
�����A����N�̂����������ŋ]���҂ɓ��������Ƃł͑�ϔ߂��݁A���Ƃ����̍Г��悤�Ƃ�����S�ɐ_�ɂ�����A�O�����̋F���������B
�����܂ň�Ăė��āA�Q�i�悤��j���Ԃ�����̔N�����}��������̈��������ł���B
���́A�e�ł������ꍛ�ꂷ��قǗ킵������Ă��āA�ƂĂ��l�g�䋟�Ȃǂɂ͏o���镨�ł͂Ȃ��B
�ꐶ�����g���ʂ������Ǝv�����炢�U�X�ɋ��������A�ܘ_���ւ̎v���͒f����Ȃ��B
����Ƃ��̋F���̖���̖������Ɉ�l�̓��q������A�u���q�̔ߒQ���ɔE�т��́A�쌱�������ē���ɋ����悤�B�v�ƁA�_�̐������̑��l�ɓ`�����B
���q�̘b�ɋ���ƁA�]�B����S�ɂ���]�B���ꖾ�_�͈���f�����J�邪�A���̋{�����͐l�g�䋟�̉Ёi�킴�킢�j���݂����B
���������ꖾ�_�{�̉Ёi�킴�킢�j�́u�������ƌ���������������ގ����A���̖�ꂽ�B�v�ƌ����A�u�������̌�������S�ɂ���B��ė��āA��Ղ̎����̌�����ɓ���Ă����B�_�͕s�v�c�ȗ͂����̌��ɗ^����ł��낤�B�v�Ɠ`�����B
����������l�́u����ő��̉Ёi�킴�킢�j�͖�������B�v�Ƒ傢�Ɋ�сA�_�̂������̒ʂ�]�B����S���猢�i�������j����ė����B
�肽�����������ʂ�ɔ��ɔ[�߂Ă��ߏ����_�O�ɋ����A���l���̉A�ɉB�꓁���\���đ҂��Ă����B
�锼�ɂȂ��āA�V�n��h�邪���剹�ƂƂ��ɋ��낵������������Ĕq�a�ɖ��オ��A�������̔��Ɏ��������₢�Ȃ⒆�ɋ��������������������o���Ȃ�������Ɋ��ݕt���A�Ƃ��ɉ������ɗ����čs�����B
��ɂȂ艺�ɂȂ�A�������ƌ����������������������l���A�u����͑�ρv�Ɖ����̌����f���A�������ɓ����ĉ����ɐ���������Č���������ގ����鎖���o���A�ȗ��l�g�䋟�̐_���͎��~�߂ɐ������B
���̉����́A�u�O��̑�K�������v�ƌ����A�O�g�E�O��E�A�n�n���́A���X�u�����K�`���v�̑����n���ł͂���B
���̌�A�������͑�ɑ��Ŏ����A���������̎�����u�������Ɖ��߂���ꂽ�v�ƌ����B
������A�O�g���E�R�̒r�K�_��(�������肶��)�̓`����������B
���ꂪ�A������`���̒��g��ǂ��l����ƁA�S�Ăɋ��ʂ���u�܂�ł����܂�Ƀp�^�[�������ꂽ���v�̂悤�ɁA�����̓`���͗ǂ����Ă���B
�́A��R�̈��闢�ɔN�V�������e�Ɣ����������Z��ł����B
���̑��ł́A�H�Ղ�ɂ́A���N�\�܍ɂȂ�O�̏������l�g�䋟(�ЂƂ݂�����)�ɏo��������Ȃ�Ȃ������B
���̂��������ɂ�����������������āA���̗��e�͂��������߂��݁A������Ď��_(��������)�l�E�r�K�_��(�������肶��)�ɂ��肢�ɍs�����B
���͕s�K��Q(�Ȃ�)���A����̋C�������v���ēr���ɂ���A�[���_�ɋF���������B
������A�r�K�_��(�������肶��)�ł́A�_��(����ʂ�)�������ʋC�����ŏH�Ղ�ɔ����A����(��������)��|�����߂Ă����B
�u���N���l�g�䋟�ɖ���������v�Ǝv���ƁA�Ղ�Ƃ͌����ɂ܂����b�ŁA�_��̐S�͕����Ȃ������B
���傤�ǂ����ցA�s���痈���Ⴂ���m���Q�q�ɗ���������B
���͂��̕��m�A���̎��_�̂������ŁA�����́u���̖̉��ɏZ�ށv�ƌ������ƁA��������ׂ́u����T�����v�̓r���������B
���m�́A�u�r�K�_�Ђ̐_�l�ɂ��A�������̑�����Ă݂悤�v�Ǝv���āA��S�ɐ_�l�ɂ��F��������B
���̂����Ⴂ���m�́A���ăE�g�E�g�Ɩ��������B
���̒��ł��l�g�䋟�ɑ����č��̖�����A�_�̐������������̂��B
�����i��߂��j�̒��ŋ����Ⴂ���m�ɁA�_�̐��͑�����B
�u�אS(���Ⴕ��)���P(�͂�)���A�l�g�䋟�̖��ƕv�w�ɂȂ�A�_�̌b�݂�`����B�q�m(������)�������E�҂ɕ�(�ق�����)��U���^����B�v
���̐��ƂƂ��ɕ����̖̏�ɍ~��ė����B
�n�b�Ƃ��ĎႢ���m���ڊo�߂�ƁA���Ɩ��̔������̖̉��ɂ͌����ɕ��݂����B
�u�ڂ̑O�Ɍ�_���i�j������v�ƌ������́A���̖����_�̂�����ɈႢ�Ȃ��B�s���痈���Ⴂ���m�́A���̖����u�T���Ă����킪�łł���v�Ɗm�M�����B
�_�������ɍ����邩��ɂ́A�ŒT���̗��̖ړI�n�͂��̒r�K�_��(�������肶��)�������̂ł���B
�m�M���������Ⴂ���m�́A�u���ꂱ���_�̌b�݁B�v�ƌ����Ă��̕�������(������)�����B
�Ⴂ���m�́A�łƂȂ閺�����������ւ̐l�g�䋟������ׂɐ_�ɓ����ꂽ�̂ł���B
���Ղ̓����ɂȂ��āA�Ⴂ���m�͖ڂ����炵�A�ӂ���x�����Ă����B
�l�g�䋟�̍Վ����ς�Ŗ����[���A���l���A������ɐ���s�v�c�ɂ������U���U���Ɠ��h���A����Ȃ��^���ÂȖ�ɐ����Ă��܂����B
�钆�ɂȂ��ĉJ���~��o�������A�ڂ��M���M�������A�����~�点�Ȃ��炱����ɋ߂Â��ė���ٗl�Ȃ��̂��������B
���m�́A�u�r�K�喾�_(�������肾���݂傤����)�v�ƐS�ɔO���Č����đ҂��Ă����B
�J������Ɍ������Ȃ������̎��A�����������}�ɕ��m�ɏP�����������B���m�����鎖�ɋC�t���Ă����̂��B
��шႢ�A�����������ĕ��m���a(��)��t����ƁA���ɕŁA�u�Y���v�Ǝ育����������A�����������u�M���[�B�v�Ɣߖ��������B
�d���͏����A������Ċ�ɓo���ē����Ƃ����̂ŁA�������낵�A�u�G�B�B�v�ƌ����h���т��ƁA���������͂̂������Ė\��A�₪�đ�l�����Ȃ����B
�Ⴂ���m�́A���̉���������Q���ގ������B���̏u�ԁA��͋}�ɖ��邭�Ȃ��āA�����ɏ\���[�g���]��̑��(��������)������ł����B
���m�́A�V�v�w�̈�l���ƌ������A���ɏZ�݂��āA�u�q�����h���A�������������ɉh�����v�Ɠ`�����Ă���B
�u��c�̑�֑ގ� �v�Ɠ`������A�O�g���E�R�̓`���ł���B
�����́u�l�g�䋟�i�ЂƂ݂������j�v�ƌ�������ł͂܂������ʗp���Ȃ��l�����̋������Љ�ɉ����鎩�ȋ]���̝|�i������/���[���j�̌��_�́A���ɉ��p�͈͂̍L���l�މi���̃e�[�}�ƌ����ׂ��I�����̖��ŁA���l�̃W�����}�ƌ������_�ɂ��̉�������߂鎖���o����B
�����Ă����̗d�����l�g�䋟�b�A�����̎���͉ڈi���݂��j�Q�����̔ƍs�����m��Ȃ����A��̎d�����C���R���̎��쎩���̉\���������B
�܂��A���_�͒���_�ł���A�_���͎����̎x�z�҂���������A�l�g�䋟��v�������d���́A���͐_�����̂��̂������̂����m��Ȃ��B
���Ԃ̓`���ɂ́A�u�V�����G�i���炷�j�V���v�ƌ������d���������A�R���̑�����g�ɓZ�i�܂Ɓj���ċ��鏊����A�����ʖ��O�ɋ�����镨���C���R���ɂ��������������ŗL��B
���ʁA�悭�l���Č���Ƃ����l�g�䋟�b�A���l�Ɂu�]�����Ă����a���ێ����傤�v�ƌ������������̈ӎ����Ȃ��ƁA�������Ȃ��b�ł�����B
�����C���R�������l���x���A�f�p�ȑ������u�l�g�䋟�v�ɂ������̂��A���̖ړI�͒N�ł��v��������ł��낤�B
���̖ړI���u�����̎��f���ׂ��ׁv�Ȃ̂��A�l�I�ȗ~�]������ׂȂ̂��́A���ɂȂ��Ă͕s���ł���B
�������A��������������A�u�C�����t�̍��Ɣ閧�@���v�ƌ�������Ȑ������ɂ���B
����ׂ̈̕z���ƁA�K�i�ʂ��j�Q�����ގ��A�z���T���A�e�풳���ȂǁA���̎���͈͕͂��L���B
���̒��̈�ɁA��������ȖړI���L�����̂ł͂Ȃ��̂��낤���H
�l�ԁi�ЂƁj�������j�i����������/�]���ʁj�ɉe������āA������ȑ���Ɂu����̊�]���ׂ��Ă����v�ƌ������҂���i�����j�����ŁA�u�S�̈���悤�v�Ƃ���S���������Ă���B
���ꂪ�S���w�I�ɂ́u�p�Y�Җ]�_�v��������A�M��́u�J���X�}�i���l/���c�j�̑��݁v�������肷��B
�M�E��p�E�\���̖{���́A����̎������݂���̂̐l�Ԃ����u�����j�i����������/�]���ʁj�v�ɉe�����ꂽ���̈ˑ��ǂł���B
���̈ˑ��ǂ̉�������ɍ݂�̂��A�u�W���s�^�[�E�R���v���b�N�X�i��x�z�̊�]�j�v�ł���B
���̐M�E��p�E�\���ɑ���ˑ��ǂ́A�����ɂ܂�Ȃ����ɁA�����œw�͂��鎖����������ʓI�ɍK�������Ŕ����}�����\�������B
���̈ˑ����鑊��̈�l���V���[�}���i�a����/�ޏ��j�ŁA�߂��Ă̏W�c�⍑�Ƃ͂��̃V���[�}�j�Y�������菊�Ƃ��Đ������Ă����B
�V���[�}�j�Y���ɉ����āu�_���i���݂����j���v�Ƃ́A�ޏ��̐g�̂ɐ_���~�Ղ��A�ޏ��̍s���⌾�t��ʂ��Đ_���u�����i����������j�v���������ł���B
�����Č����Ɋ��u����s�i�����傤�j�v�́A���{�̐M�j��ɘA�ȂƑ��������f�ޏ��̐_�s(���傤)�Ɏn�܂�R�������B
���R�A�ޏ����u�_���i���݂����j���v��Ԃɐ���ɂ́A�����̐_���~�Ղ���ׂ̎��f�s�ׂ��s�Ȃ��A�_���i���݂����j����Ԃ�U�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���̍ł������ɍs�Ȃ��A�i���A�z�C���ɓ`��������ꂽ���f�s�ׂ̏p���A���Ȃ킿�ޏ��ɉߌ��Ȑ����������ăh�[�p�~���������A�]������̃x�[�^�[�E�G���h���t�B�����ʂɔ��������鎖�ŁA�ޏ����I�[�K�Y���E�n�C�̏�ԁi��������ԁj�ɐ���A���̛ޏ��ٕ̈ρi�ψفj�����l�q������͂��_�̍~�Ղ�F�߁A�u�_���i���݂����j���v�Ɛ���B
�����܂ł��{�C�ʼn����܂ł����ւ��͂��̎���̐l�X�ɕ����Č��Ȃ���Δ���Ȃ����A�܍��L����q���ɉh�̊肢�����߂閼�ڂ̎��f�i���セ�j�Ƃ��āA�Ղ�i�J��j�Ƃ��Ă̐����s�����F�߂��Ă����B
���i����j���ė������́A�C����p�ɋ�����f�ޏ��̎d���ݕ������A����͂������@�����܂��Ă���B
���̂Ƃ͕s�v�c�Ȃ��̂ŁA����グ�ĎO���قǕς��ς��U�ߗ��Ă�A�v���C�����Ƃ͕ʂɁA�g�̂������̉������o���Ĕ������܂��B
�����Ȃ���߂����̂ŁA���炩����f�i�����j�ɉ�����l�ɂȂ�A��p�������Ȃ��s������f�ޏ�����������B
�����ɓ����Ċm�M�������A�C�����͂����ĉ������ȏp�ŁA�������Ɛ��������B�𑀂��Ă�����ł͂Ȃ��\��������B
�C�����̎{�p�́A�ޏ��B�̔\�͂������o���u�菕���������ɉ߂��Ȃ��v�ƋC���������B
�ޏ��́u�_������ԁv�����㕗�̊i�D�����̂��̂ł͂Ȃ��A�������A�z�C���̎{�p���@�𐳊m�Ɍ�����A����̐l�ԉȊw�I�ɉ\���������o����̂ł���B
�������̐g�̂́A������ׂɂ�����i���𐋂��āA���ׂ̈̔����������u�����o���Ă���B
�u���̊��v�Ƃ͗ǂ����������̂�������̓`���b�g�����\�ʓI�Ȃ��̂ŁA�����i�ꐫ�j�ɂ͂����Ƒf���炵�����𖢗��Ɍq���ׂ̐��ݗ\�m�\�́i�댯�\�m�j�����J���̂܂ܑ��݂���B
�A�����̐��ݗ\�m�\�́i�댯�\�m�j���������ɊJ������锤���Ȃ��B
�×�����a�̍��ɓ`�����f�ޏ��́A�_�y�ޏ����i���͗֊��ޏ��s�j�̃g���b�v���ۂɋ���h�[�p�~���̉ߏ萶�����甭������]������i�����z�������j�A�x�[�^�[�E�G���h���t�B���̌��ʂŁA�]�̗\�m�\�͂̐��x�����߂鎖�Ŕ\�͂����C����ꂽ�B
����͔]������i�����z�������j�A�x�[�^�[�E�G���h���t�B���̌��ʂśޏ����u�_�����ԁv�Ɋׁi�������j�錻�ۂ��A�u�_���ޏ��ɍ~�Ղ����v�ƐM����ꂽ����ŁA���n�@���̉�����̖��M�����m��Ȃ��B
���f�ޏ��́u�C���̍s�v�͓ǂ�Ŏ��̔@���ŁA�C�����Ƃ̗֊��s�Ɋ��u�o�����C�߁v�]�̗\�m�\�͂̐��x�����߂鎖�ŁA�C�������B�Ɏ{�i�قǂ��j�����֊����f�p�́A���ꂱ�����l���ŋ���ȗ֊��i�܂킵�j�s�������A���E����ߏ�Ȑ������������I�ɂ����炷�ׂł���B
�܂���f�ޏ��́A�u���ՊE�����o�v�ɒB����Ɓu�_������ԁv�ɐ���A�����\�m���o����u�֊��ޏ��s�i�C���̍s�j��ς�ŁA���f�ޏ���C����v�ƌ��������A�����M����ꂽ�����������B
���ꂪ�P���C�����̐��~�����ׂ������\�������邪�A�x�[�^�[�E�G���h���t�B���̌����śޏ����u�_������ԁv�ɐ��錻�ۂ͎����������悤�ł���B
������A��l���ɘA�����ĔƂ����̂ł��邩��A���Ȃ��Ƃ��u�ՊE�_�M���M���v���������i�͂��j�ŁA���ꂱ���u�����āA�C�������lj߂���v�Ǝv���قǂ̐Ⓒ�����r�ꂸ�ɘA�����Ď������A���̘A������s��ȐⒸ�̉����u���ՊE�����o�v�Ɣ��ɐ_�����ԂɊׁi�������j���āu�\�m���v������B
�����œ�����u���ՊE�����o�v���A���ݗ\�m�\�́i�댯�\�m�j�̃I���E�X�C�b�`�ɐ����Ă��Ă��̈����o���ꂽ�\�m�̌�����A���B�͐_�̌������������̂��B
�C�������B�Ɏ{�i�قǂ��j�����֊����f�́A�ߏ�Ȑ��������B�Ɏ{�i�قǂ��j�����Ŕ]������i�����z�������j�A�x�[�^�[�E�G���h���t�B���̑�ʔ����𑣂����̂��ړI�ŁA�֊����f�͐��ݔ\�͂������o����i�ł��݂����\��������̂��B
���������C�����̎{�p���A�P���Ɂu����̏펯�v�ƌ����������Ōv�鎖�͊ȒP�ł��邪�A�{���u�����q���v�ƌ����u���B�s��/�����v�́A�M�I�Ɂu�������́v�ƍl�����Ă������オ�������������l������ƁA�_�s�Ƃ��Ă̛ޏ��̗֊����f�p�͏[���l������̂ł���B
�܂��A���̐��_�v�l�����q���㖖���E��k���������Ɏ������Ɏ������܂ł͍��������݂����ׁA����ȑO�̐_�s�E���s�ɏC���̍s�ł�����f�ޏ��̗֊����f�p�i�_����p�j���`�Ԃ�ς��Ȃ�����c��A�^���i�����j���여�ɓ������Ƃ��Ă��s�v�c�͂Ȃ��B
�����C�����t�A���͂���������ׂ��d�v�Ȗ����u�剤�i�������݁E�V�c�j�̖����v��ттĂ����B
����͊��鎁���i��Ύ��j�ɋ����_�ȁu������������v�ł���B
���Õ����ɂ͈Ӑ}���Ď������B���ׂɏ����ꂽ�������鎖����A�ʂ̌Õ����Ƀ|�c���ƕ����オ��u�`���_�b�v�͎j����ǂ���ŏd�v�ȍl���_�Ɛ���B
�O�@��t�E��C�������C�s������{�ɋA�҂����������̌䐢�́A�܂��n�������ł�����a�����ƌ��Z�ڈΑ��Ƃ̕��͍R�������{�̂����������ő����Ă����B
���̕��͍R���̖��������A�O�@��t�E��C�͉A�z�������f�ɋ��ߒ���ɐi�����A����͂��̍�ɏ�����B
�����Ă��̍�A�A�z�������f�Ƃ͌����Ȃ���A�z�C���҂ɋ��邱�̐^�������̕z���ړI�́A���͐����ɋ��閯���̍����a���i����͓����j�ƌ��������I�Ȃ��̂������B
�u����ȓ˔�Ȏ��͍l�����Ȃ��B�v�ƈ��Ղɔے肵�Ă��܂��Ύ��͊ȒP�����A�����̓��{�͂܂��u�����Ԃ̕��͍R���v�ƌ�����肪�d�v�ۑ肾�����B
�����������������đS���ɎU�����A�z�C���҂���A�l�g�䋟�`�����L�������̂͌����܂ł������B
�_�b�ɂ�������i�������j���g�b�v���m�̐��������̈Ӗ��ł���Ȃ�A���̍l���������Ɛ���̍���ɂ����Ă��s�v�c�͖����B
������n���������ɂ́A�u������������v���K�v�ŗL��B
�����͊ȒP�ŁA�����̏������i�������j������������Ηǂ��B
������S�Ă̖��ɁA�c���E���鎁���i��Ύ��j�̌��𒍂��Ηǂ��B
�c���̌����p����Έꑰ���A���̔C�ɍł������������炱���A�C�����̒��́u�����p(����̂��Â�)�v�������̂ł���B
���������C���̖ړI�Ƃ��Ă̓���āi�����j�ɁA�u�����M�E�k�C�M�Ɩ����̐��I�����̏K���������Ă����v�������B
�܂��C�����t�ɂ́A���X�ɕ�������A�u���l�̐M�S�ɏ悶�āv��Ύ��̎q���X�̏����ɐA�����ĕ������ɂ̎g�����Ă����B
�����A��a���삢�܂����肵�Ȃ��t�����̔���A�����p�i����̂����ʁj�Ƃ��̈�}���剤�i�������݁j���玒�����������A���̐���̊T�O�ɋ��邢�����������Ȗ������������̂ł���B
���́u���̖��������v�ƌ����r���������ړI�ׂ̈ɁA�����̎��f���ׂ��ׂɂ́A�C�����t�̑��������u���f�ޏ��v���K�v�������B
���l����R�����A�i��Łu���f�ޏ��v�����������ׂɁA�C�����t�͂�����u����̕���v���̂����B
���ׁ̈A���l���C�����t�ɂ��肢���āA�Ђ������������f���s���Ă��炤���ɂȂ�B
�d���̓{���Â߂�ׂɏ��������тɂ����B
�܂��l�g�䋟�ɋ����ꂽ�����́A�_�̎g�����_�l�i��_/�������ݗl�j�ɗd�����珕���o����A�C���̎�p���\���{����A�u�_�̎q��g�������Ė߂��Ă���v�ƌ����f�p�ȋ؏����ŗL��B
���������̈�A�̓`���́A�_�̌䗎����ʎY���đ����A�����A����A����i������j���p������g�D�I�A�d�������B
�n���̏C���`�������グ��ƁA�u���̎���ɂ͏����͖��������v�Ȃǂ̎���l�ؓI�Ȏw�E������B
�m���ɏC���`���́A���X�͌Õ����ォ�畽������̓`���Ƃ��Ďn�܂������̂ł���B
���̓`�����A����̈ڂ����Ɣ��Ɏ���A���̓`�����e�̈ꕔ�����̎���̏����ɗ�������Ղ��l�ɂ��̎���w�i�ɓK�����`������݂܂œ`����ė����B
�]���Ď���l�ؓI�ɂ͌Ñ�j�ɖ����]�ˊ��̂��̂��ォ��`���ɍ�����ȂǁA�`�����e�ɏ����Â���I�ȁu�����v�������Č���ɓ����Ă��Ă��s�v�c�͖����B
���������`���`���̕ω��͎���w�i�I�Ȍo�܂Ƃ��ė������ׂ��ŁA����͕K�v�����w�E���ׂ��ԈႢ�ł͖����B
�����Ŗ��Ȃ̂͏����̖��̂̑��݂ł��邪�A�����i���傤��j�E����i�Ȃʂ��j����������ƁA�]�ˎ���̑���l�ł���n���O���i�����O���Ƃ������j�̂ЂƂA�����͒���l�̂ЂƂƉ��������B
�n���O���i����������₭�j�̂ЂƂŁA�����̑�\�҂ŁA�����{�ł͏����̌ď̂������A�����{�ł͖���ƌĂ�鎖�������Ƃ���A�܂��A���k�n���E�k���n���E��B�n���ł͊̐��i��������j�ƌĂԁB
�m���ɍ]�ˊ��̑���l�������͒���l�́u���x�Ƃ��Ă̖��́v�ƌ����_�ł͂���ŊԈႢ�ł͂Ȃ����A�����i���傤��j�E����i�Ȃʂ��j�ɂ͍]�ˊ��ȑO����̗��j�I�w�i������A�u�]�ˊ��ȑO�ɖ��̂����������v�ƌ����Ċ��Ă�̂́A���X���\�ł���B
���̂Ȃ�y�n�͈͂������y�����x�z�͕��������瑶�݂��A�������͉����ɂł��݂�������A�ܘ_�����~�����̓y�n�̊Ǘ��𐿂������x�z�K���������ŁA������ꌹ�Ƃ��č]�ˊ��̏����̖��̂Ɩ����݂�B
�Ⴆ�Γ����i�Ђ䂤���j���y����䏯�z�ɂ������i�喾�_�j�_�����݂�A�_�X�̑��݂��������씪�`���̃A�����M�̗��E�����\�Ђ̐X���A�܉Ӑ��심�J�i����䋬�j�̍����_�ЂɒH�蒅���B
�����i�喾�_�j�_�Ђ̗R���ɂ́A�y�������������ɂ͍���䏯�\�������\���Ђ̑��ЂƂ��āA��Í����c�_(�����O��̐_�X�j���J��z�Ƃ���B
�܂��A���������犙�q���Ɉڂ鎞�_�́y���z�̑��݂ł��邪�A�������ٕ̈���ɂ������`�o�̓����̌Z�E����S���i���̂��傤/����ہj�́A���E���`���i�݂Ȃ��Ƃ悵�Ƃ��j���u�����i�ւ����j�̗��v�ɔs��A�������ɏ�������đm���ɐ����Ă����B
���̈���S���i���̂��傤�j���m�Ђ̂܂܌������̋����Ɍĉ����Ď蕿�𗧂āA�������������i���s������̖��y���j��^�����A�k�𐭎q�̖��E�ێq�i���g�ǁj�ƌ����A�x�́i�É����j�̍��E�y����̏��i���̏��Îs���E�����j�z��q�́A������āA���쐩�𖼏���Ă���B
�܂肱�́y����̏��z�͈��ŁA�Õ����Ɂy���z�̑��݂͓�����O�ɋL�ڂ�����B
���ɍ]�ˊ��́u�����v�ȑO�́y���i�����j�z���������f�ނƂ����D�c�M���i�����̂ԂȂ��j�̐D�c�Ƃ��g���B
�D�c�M���̏o���Ɋւ��D�c�_�Ђ́A�ޗǁE������������錕�_�Ёi�z�O���։�S ���_�Ёj�ƌ����A���_�Ђ���������y�z�O�E�D�c�̏��z�͐甪�S�N�̗��j��L���Ă���B
�D�c�Ƃ͊����i����ׁj����c�Ƃ��錕�_�Ђ̐_���ł���A�y�D�c�̏��z�̏����i�����j�ł���B
�����Ƒ����͓����Ӗ��ŁA���i�����j�ŁA�̎�̖����ĔN�v�̒����E��[�A�����ێ��Ȃǂ̔C���ɂ��������҂������i�����j�ƌĂсA���i�ƌ����ď̂�����B
�����̗̎傩��h�������ꍇ�ƐD�c���̂悤�ɒn���̗L�͎҂��C�������ꍇ�Ƃ�����A���オ����ɏ]���Č�҂̌`���Ƃ�悤�ɂȂ����B
�����i�����j�́A�����̎傩��C������A������ �̔N�v�̎�藧�Ď����ێ��Ȃǂ��i�ǂ����E�ŁA�D�c�Ƃ͌��_�Ђ̐_������y�n�̗L�͏������A�������Ɏ��E�E�z�g�i���j���ɔ튯����B
���͎��E�E�z�g�i���j���͎������{�̗v�E�ɍ݂��Ē����ɋ����ׁA���̂̉^�c�������ɔC���Ă����B
���������m�̗��Ȍ�͉����オ����ɂȂ�A�D�c�Ƃ͎z�g�i���j���̎�����o�Ă��̕��Ƃ������ɓn���Đ퍑�喼�ɐ��������B
���j�ɂ͘A�������݂�B
�����A���̎���ӂƂ����ȗ��j�Ƃ�����ăX�p�b�Ƃ��̎��ゾ�����o���āA�u�����ƌ����g���͍]�ˎ��ゾ�v�ƌ����Ƃ��������C�Ō����B
����ł͖Ӗڂ̎҂��ۂ̐K�������G���āu�ۂ͍ג����������ł���v�ƌ����悤�Ȃ��̂ŁA�c�O�Ȃ��炻���������́A���j�̘A�����������m���ŕ��������đ傫�Ȓp�������B
���j�I�Ɏx�z�K�w�����������̖��Ⴊ�A�_�����S���ɐ������̂ł���A���������K�w���ʼn����x�z�E�ł��鏯���▼��A�����Ȃǂ�C�����B
���������E���c�ȗ��̍ݒn�L�͎����̎҂������A���q���`�퍑���̑喼�̉Ɛb�������Ƃ��L�͎҂Ƃ��č]�ˏ����̏����߂���������Ȃ��Ȃ��B
�����ɂ��Ă������ɂ��Ă��s����悾����A�����~�ɂ��Ă������~�ɂ��Ă��w������̎������������̏Z���ł���B
�܂�]�ˊ��ɐ����ċ}�ɏ������a��������ł͂Ȃ��A�܂��y�n�̖��i���c�j���������������݂�A��������ꌹ�Ƃ��Ė���ł���B
�����Ċ̐S�Ȃ̂́A�l�g�䋟�`���̓`���͌�̎���ɉ�����قǗ������Ղ��悤�ɓ���̏ɍ��킹�ď������ω����ċ��鎖���l�����ׂ��ł���B
�ܘ_�̂̓`�����A�����������r���ł��̎���̊��ɍ��킹������ɒ������ꍇ�������A���ꂪ�`���̂̎��ł��邩�玞��l����v���Ȃ����͊��ė��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
����������Ƒ��l�B�����́u�l�g�䋟�v�̖ړI�𗝉����Ă��āA����ł��u�����P�����f�v�ׂ̈ɂ͐l�g�䋟���d���������ƌ��_�t���ċ����̂����m��Ȃ��B
����I�Ɂu�l�g�䋟�v����������ׂɁA�X��A�u�ҏb�̐��сv�Ƃ���`��������݂ō�����\�����L��̂��B
�ޓ��n�����������{�Ɍ����ė������A���{�͕��a�̖��E�ڈΑ��i���݂�����/���Z�ꕶ�l�j�̊y���������B
�����Ă��̊y���͓n�������B�ɕ��͂ŏ������A���a�̖��E�ڈΑ��i���݂������j���؎��i�ӂ��イ�j�ƌ������ŗꑮ�����ꕞ�]��������ꂽ�̂����A���̌o�܂̋L�^�͈Ӑ}�I�ɏ�����ĂقƂ�ǎc���Ă͂��Ȃ��B
����ɓ��{�ɂ���ė��āA��Z�����E�ꕶ�l�i�ڈΑ�/�G�~�V���j�̓y�n�͋��D���A�؎��i�ӂ��イ�j�ƌ������ŗꑮ�������n�������ɋ���ꕶ�l�i�ڈΑ�/�G�~�V���j�ւ̔��Q���Î��L�E���{���I���V���~�Փ`���Ƃ�����R�[�����܂ł߂�������Č��`�����C�����t�ɋ����ĈӐ}�I�ɏ����������B
�����Ă��̌�N�������n�������E�������i���炼��/�_�k�R�x�����j�Ɠn�������E�����i������/�C�m�����j�ɋ����e�������Ɛ���i�������j�̍������A�Î��L�E���{���I���V���~�Փ`�����C�����t�ɋ����ĈӐ}�I�ɏ��������ĉi�v�I�Ȏ����i�������x�j�x�z�̐��̊m�������B
����Ɏc�����̂��A�V���~�Ր_�b�Ƒ����̋r�F���ꂽ���`���ŁA����͉A�z�����C���R���B�ɋ����đS���ɍL�������B
�`���ɂ́A�B���ꂽ�����ւ̃��b�Z�[�W������B
�C�����t�̉���l�g�䋟�`���́A���a�̖��E�ꕶ�l�i�ڈΑ�/�G�~�V���j�W���̗L�͎ҁu���v�̖��ɓn�������̎q��g�U�点�A���́u���v�ɓn�������̌�������u�����ߒ��������v�Ƃ�����A�����I�ł���B
�܂�ڈΑ��i���݂������j�̒n�E���{�����������������B���ړI�ŁA�s��ȑn��A�Î��L�E���{���I�͕Ҏ[���ꂽ�B
�������V���~�Փ`�������O�Ƃ���n�������i�����j���͂ɕ��͔��Q�̎����͎�����Ȃ�����A���̔閧�͂��̍��ɂƂ��ĉi���ԕK�v�������������m��Ȃ��B
���̍���ɍ݂�p���́u�Õ����ɋL�ڂ���Ă���v�ł͂Ȃ��A���j���u�������̖ړI���݂��ĒN���n�߂����̂��H�v�ƌ������_�ő�����ׂ��ł���B
�܂蕨���̎n�܂�́A�M�ɂ��Ă��K���ɂ��Ă��ŏ��͉��҂��̈Ӑ}���݂��Ďn�߂�ꂽ���̂ł���A���j�����҂��̂��瑶�݂��鎖�𗝗R�ɖ������ɋ^��Ȃ��̂ł̓C���e���W�F���X�������߂���B
�����������Č���ƐG���ꂽ���Ȃ����{�j�̈Õ��������オ���ė����B
�܂����l�̉ߒ���H�����č��ɒu���Ă��A�ߍ��ł͌��߂����̂����l�J��c���C���f�A���i�l�C�e�B�u�A�����J���j���키��ʂ̉f��i�������j�͂߂�����n��Ȃ��Ȃ��Ă���B
�܂�A�����J�嗤�J��j�̋�J�b�����A���l�̓y�n������ɕ��͋��D�����������������肽������ł͂Ȃ����낤���H
�u���f�ޏ��v���C�����t��ʂ��Đ_���ƌ����A��F�ɐ��܂�ς���āA�_����̎�����҂��Y�ގ��ɂȂ�B
���̉�̌����������u������ҁv�́A�����i�ނ炨���j�̏��ő厖�Ɉ�Ă��A����̑��̃��[�_�[�ɂȂ��čs���̂ł���B
���|�̐����剤�̌��́A���N�̎����u�ĂāA���܂˂����{�ɍL����A�����̓���͂Ȃ���čs�����̂��B
���̗ǂ��E������^���E�s�^����ʂɂ��������Ƃ��āA�u����i�������j�v�ƌ����`�̐����͐_�ォ�瑶�݂����B
����i�������j�̐����͑���ɑ��镞�]���Ӗ����A�������̓I�ɏؖ������i�ł���B
�_�O�ɉ�����ޏ��̐����͐_�Ƃ́u����i�������j�v�ł���A�u�_�̌����v��ׂ̐_���ȍs�ׂł���B
�]���āu�_�i������j�v�������ł��邪�A��𗍂܂��������̈���ɂ拒��u�_��i�����₭�j�v�Ƃ͏����Ⴂ�A�u����i�������j�v�̐����͂����܂ł��u���]�I�ȍs�ׁv�ƌ������ɐ���B
����͋Ɏ��R�Ȏ��ŁA�����Ĉٗl�Ȏ��ł͂Ȃ��B
�����C�����̎�p�ɉ����āA�����ɂ��V��������n�����鎖�́A���Ȃ킿�u�_�̗̈�̔��e�v�������̂ł���B
�]���āA�C�����́u���݂̗��j�v�̒��ɉ����āA���̐��_���剤�i�������݁E�V�c�j�̖����Ƃ��Đ����Ă����B
�����ېV���O�̍]�˖����ł����{�̐l���͎O�疜�l���ǂ����ŁA�����܂��Ȑl���́u���݂̎l���̈�v�ƌ��������B
�]���Ď��オ�k��قǐl���͏��Ȃ��B�A�z�R���i�C���ҁj��������ꂽ�u���̓����v�̖����́A��a�̍����������̒i�K�ł͑����ɗL���Ȏ�i�������B
���̌��������o�A����d�˂āA������ݒʂ�u�P���a�����v���`������čs�����̂ł���B
�l�Ԃ͊�{�I�Ɂu�Q��Љ�̐������v�ł��邩��A�u�A���ӎ��i�Q��j�v�������˂ΌǓƊ��ɉ����ׂ���Đ����čs���̂��h���B
���̌Q��ӎ��̋A�����鏊�������������薯���������肷��̂ł��邩��A�����Ȃ鎖�ۂł����́u�A���ӎ��I�v�ȗ��ꂪ�ς��Δ��z���ς��A�������N����̂ł���B
���̑����́u�A���ӎ��i�Q��j�v��Z�����Ȃ���������͂��Ȃ�����A����i�������j�̖����I�i�����I�j�Z�����B��̕��a�I��i�������B
�]���Đ���i�������j�̐������u���f�I�Ȑ_���v�Ɖ��߂����l�ɐ���A�n�����������M�ƏK�����č��J�ɐ��I�ȗv�f���܂ޛޏ����_�y�̗l����l�g�䋟�`���A�_�ɖL���i�L��j���F��_���u�L�N�x��v�̗����u�ÈōՂ�v���A�z�t�ɋ����đS���ɓ`�d��������A���{�l�̂����炩�ȁu���ɑ���K�́v�����������B
������i�V�c�j���r�u�F���E�i�݂Ȃ͂炩��j�v�́A�����������ꂩ�琶�܂ꂽ�u������v�̌Z��o���̈Ӗ��ŁA�u���̏㖳�����������v���Ӗ����Ă���B
�����剤�i�������݁E�V�c�j�̖��������A�킪���ō��̍��ƓI�A�z���f�����m��Ȃ��B
�ܘ_�A�����Ō����u�����̓���v�͑�g�i�吨�j�̘b�ŁA�ׂ�������̃C���M���[�͑��݂���B
���{�ƌ������ł́A�͂ݏo���҂͊��邪�o���͖]�߂Ȃ��B
���ꂪ���Ԃƌ������̂ł���B
�{�\�Ȃ̂��A�u�F�œn������Ȃ��v�̋A���ӎ��A�u�o��Y�͑ł����v�̉����шӎ��A�u���ɏo�����Ƃ��ʂ���v�ƌ����Öق̗����ӎ��A�����ł͒ʗp���Ȃ��u�͂��v�ƕ\������m�[�A�u�l���Ă݂�v�ƕ\������m�[�̌��_�������ɂ���B
�܂�A�u�剤�i�������݁j�̖����v�����A�ǂ�����������a�����������I�ɓ��ꂳ���A�P�ꖯ���ӎ��Ɏd���ďグ���̂ł���B
���݂̏펯�ŁA�u����ȉA�d�͂��肦�Ȃ��v�Ɣ��f����̂́A�~�߂ė~�����B
�����������́A����̊����ǂ߂Ă��Ȃ��B
���̂Ȃ�킸���Z�\�N�O�A�u���U���v�ƌ����u���肦�Ȃ����́v���A�����ɏ펯�Ƃ��đ��݂����B
����́A���������l�g�䋟�`���ɁA�ւ���Ă����̂��u�C���R���ł���̂͊ԈႢ�Ȃ��v�ƁA��y�͊m�M����B
���������肾�Ǝv�����A�A�z�t�Ɏn�܂镐�p�͕��m�E����A�ʂĂ͌|�\�ɂ܂Ōq����A����������A�����M���ƌq�����āA���̃����[���㐢�Ɍq���čs�����B
�����������M�E�k�C�M���̒S����Ƃ����A���̒���̕����E������ƕ���œ��͖[���̕����E��t�����L���ŁA�����̐�t����͂��̌��Z�̗�����k�C�꓁���Ə̂����B
��t�ƌ������ŁA�Ȓ��n�Ձi���傭�Ă�����j�̖���E�쑍���������`���Љ�悤�B
���ꂪ�^���������ނɁA�ٓV�l�i���P�j�ƌ�(���[)�̒{�����i�b���j�����[�̕���ł���B
�C���h�E�q���h�D�[���̐_����J�́A�ꕔ�`��ς��Ȃ�������{�̕������_���K�����C���M���ɉe����^���Ă���B
�O�@��t�E��C���`����t�E�Ő������{�Ɏ����A�����o�T�̒��ɂ��A�q���h�D�[���̋��`����J�̐M�͊܂܂�Ă����B
�_�͗��l�A�_�ɕ�����x��̌��_�́A�C���h�E�q���h�D�[�����V���@�_�i�j��_�j�ɍ݂�A�q���h�D�[���͐����Ȑ_�ŁA�q���h�D�[���̎O�ō��_�̈ꒌ�̃V���@�_�i�j��_�j�̏ے��̓����K�i�j���j�ł���B
�܂�C���h�́A�Ñォ��l���̎O��ړI�Ƃ��ăJ�[�}�i�����j�A�_���}�i���@�j�A�A���^�i�����j���������鍑�ŁA�O�含�T�Ƃ����u�J�[�}�E�X�[�g���v�A�u�A�i���K�E�����K�v�A�u���e�B���n�X���v�ƌ��������T�ݏo�������Ɛ��Z�I�̍��ŁA���̃q���h�D�[���̉e���������A�����炩���������{�̐��K���̌��_�����m��Ȃ��B
�Ⴆ�C���h�̓y���M����n�܂����q���h�D�[���̏��_�E�T���X���@�e�B�[���A�����o�R�œ��{�ɓn�������ٍ��V�̌��^�ł���B
�ٍ��V�͌��^�ł���C���h�y���̏��_�E�T���X���@�e�B�[�̍�����A���̏��_�Ƃ��Ă̑��ʂ������Ă����l�ŁA���̃C���[�W�͓��{�ɓ����ė��Ă�������݂������B
���_�E�T���X���@�e�B�[�̓q���h�D�[���̑n���̐_�u���t�}�[�̍ȁi�z���_�j�ł���A�T���X�N���b�g��i����j�ŃT���X���@�e�B�[�Ƃ͐��i�j�������̂̈ӂł���A���ƖL���̏��_�Ƃ��ăC���h�̂����Ƃ��Â����T���O�E�x�[�_�ɉ����āA�n�߂͐��Ȃ��A�T���X���@�e�B�[��i���̎��̂ɂ��Ă͏�������j�̐_�b�ł���B
�����ɉ�����k�B���i�i�f�[���@�_�b�^�{���A�����̓_�C�o�_�b�^�i�j�̊ϐ�����F�ɂ��āA���̗��ҁi�ٍ˓V�Ɗϐ����j�́A�u������]���ɋ����鎖�ɂ���Ēj���~�ς��鑶�݁v�ƌ������ʐ��������Ă��āA���{�̖��O�̊Ԃł͏����̎����w���āu�ٓV�l�v�����́u�ω��l�v�ƕ\�����鏊����ٍ��V���u�ϐ�����F�̉��ρv�ƌ��Ȃ���ċ���B
�^���@����C�E�V��@�̉~���̍s�����ɂ͑����ٍ˓V�̓`�����c���Ă��邻�����B
����A�C�s��ς��̈���m���l�̎q�ŁA�������m�����@�̓�������ڂ������B�́A���g�̐l�ԁi�����j�ł͂Ȃ��u�_���Ɛڂ����v�Ƃ��闧���̕X���������̂��H
����Ƃ��A�ނ�͓��ʂȔ�@�i���f�j�ɂ���āA�����⒬�������A���̓y�n�ׂ̈ɁA�V���Ɂu�������ٓV��F�v�����o�����̂����m��Ȃ����A�^���͔���Ȃ��B
���X�C���h�E�q���h�D�[���̐_����J�ɂ̓J�[�}�i�����j���̗ƂƂ���v�z���݂�A�V���@�_�i�j��_�j���_�L�j�V�i䶞k��V�j�A�J�[�}�E�X�[�g���i�C���h�O�含�T�̂ЂƂj�Ȃǂݏo�����v�z�̍�����������A���{�Ɏ������܂ꂽ������_���K���̏C���M�ɂ��̉e����^���Ă���B
�Ȃ��ł��]�̓��E�ٍ��V�͗��`�ٍ��V�ŗL���ŁA�]�̓��̖{�{�Ƃ���铴�A�ٍ͕��V�M���������܂��ȑO����A�����̐����q�{�Ɍ����Ă��u���A�M���������v�ƌ����B
���̕ӂ�̉��n���A�u�����ɂ���đ��������v�ƌ����C���[�W�����N�����̂����m��Ȃ��B
���̍���ɍ݂����̂��A�u�����̌��̓����v�ƌ������ƃv���W�F�N�g�ƌ������ɂȂ�B
�C���h�̓y���_�b�ŁA���̉��̖��E�O����i�T���X���@�e�B�[�j���u�j�q�ɕς��Đ��������v�ƌ������e�́u��k�B���i�i�f�[���@�_�b�^�{���j�v���q�܂菗�ł��A�q���i���j�ł��b�i���j�ł������ł��鎖��������o���r�Ƃ��Ę_�����鎖�������B
���̓y���_�b�ŁA���̛O����i�T���X���@�e�B�[�j���̖����u�j�q�ɕς��Đ��������v�ƌ������e�́u��k�B���i�i�f�[���@�_�b�^�{���j�v���q�܂菗�ł��A�q���i���j�ł��b�i���j�ł������ł��鎖��������o���r�Ƃ��Ę_�����鎖�����������炵�āA���͏b�ƌ��������炵���B
�b�����@���V�̒��ԂŗL��A�b�i���j�ł������ł���̂Ȃ�A�{�����i�b���j�ɗ����Ă������ł��闝���ł���B
�ƂȂ�ƁA�u�A�z�C�����t���Ö��v�Ǝv�����l�g�䋟�`���̌��_�����̃C���h�E�q���h�D�[���̏��_�E�T���X���@�e�B�[�ƕ��@���V�̒��ԁE�b�i���j�̒{�����i�b���j�̕���u��k�B���i�i�f�[���@�_�b�^�{���j�v�̗����A���≎�Ȃǂɉ��H���ĉ��p�����̂ł͂Ȃ����Ɛ��������̂ł���B
�����ɁA�ے��I�ȏ���������B���[�̍��i���̐�t���̈ꕔ�j�������͐��a�����V�c�Ɨ��̌n�}�ł���B
�ڍׂ͕s�������V�c�i���j�Ɗ�̎q���A�����`�������[���Ɉڂ��ēy�n�̗̎��������Ǖ������[�̗̎�ƂȂ�B
�c���\��N�i��Z�S�\�l�N�j�A�������`���n�ł����v�ے����r�ɘA�����Ĉ��[��v������A�����̑�֒n�Ƃ��Ĕ��ˍ��q�g�O���ɓ]���ƂȂ������A���Ԃ͔z���Ɠ��������ō݂����B
�����Č��a���N�i��Z�S��\��N�j�A���`���a������Ɓu�Ռp�������Ȃ��v�Ƃ��ė����͉��Ղ��ꂽ�B
���n�Ղ́u�쑍���������`�v�͂��̗������̈�b�B������u�ˋ�̕���v�ł���B
���̔��[�i���j�Ɨ����Ƃ̕��P�A���n�Ղ̕M�ɂ���Ĕޏ��͎��甪�[�̍ȂƂȂ鎖�Ŕ��[�̓{�����߁A�₪�Ă͕��S�ւƓ����B
�����A���[�ƕ��̌��Ƃ̋Y��̖A�u�G���̈����̎�������A��Ε��P�����B�v�Ƃ̖ɁA���[�������G�������̎�������A��B
�����A�u���������Ƃ̖v�ƂȂ�������ɂ��A���j���Ĕ��[�̍��݂��A�����Ƃ͎��X�ɕs�K�Ɍ�������B
�����P���A���̗����x�ɐS��ɂ߁A���ʂ����A���[�̓{���Â߂�ׂɁu���[�̍ȁv�ƂȂ錈�ӂ�����B
����ŁA�����Ƃ̐�̌��ɂ��A���[�͕��P�ƕx�R���K�i�ق���j�œ�������Ɏ���B���́A���[�ɂ͕����P�̂�������m��Ȃ��ߋ��̍��݂ɂ��A�d���A���O�Ƃ��ĕt���Ă����B
����́A�����P��{�����i�b���j�ɓ����āA���̐�����Ȃ�u�ϔY�̌��v�ƂȂ���ƁA�ŏ�����̊�݂��w�i�ɂ������B
���X���P��l��{�����i�b���j�ɗ��Ƃ��݂̂Ȃ炸�A���P�Ɂu���[�̎q��s�܂��悤�B�v�ƌ����S�Â��肪�������̂��B
�x�R���K�i�ق���j�œ������������P�͂₪�ĉ��D���A���̋ʂ��Y�ݗ��Ƃ��B
���n�Ղ͏���Ȃ��̉��D�������Ă��邪�A��~�ɂ���ĕ��P��g�����点���Ȃ�A����͂�͂�{�����i�b���j�̌����Ȃ̂ł͂���܂����B
�u������]���ɋ����鎖�ɂ���Ēj���~�ς����F�i�ٍ˓V�j�̎��߁v���A�n�Ղ̕M�ɂ�蕚�P�́A���̕���ɉ����đ̌����Ă���B
���[�̏�~��]��������A�C�e���Ƃ��āA�u�@�،o�v�̏b���̉߂������͂��u��k�B���i�v���o�ꂷ�鎖�ƂȂ�B
�n�Ղɂ��A���ɐl�ԁA���������̕P�N�Əb�̌����������̂͑����ɒ�R���������̂��낤�B
���n�Ղ̂��̕M�̕��䂪�A�����M�̒n��I���A���Ƀ_�L�j�V�i��חl�E���j�Ǝv����ς̉��g���k�C�M���i�V�ꐯ�M�A�k�l�M�A�k�ɐ��M�j�ȂǁA���炩�ɖ��������ނ��Ƃ��Ă���B
���������`�̃x�[�X���A�z�C���������`�[�t�ɂ��Ă���Ȃ�A��v�o��l�ҁE���P�i�ӂ��Ђ߁j�̖��̂ɂ��Ă��C�����t�̕ʏ́E�R���i��܂Ԃ��j���������R���P�Ȃ̂����m��Ȃ��B
���̕���A�ߐ�(�]�ˊ��E�����E��������)�ɓ����Ă��珑����Ă��邪�A���̌��_�́u�̘b�̓`���ɂ������v�ƌ���B
�n�Ղ��t�����u���P�i�ӂ��Ђ߁j�v�̈Ӗ��́A���炩�Ɂu�R���i�C�����j�́i���L����j�P�v���Ӗ����Ă���B
�����P�ɂ����鏗�������҂��͎v������Ȃ��Ă��A���[�͂܂������A�z�t����R���H�}�́u��_�i��������/�T�j�v�ł���A���̋ʁi���l�̎q�j�͍c���E���鎁���i��Ύ��j�̌��������u�D�G�ȑ��݁v�ƈʒu�A�����Ă����̂ł���B
�k�C�k�l���M������������������ǁA���̎g���̐_������B
�u�g���v�ƌ����Ă��Â����Ă͂����Ȃ��B
������F�͉F�����x�z����ō��_���B
���̎g���_�������͂��i�i�ɋ����B
����ŁA�u�T�i�I�I�J�~�j�����̎g���_���v�ƌ����Ă���B
�����ېV�O�͑S���I�ɖ����{�ƌ����_�Ђ����������A���ꂪ��Ƃ̊ւ�肪�����B
�܂�u��̕ۑ��{�\�v���F��̊�{�ɂ����M���B
���̎g�����A�T�ƞ��i�t�N���E�j�ŁA�T�̕��ɂ́u��v���_�Ёv�ƌ����Ӗ��[�Ȗ��O���t���Ă���B
�T�_���Ƃ��Ēm���Ă������ɂ̗{���_�ЕM���Ɂu��v���_�Ёv���A���̖����Y�o�������R�ƌ����R�̘[�ɂ���B
�����R���i�T�j�_���ł���B
���̐_�Ђ̘T�́u�k�l�i�����j�̎g���v�ƌ������ɂȂ��Ă���B
���ꂪ�k�C�M���̒��ɂ��郄�}�C�k�M�ł���B
���i�t�N���E�j�̕��͒����_�ЂŁA�n���͌Â��A�m�X�v�����E�m�X�v�F������c�̔��ӎv�������Ղ����̂��n�܂�ŁA�֓��ł����w�̌ÎЂł���B
�u���������{�A�����Ёv�ȂǂƌĂ�Ă������A�����ېV��̐_���������ɁA���̂������_�Ђƒ�߂��A����ƂƂ��ɍՐ_�����������F����V�V�䒆��_(���߂݂̂Ȃ��݂ʂ����݁j�ɉ��̂��ꂽ�B
�����_�Ђ̎g���́u�k�C�̞��i�ӂ��낤�j�v�ł���B
�t�N���E����Ӓ��ڂ����J���p���`���A��𐧂���u�_�̎g���v�ł���B
�֓��̘T�_�Ђ��\�Ƃ���́A�����O��_�Ђ̂ЂƂu�O���_�Ёv�ł���B
�T�_�Ђɉ����ĘT���u�_�̎g���v�ł���ƌ����v�z�͂ǂ����痈�����A�ǂ��������E�C�����ɂ��̌����L��B
�܂蕚�P������A�s�܂����̂������_�̎g�����_�i��_���T�j�Ȃ̂ł���B
�����`�̗����Ƃɖ߂�B
��t���َR�s��^�q�ɖ����@�i���[����R�����@�j������B
�V���N�ԂɁA���[�̍��̑喼�A�����`�N���̔���ɂ��A�I�B����R�̒����ʉ@�E�����Ƃ̋F�莛�Ƃ��ĊJ�R���ꂽ��[���B��̌Ë`�i����R�j�^���@�̎��ł���B
�܂�A�����Ƃ͐^���@�Ƃ̉��������B
�����@���A�I�B���������̖����C���@�̖�������������M�̏ł���B
���̖����@���炿�傤�ǖk���i�S��j�̕��p�ɈӖ��[�Ȓn��������B
��[���s�̈�p�ɋ����[�S�x�R��������A���̕x�R���̕��Q�n��ɂ���n�����A�u���|�v�ƌ����A�܂�Ŕ����`�����ۂɍ݂��������Ƃ��n���ł���B
�y�|�����z�́A�×���萫�����Ӗ����錾�t�ł���B
�䂪���ł́A�l��������l�דI�Ɍ���ɐB������s�ׂ��y�|����z�ƌ����B
���́y�|����z�̌ꌹ�ł��邪�A�̊_�̌ꌹ�́u�̊|���v�ł���A�锇�����u�Ă��i���|���j�v�ł���B
�܂��ِ��ł́A������Ӗ�����u�|����v�̌ꌹ�́A�_���i���݂����j��́u������v���痈�Ă���ƌ�����������B
�܂�A�z���f�̐M�ɉ����Č������͐������h��ׂ̎��f�V���Ƒ����Ă��āA���̍s�ׂ́u������_���i���݂����j�点�鎖�v�ƌ����F���ł���B
������͑��n�Ղ́u�쑍���������`�v�̘b�ł��邪�A�u����v�̈Ӗ����u�삯��v�ł��邪���Ă鎚���Ⴄ�B
���P�̓t�B�N�V�����Ŏ��݂��Ȃ��̂ŁA�N���������A�����P���ׂ̈ɁA�����u�|����ꂽ�v�ƌ����u�̘b�i�`���j�����݂����v�Ɖ��߂���̂��Ó��ŁA�����Ȃ�Ɛ̘b�̕��͏C���R���̎d���Ɖ��߂���̂��Ó��ł���B
���������̏b���A����̊��o�ōl���Ă͂����Ȃ��B
�R������_�i�T�j�ł���A�������ƌ���ꂽ�ܑ㏫�R�E����j�g�ɂ��A�u���ވ���݂̗߁v�����z����鎞�ゾ�����B
�܂�A�_�̎q���h���_���Ȏ��f�ł���B
�������u�����[�v�Ɓu���P�v�Ƃ́u���|���v�͂����܂ł��`���ł���A�����ɂ͓V��`���ɍ݂�悤���V�̋�i�Ă�̂���/�Ă�̂��ʁj���C���R���̍s�҂̎d�ƂȂ̂ł���B
�������i��t���j�ɍ݂�n���u���|�v�͓���E�����`�L���f���i���̒��ꟁj�̒��j�����`ꟂƂ̉Ɠ����̐킢�ɔj��A���n�����s�g�ȌÐ��ՂŁA�S��̕��p�ɓ���B
���ȏ�ɐM�S�[������̎��ł���B
�S�啕���̎��f���A�����Ƃ��C�����ɖ����āA�����Ɏ���s�����\���͊��Ă���Ȃ��B
�����͑��n�Ղ��A���̓y�n�ɖ����ɓ`���u�l�g�䋟�`���̉\�v���Q�l�ɁA��i�Ɏ����ꂽ�\�������Ă���Ȃ��̂ł���B
�܂�A���n�Ղ��쑍���������`�́A�R���i�T����_�j�M�Ɛl�g�䋟�`�����]�ˎ���̓������ɃA�����W���������ł���B
���n�Ղ����������`�́u���v�́A���{�×��̐M����u���v���Ă���B
�����`�i�����m�j�ł���A���̖��͔��[�ł���B
���{�̐_�b�̃L�[���[�h�́u���v�ƌ��������ł���B
�܂��A���Ɋւ��l�g�䋟�`���́A���{�S���ɐ��������݂���B
�_�b�̓`���ɂ��ƁA�X�T�m�I�i�{�����j�ɂ́A���l�̎q�����鎖�ɐ����Ă���B
�唪�B�i�����₵�܁E���{�j�A���S���i�₨��낸�j�̐_�A�����i�₠���܁j�̂��낿�A�����i�͂��܂�j�_�A�����ăX�T�m�I�̔��l�̎q�A�܂�A�q�����l�������̂Łu���v�ɂ������̂��A�u���v���厖�Ȃ̂Ŗ�����蔪�l�̎q�ɂ����̂��B
���炭�A�u���v�Ɓu���v�ɓ��ʂȈӖ��������L�邩��u�����`�v�ł���A���̐����ł͍݂蓾�Ȃ������̂��B
�����M�͓`�������A�n���l�̑�����͓��ȂǕӂ�ł̐M�ł��������A����ɋE���ȂǂɍL�܂��čs�����B
���������̎�����́A���̋֎~���ꂽ�@�������鉓��Ȍv��ɗ��p���鎖���l���t���Ă����B
�S�ẮA����������ړI�Ƃ��������̃R���g���[���ł���B
����ɂ́A�܂��������Ȑ��s�ׂ͋֎~���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�܂薯�O�̐��s�ׂ������R���g���[�����鎖���l�����̂ł���B
���S��\�Z�N�i����\�ܔN)�ɁA�����M�ő�̍s���u�k�C��(������)�v��́u�������ɂȂ��M�ł���v�Ƃ��ċ֎~�����B
�\���������R�́u���I�̗���v�ō݂����B
�܂�S���ɂ��閭���{�́A����̋֎~������܂Łu���I�Ȃ��̂����e�������͏��シ�鋳�`�������v�Ɛ��������B
�������̌��O�֎~�����֎~�@���������M���E�����́A����������Ȃ��������̔閧�@�ցu�A�z�t����R���H�}�v�ɂ���ĕz������A�����̐��ӎ��Ƃ��Ē蒅���čs�����B
���̋��`�̌��Ƃ��Ď��グ�A���p�����̂��u�^�������v�ł���A���̑S�����z�ɂ��C�����i�R���j��������A�Ӌ��̋�������R�[���t���܂ŕ��������ĕz���ɓw�߁A���l���Ă����B
�\�����A�����̌��͎҂̈ӌ��ɓY��Ȃ��@���́A���̐������[����ɐg���B���B�܂����������̌��O�ƈႤ�ړI�A�J���́i�����j�̑�����ړI�Ƃ����B�������M���́A�C�����i�R���j�ƂƂ��ɑ��X�ɎU���Ă������B
�S���̐_�Ђ̘e���K�i�ق���j�Ƃ��čՂ��Ă���_�l�ɎR�m�_������B
�R�̐_�́A�t�A����̐_�l�A�q�����̐_�l�Ƃ��ĐM����Ă���B
���̔��z�́u���������i�炦���ɐ_���h��v�ƌ����l�����ŁA���^�͋��̎劲�ɋ������̂��I�ꂽ�B
���̋��u���A�̎p�v��f�i�����邩��ŗL��B
�]���āA�R�̐_���u�Ï��[���ĂԎ��̌Ăі��v�Ɛ������B
���̎R�m�_�A�c�_�ƌ����閯�ԐM����h���������A���̌��C�����i�R���j�̊����ƌ��ѕt���A��������M���Ƃ̊ւ������߂āA�e�n�́u�l�g�䋟�`���Ɍ��ѕt�����v�Ǝv����B
�y�n�ɋ����ẮA�u�����l�v�ƌĂԒj���̐_�l���R�m�_�ƈ�𐬂��A�u�܍��L���A�q�����F��v�Ƃ���Ղ������B
�܂��A���w�␅�����̏����Ɂu���a������Njq�l���v�̂����v���肤�_�ɂ��Ȃ��Ă���B
�A�����J�嗤�̘J���͕s���ɑΉ������̂́A��l���I�ȓz��f�Ղł���B
������A���{�̑�a����́A���Y�͌���ׂ̈ɁA�u�Y�߂�A���₹��v�ł܂��Ȃ������������B
�܂��ɁA���̌[�֎�i�ɏC������������B
�܂�A�M���Љ�Ƃ͐����́u���I�ɐϋɓI�ȋ����v�������ɐA�����鎖�ɁA�u�A�z�t����R���H�}�v�́A������ɖz�������̂ŗL��B
��
|
 �y�V��C�����ƌ��_�E�l�g�䋟�`���z��Җ{���E��ؕ����\���y�[�W�y�T�C�g�i�r�z�ɖ߂�B
�y�V��C�����ƌ��_�E�l�g�䋟�`���z��Җ{���E��ؕ����\���y�[�W�y�T�C�g�i�r�z�ɖ߂�B �y�V��C�����ƌ��_�E�l�g�䋟�`���z��Җ{���E��ؕ����\���y�[�W�y�T�C�g�i�r�z�ɖ߂�B
�y�V��C�����ƌ��_�E�l�g�䋟�`���z��Җ{���E��ؕ����\���y�[�W�y�T�C�g�i�r�z�ɖ߂�B