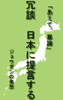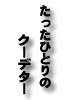�� �M���͌��݁A��������k�i�~���N���W���E�_���j�����g�o�yjiyoudan's Website �z������ ���̂v�d�a�T�C�g���̃R���e���c�i�L���j���u���p�v�E �u�]�ځv���鎞�́A�E�E�E�E�E�E �K������Җ��E��������k�L������ŏo�T���̓����A�h���X�������N�œ\���ĉ������B���A���^�C���E�҃r�W�^�[ SAMURAIFACTORY
�y�����m�푈�̉����E�E���������E�����E�����Ύ����̉A�d�z ��Җ{�� �E��ؕ��� �\���y�[�W�y�T�C�g�i�r�z�ɖ߂�B �i��㎵�\���N�ɓǂޓ��{�j�j �E�i�����m�푈�֎��鉓�����哱�����֓��R�j�i��㎵�\���N�ɓǂޓ��{�j�j �E�i�����m�푈�֎��鉓�����哱�����֓��R�j�������� �i��㎵�\���N�ɓǂޓ��{�j�j �E�i�����m�푈�֎��鉓�����哱�����֓��R�j�������� �i��㎵�\���N�ɓǂޓ��{�j�j �E�i�����m�푈�֎��鉓�����哱�����֓��R�j�������� ���̏����́A�y��̏����� ��������k�i�~���N���W���E�_�� )�z�̗��j���߂�������������i�ł��B�� ����WEB�T�C�g�Ɋւ��邷�ׂĂ����쌠 �́A��ƁE��������k �ɋA�����܂��B��������k(Miracljoudan) �̗R���́A
This novel is a work of novel writer�ynovelist ��������k (Miracljoudan) of the mystery�z.
�������y�c�����K�̉e�l�z��� �������y���j�̃~�X�e���[ �z������������������ �y�����m�푈�̉����E�E���������E�����E�����Ύ����̉A�d �z �i�i��㎵�\���N�ɓǂޓ��{�j�j �j �i�����m�푈�֎��鉓�����哱�����֓��R�j �y�� �z ���̏����́A�y���{�j�E���j�̃~�X�e���[ �̃V���[�Y���X�g�z�̈�ł��B�� ��������k�̏���
���쌠 �͂����܂ł���҂ɂ���܂��̂ŁA��������k ���_�E���� �̋L�q���e��ғƎ��̐V�� �ł��B�@�I��i �ɑi�������Ē����܂��B�� �z��̏����ƁE��������k�i�~���N���W���E�_�� )�y��җ����Љ� �z�� �z�y���ό�������̍��� �͑��݂���z
���v�����T�C�g���́����ΐF �̕\�����W�����v�E�N���b�N �ł��B
�������y���j�̃~�X�e���[ �z������������������ �y�����m�푈�̉����E�E���������E�����E�����Ύ����̉A�d �z
���������������������m�푈�E�������哱�����֓��R�T���j �����m�푈�E�������哱�����֓��R�T���j
�y�����m�푈�E�������哱�����֓��R�T���j
���{�͓��\�ܔN�i������\���N�j�A�����m�푈�̔s��㎵�\���N���}����B���I�푈 �ŏ������A���V�A�Ƃ̊ԂŃ|�[�c�}�X���i���I�u�a���j����������B�֓��R�i����Ƃ�����j �Ƃ��ēƗ������B�͖{��� ���R�����卲�炪�������i���傤�������j���E�������N�����B�֓��R�����Q�d�E�_���l�Y�卲�Ɗ֓��R����C�Q�d�E�Ό��Ύ����� �́A����̔��z����_�ɍs�������Ă��āA���m���Ō������́u�N�i�V�c�j�̈ӌ��v�ȂǁA�ŏ����疳�����Ă����B�����Ύ��� ���N�����Ē��w�ǂ̐��͂B����쒀���A�����S�O�\��N�A���B������������B�܁E������i���E�����E��������j �̋��e�ɓ|��A���̍֓������t�͓����c�菑����������B�������F����B�m�����n������ �ł́A�֓��R���g����킷�邪�傫�ȑ��Q������{���R���ł͖k�i�_����܂�_�@�ƂȂ����B�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z
�������������֓��R�Q�d�E�͖{���i�������Ƃ��������j�卲 �֓��R�Q�d�E�͖{���i�������Ƃ��������j�卲
�y�֓��R�Q�d�E�͖{���i�������Ƃ��������j�卲
���������E�����i���傤����������������j �́A�֓��R�Q�d�E�͖{���i�������Ƃ��������j�卲�ɂ���āu�����ɔ��e���d�|�������s���ꂽ�v������ł���B���I�푈 �ɏo���A�d�����B�֓��R�i����Ƃ�����j �Q�d���A���������E�������N���A��E�A�Җ��A�\����ғ��ƂȂ�B���a�V�c�T�m�É��i���傤��Ă�̂��Ђ�ЂƂւ���) �ɕ����B���B�� ���̗L�͍��E�l�ƂȂ�B�T�؊�T�i�̂��܂ꂷ���j �̎��j�E�ۓT�i�₷����/�������сA���I�푈 �Ő펀�j�Ɠ����ł���B���B������ �܂ł̋O�Ղ�H��ƁA�ƂĂ��ڋ��Ȏ��͂��Ȃ��������m���̍� �̍c�R�E�֓��R �͎�i��I�ʖd���̌R���������B���v �v�ƌ����A���ł��ʂ�l�ȕ����̎��ゾ�����B�����Ƃ̖����̉ʂ� �v�ɁA��������������Ŏn�߂����Ȃ̂��A�����ɉ��������̂ł���B�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z
���������������������E�����i���傤����������������j ���������E�����i���傤����������������j
�y���������E�����i���傤����������������j
���������E�����i���傤����������������j�́A���S��\���N�i���a�O�N�j�Z���l���A�֓��R�i����Ƃ�����j �ɋ����ĕ�V�R���̎w���ҁE���������ÎE���ꂽ�����ł���B�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z
���������������������Ύ����i��イ���傤��������j �����Ύ����i��イ���傤��������j
�y�����Ύ����i��イ���傤��������j
�����Ύ����i��イ���傤��������j�́A���S�O�\��N�i���a�Z�N�j�㌎�\�����A���݂̒������k���i���B�j�̌��݂��c�z�s�i��V�j�ߍx�̖����i��イ���傤���j�t�߂œ��{�̏��L����얞�B�S���i���S�j�̐��H�����j���ꂽ�����ł���B�֓��R�i����Ƃ�����j �̕��͖͂}�i����j���ꖜ�ł���A�S������ɔC�����Ɨ�������Ɠ�N���Œ�ⲁi���イ����/�h���؍݁j������n�̈�t�c�i�����͑��t�c�A�����Ԓn�͋{�錧���s�j�ɂ���č\������Ă����B�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z
�������������܁E������i���E�����E��������j �܁E������i���E�����E��������j
�y�܁E������i���E�����E��������j
�܁E������i���E�����E��������j�́A���S�O�\��N�i���a���N�j�܌��\�ܓ��ɓ��{�ŋN�������������ł���B�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z
�������������������B���ρi�܂イ���ւ�j ���B���ρi�܂イ���ւ�j
�y���B���ρi�܂イ���ւ�j
���̖����Ύ����i��イ���傤��������j�[�ɁA�֓��R�͂���B���ρi�܂イ���ւ�j�ɔ��W�����čs���B�֓��R�i����Ƃ�����j �i���F�����̑���{�鍑���R�̌R�j���얞�B�S���̐��H�j���������i�����Ύ����j�ɒ[�������͕����i���ρj�ł���B�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z
�������������������F���i�܂イ�����j�̌��� ���F���i�܂イ�����j�̌���
�y���F���i�܂イ�����j�̌���
���F���̌����ɂ��A�����s��ɊS�����č��瑼�̗Ƃ̑Η����[���������B�����Ύ��� ��������l����̐��S�O�\��N�㌎��\����A�֓��R�i����Ƃ�����j �̖��B���̗L�v��͗��R��]���̔��œƗ����ƈĂւƕύX���ꂽ�B�Q�d�E�Ό��Ύ��i������炩�j ������ɟ�V����ǂƂ���e�����Ƃ��������ׂ��Ǝ咣�����B�]�R�Ԉ��w�̋����A�s �v�́A�S���F�߂鎖���o���Ȃ��R�̑n��ł���B�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z
�������������ۘA���E�ށi�����������߂����������j ���ۘA���E�ށi�����������߂����������j
�y���ۘA���E�ށi�����������߂����������j
���ۘA���E�ށi�����������߂����������j�Ƃ́A���S�O�\�O�N�i���a���j�O����\�����A���b�g�����̍̑��ɔ����āA���{�������ɍ��ۘA���E�ނ�ʍ��������������B���B���� ���_�@�ɂ��̒n�ʂ���]���A�����������ɂ���ĘA���ɒ�i���ꂽ�B���B�� �����S(�����炢)���Ƃł��鎖��������F�߂���̂ł������B�`�a�b�c��͖ԁi�G�B�r�C�V�B�f�B�ق��������j �ƌĂ�Ŕ�������B�̓y�s�N��� ���Č��ق�ݒu����Ɏ���A�����̓Ɨ����̎O���̈�ȏ�ƍ���������ň��肵����Ԃɒu���ꂽ�B�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z
����������������ḍa�������i�낱�����傤������j ḍa�������i�낱�����傤������j
�yḍa�������i�낱�����傤������j
���B����������{�́A���S�O�\�O�N�O����\�����ɍ��ۘA���E�ނ��A�����̍������z���Ē����̓��Ɏx�ߒ��ԌR��u���Ă����B��E��Z���� ���N�����Ă���B�����p�@�i�Ƃ����傤�Ђł��j �瓝���h�̐����I�����͂��܂��܂������Ȃ�A�Ԃ��ČR���̗͂����܂��Ă��܂��A�o�ϖ��܂ł����u���͉������嗬�v�ɂȂ��Ă��܂����B�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z
���������������������R���E�����Ɠ�E��Z���� �R���E�����Ɠ�E��Z����
�y�R���E�����Ɠ�E��Z����
�ېV�͐������A�u�ߑ���{���{�v�͂���Ɛ��������B�m���Љ� �ƌ��������g����菜����A�������w�⎟��Łu�ׂ�����n�ʂ̌����v���ɕۗL����悤�ɂȂ������A����͉i�����������Љ�i�����Љ�j �̕���̏��͂ł���A����Ɠ����ɐV�����`�̊i�����n�܂�������ł��݂�B�����푈 �A���I�푈 �A���N�������� �A���B������ �A�ȂNjߗ����������ށu�s�K�ȗ��j�v���A���̔w�i�ɂ́u���{�����̕s���v�ƌ�������������B�������� �A�y�ѓn�Ӌ��瑍�Ă��̑��x���̌x�@���Ȃǂ��E�Q�������̓������A�c���̔h�Ɠ����h�̌��͑����̑��ʂ������Ȃ�����A�s���̒��A���R�m���w�Z�o�̐N���Z�������オ�������v�N�[�f�^�[�ł���B�����p�@�i�Ƃ����傤�Ђł��j �瓝���h�̐����I�����͂��܂��܂������Ȃ�A�Ԃ��ČR���̗͂����܂��Ă��܂��A�o�ϖ��܂ł����u���͉������嗬�v�ɂȂ��Ă��܂����B���w�� �ɐg���肵�čs������Ȃ����A�o�ϓI�ɒǂ��l�߂��Ă����B�L�b�G�g �����i���N����/���\�E�c���̖��j�̖��d�ȊO�n�l���s�ׂ̋��P�͖Y����Ă����B�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z
�����������������������؎��ρi�ɂ������ւ�j ���؎��ρi�ɂ������ւ�j
�y���؎��ρi�ɂ������ւ�j
���؎��ρi�ɂ������ւ�j���x�ߎ��ρi���Ȃ��ւ�j�Ƃ́A���S�O�\���N�i���a�\��N�j��������n�܂������{�ƒ��ؖ����̊Ԃōs��ꂽ�����Ԃ���K�͂Ȑ퓬�ł���B�����m�Εĉp�푈�y�����m���ڃj���q���N�X���R�g�A���w�L�푈�n�x�ߎ��σ����܃��哌���푈�g�ď̃X �v�ƌ��肵���B�֓��R�i����Ƃ�����j �ŁA���{�{�y�̎O�{���̖ʐς������B�̐�̂����������B�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z
���������������������m�����n������ �m�����n������
�y�m�����n������
�m�����n�������i�m�����n��������j�́A���S�O�\��N�i���a�\�l�N�j�܌����瓯�N�㌎�ɂ����ċN���������B���ƃ����S���l�����a���̊Ԃ̍��������߂����Ĕ����������\���R�̍������������ł���B�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z
�����������`�a�b�c��͖ԁi�G�B�r�C�V�B�f�B�ق��������j �`�a�b�c��͖ԁi�G�B�r�C�V�B�f�B�ق��������j
�y�`�a�b�c��͖ԁi�G�B�r�C�V�B�f�B�ق��������j
�`�a�b�c��͖ԁi�G�B�r�C�V�B�f�B�ق�������/ABCD encirclement�j�Ƃ́A������̑Γ��o�ϐ��ق̓��{������̕ʏ̂ł���B���ۘA���i�����������߂��j��E�� ����B���B���� �v���������̓��{�̗̓y�g���`�ŁA�����������i�u�`�a�b�c��͖ԁv�ŗ}�����悤�Ƃ������ʂ́A�j�ꂩ�Ԃ�̑ΕĊJ�킪�^��p�U���ł���B�����i���]��/�v�Z�j�Ɗ����i�E�]��/����j �̍l�������炷��ƁA���푈�i�n�푈/�����j �́A���ɏ��Z��x�O�������u���c���Θ_�ƌ����E�]��̊ϔO�v�݂̂ŊJ�킵�Ă��܂������B�c�h�̋��s�������B�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z
�����������������Ƒ������@�i�����������ǂ�����ق��j ���Ƒ������@�i�����������ǂ�����ق��j
�y���Ƒ������@�i�����������ǂ�����ق��j
���Ƒ������@�i�����������ǂ�����ق��j�́A�����푈 �̊g�傪���W������E��풆�ɍs��ꂽ�R�����ƂƂ��Ă̗v�i���Ȃ߁j�ƂȂ�ԗ��I���������@�ł���B�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z
�����������������������^��k�i�����^����j �����^��k�i�����^����j
�y�����^��k�i�����^����j
����E���Ƒ哌���푈�̏��s�����炩�ɂȂ���������S�l�\�ܔN�i���a��\�N�j�A�A�����J�̃t�����N�����E���[�Y�x���g�A�C�M���X�̃`���[�`���A�\�A�̃X�^�[�������\�A�̃N���~�A�����̃����^�ŋ��c���s�����B���I�푈 ��̃|�[�c�}�X���ɂ����{�����������`��얞�F�S���Ƃ��������{�̌��v���܂܂�Ă����B���B �A�瓇�A�����ɐN�U���J�n����B�\�A�Γ����Q��i������ɂ����₭����j �̊J��o�܂ł���B�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z
���������\�A�Γ����Q��i������ɂ����₭����j �\�A�Γ����Q��i������ɂ����₭����j
�y�\�A�Γ����Q��i������ɂ����₭����j
�\�A�Γ����Q��i������ɂ����₭����j�́A�����m�푈�����Ƀ\�r�G�g�A�M�R�����\�������i���S�l�\��N/���a�\�Z�N�����j������I�ɔj�����Ė��B�ɍU�ߍ���ŗ�����A�̊�P�U���̍��E�퓬���w���B�֓��R �Ƌɓ��\�r�G�g�A�M�R�Ƃ̊Ԃōs��ꂽ���B �E�k���N�ɂ������A�̍��E�퓬�ƁA���{�̑�ܕ��ʌR�ƃ\�A�̋ɓ��\�r�G�g�A�M�R�Ƃ̊Ԃōs��ꂽ�슒���E�瓇�ɉ������A�̍��E�퓬�ł���B�m�����n������ �ɉ����ē��\���R�͐퓬���s���A�֓��R�͂��̍���̐�͍��Ȃǂ�F�������B�����^��k�i�����^����j �ł͑Γ��Q��v������̉����A�h�C�c�~����O�����ł̑Γ��Q������B�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z
�������������������\�A�E���F���N�U �\�A�E���F���N�U
�y�\�A�E���F���N�U
���\�Ԃɂ́A���S�l�\��N�i���a�\�Z�N�j�ɓ��{�ƃ\�A�̊ԂŒ������ꂽ�������u���\�s�N���v���݂����̂����A�\�A�͂��������I�ɔj�����Ė��B���y�ѓ��{�̂̓슒���A�����Ėk���l���ɐN�U�����B�֓��R�i����Ƃ�����j �͍����Őw�n�h����s���A�틵�̈����ɏ]���Ėh�q����i�K�I�ɑ�A - �V�� - �}��̎O�p���܂œ쉺������琨��ނ��s�����B�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z
���������������������N�U���ʘ_ �����N�U���ʘ_
�y�����N�U���ʘ_
�����Ύ����i��イ���傤��������j�̎�ƁE�_���l�Y�́A��ɗ��R��b�i��ꎟ�߉q���t�y�ѕ������t�j�߂Ȃǒ����ŏo���A�叫�ɁA�Ό��Ύ��i�����͂炩�j�͒����܂ŏ����Ă���B�����_�� �̂`����ƍ��J���ł���B��w�P ��z�N���A�u�����Ęؗ��̐J�߂��E�E�E�v�ƑޘH��f���A�㊄���퓬�ł͂Ȃ��u�a���A�쎀�A���n�A���U�v�ƌ����ߍ��Ȏ��ɉۂ����ӔC���A�����Ĕs��ӔC���A���́u�����`����ƍ��J���v�̘_�c����O��?�����p�@�i�Ƃ����傤�Ђł��j ��u�`����Ƃ���푈�w���ҁv�ƁA�u���J�����͖̂��O�v�Ǝv���p��͑������ł���B���钩 �����N�O�ɉ�����̖��������̖ژ_�݂͌����������āA�u��a�P�ꖯ���v���������Ă����؋��ł���B
�y�� �z �y�����c�����K�̉e�l �z��蔲���B�{�� �����ǂ݉������B
�� �y�� �z �y��ҁE�����v�����T�C�g�\���[�� �z�֖߂�B♥ ♥ �����œǂ߂�����������������
��������k�̏������X�g ♥ ♥ ♥ ♥ �y�p��l������E���{�j�����E�N���b�N���X�g �z �y���m�点�z
�����̖{�i������i���A�g�o�ŒZ���Ԍ��J�����Ă��������܂��B
���{�l�Ȃ�m���Ă��đ��͖��� �y���ȏ��ɍڂ��Ă��Ȃ����j�̓� �z�ɔ���B�y����{�j�������� �A�z�܍s�㎚���@ �剤�i�������݁E�V�c�j�̖��� ���z
���C���^�C�g���y�c�����K�̉e�l �����Ƃ��Ƃʂ��̂����т� �j���S�Łi�S�l�� �E���e��疇 �j���y�����L�[���[�h�E�_�C�W�F�X�g�W ��ԁB �z�c�����K�̉e�l�����L�[���[�h�E�_�C�W�F�X�g�W �z�ɔ�ԁB �� �y�����̋^�f��Nj����� ��ԁB �z
�A�[���ɗ���E�E�E�c��̊�Őe���������������ƌ����܂��B �z �y�E�z ��l��y�� ��������l��y�� �������y�E�z��������k�ƃ��[�����C�������ׂ���l��y�� �������N���b�N ���������C�ɓ���\�� �v������ƁA���S����J�̃��[�����C�������ׂ܂��B)
NINJA�u���O�i�E�ҕ���j ���������j�̓�z�͂������y�N���b�N �z�����g�o�E�g�b�v�Łi��k�̕����g�o�j �ɔ�ԁB�����̋^�f��Nj����� �z�E�E�E�E�E�E�E�E�E���ό�̍����̍����͑��݂��� �z���L�e�\�荀�ڂ̃��X�g�����N���b�N���Đ��ւ��q�˂��������B
�yyahoo���� �z�y�foogle���� �z
�y�� �z �y���{�l�̑c�� �͉������痈���̂��H �y�� �z �y�S�`���ɉB���ꂽ��Z���i�ڈΑ�/�G�~�V���j �y�� �z �y�l�C�e�B�u�W���p�j�[�Y�E���{�ŗL�̌��Z���� �y�� �z �y���E������Y�E�x�m�R���̂̈��i����j�� �y�� �z �y�V�Ƒ�_ �E�V�̊�˓`���͑��̐_�b���H �y�� �z �y�V���~�i���j�Փ`���Ɩ؉ԍ��P�i���̂͂Ȃ�����Ђ߁j �y�� �z �y�R�K�F�E�C�K�F�i��܂����Ђ��E���݂����Ђ��j�ƉY���E���{�`�� �y�� �z �y�����̔��e�i���Ȃ̂��낤�����j�`���Ƒ卑��i�������ɂʂ��j �y�� �z �y�����E�F����i�������j�����{�����i�X�T�m�E�j�� �y�� �z �y�_�����J����E�_�b�^���L �z�� �ŐV�� �y�� �z �y�u���{�̓V�c�Ƃ̑c��͒��N�������痈���v�������� �y�� �z �y��a�����i���}�g����/���{�l�j�̐����ߒ� �y�� �z �y�L���`�̍� �_�i����E���{�`���_�̋^�f�j �z�y�� �z �y���j����i�������͂������j�ƍ��B��i�������ˁ^�����j �y�� �z �y�Ñ㍑�ƁE�הn�䍑 ���ږ�� �͉��҂��H�y�� �z �y����~�X�e���[ ���ɓ��̍����ɓs�� (���Ƃ����j���y�� �z �y���{��̃��[�c �ƈ��{���y�� �z �y��a�i��܂Ɓj�̂܂ق�i�}�z���o�j �z�y�� �z �y�V�� �C���� �����_ �E�l�g�䋟�`�� �y�� �z �y���{�̓`�����X�g �y�� �z �y�H�c���l ���i�j���h���� �y�� �z �y�����̃��[�c �������i�������ˁj �̗��j�y�� �z �y�l���n�肵�_�ƕ��̊Ԃ� �y�� �z �y���{�̌��i�����j�\���͗R�������� �y�� �z �y���{�j�E���j�̃~�X�e���[ �y�� �z �y�ÈōՂ�̗��j�F�� �z �y�� �z �y����i�������j �y�� �z �y�������j�W�ꗗ���X�g �z �y�� �z �y���̈��������{�̐����� �y�� �z �y�n�����~���u������`�v �ƌ����C�f�I���M�[ �y�� �z �y���{�l�E���̋C���̃��[�c �y�� �z �y�M���낵�i�ӂł��낵�j�Ɛ��g���i�݂������j �z�y�� �z �y�Ñ���{�j�̍l�@ �y�� �z �y���{�j����敪�嗪�E�ꗗ�\ �y�� �z �y�v�w�r�̖�(�߂��Ƃނ݂̂�) �yyahoo���� �z�y�foogle���� �z
�y�� �z�y�^���������여 �y�� �z�y�A�z�t�����ƒ���@�� �y�� �z�y��Β��s�i����R���H�Ɓj�ƈ��{�����i�y����)�̓� �y�� �z�y�m���V�c�i�ɂ�Ƃ��Ă�̂��j�ƓV�c�ˁi�Ă�̂���傤�j �� �ŐV�� �y�� �z�y�������q�͎��݂������H���̋^�f��ǂ� �y�� �z�y�p�̑剤�i���������������݁E�V�c�j���ʂ̂���^���B �y�� �z�y��C�l�c�q�i�������܂݂̂��j�͉��҂��H �y�� �z�y�㏬���V�c�i�����܂Ă�̂��j�o���^�f �z �y�� �z�y�������i������̂������j�̓�ɔ��� �y�� �z�y�V���i���Y�j�̗��j �y�� �z�y���{���m�̃��[�c �z�y�� �z�y���Ɓi�a��l�j�̉Ɩ��ꗗ �y�� �z�y���B���{�Ƃ̑c�E���Y���r�i�܂炽���Ƃ��j �y�� �z�y���`�o�Ɠ�l�̏����i�ɂ債�傤�j �y�� �z�y���q�a�̏\�O�l �z �� �ŐV�� �y�� �z�y�������{����̌o�� �� �ŐV�� �y�� �z�y�D�c�M���́u�動�i�������j���v��������� �y�� �z�y�u�{�\���̕ρv�̓�E���G�̖{�\�� �z �y�� �z�y�{�\���̕ρA�Ȃ��N������������������B �y�� �z�y���q���G ���V�C�m������������ �y�� �z�y��Ɏ��Ə����퍑�����E��ɒ��Ձi�����Ȃ��Ƃ�j �� �ŐV�� �y�� �z�y���{�́A��߂�ꂽ������J�E�t������ �� �ŐV�� �y�� �z�y����ƍN��l���̓��ǂ� �y�� �z�y�L�b�G�g�E�R�|�i�T���J�E�T���K�j�̉����� �y�� �z�y�R�t�E���c�����q�F���ƒ��� �y�� �z�y�V���̒m���E�^�c�M�Ɂi�K���j�Ɛ^�c�� �� �ŐV�� �y�� �z�y�L�b�ƖŖS�̗v���E�G���̎����ʐl���^�f �y�� �z�y�䏗���i�����傿�イ�j�ƍ����i�������Ɓj�̈Ⴂ �y�� �z�y�{�{�����i�݂���Ƃނ����j�`���̐^�� �� �ŐV�� �y�� �z�y��E�֎~�߁i�����Ђ����ꂢ�j�Ǝ���l�� �� �ŐV�� �y�� �z�y�u���ˉ��喟�V�L�v�̃q���g�Ɛ������j���E���˓���ƈٕ� �y�� �z�y���D�O��E���A���w���{�̊�@ �z �� �ŐV�� �y�� �z�y�������m�X���E�ېV�^���L �� �ŐV�� �y�� �z�y�ߍ]���E��{���n�ÎE�����̈ӊO �y�� �z�y�u�ٕ��E�B���ꂽ�����ېV�v�i�����ېV�ɂ܂��\�̓�j �� �ŐV�� �y�� �z�y���������E����q��������푈�i����̖��j �y�� �z�y�����`�����ېV �E�l���Ǝ��σ��X�g �y�� �z�y�����i����j�j�T�� �� �ŐV�� �y�� �z�y�吳���}���Ɋς�D�i�C�ƕ����K�� �� �ŐV�� �y�� �z�y�����m�푈�̉����E�E���������E�����E�����Ύ����̉A�d �z �� �ŐV�� �y�� �z�y�^��p�U���i���ĊJ��j �z �� �ŐV�� �y�� �z�y�L���E���� �����픚�T���j �z �� �ŐV�� �y�� �z�y�R���ւ̓��i�����`���a�����܂ł̎��ϊW���X�g�j �y�� �z�y���j�E�̓y���Ɣ����^�����l�@���� �y�� �z�y��͑�a�̉p��ɕ����E�����Ė��� �y�� �z�y�]�R�Ԉ��w���� �y�� �z�y���Ƃ̕i�i �E���m���̍��E���{ �̂܂₩���y�� �z�y���O �E�������� �E���{ �̂܂₩���y�� �z�y�����c��c���j�ρi��������������j �z �� �ŐV�� �y�� �z�y�]�R�Ԉ��w�Ɠ��{�l�f�v���i�f�v���Ɠ��Đ��{�̉��x���j �y�� �z�y�`�����O���̐��� �u���@�����@�\�E�W�����O�� �@�̃����v �y�� �z�y���{�� �u���{�W�O�����{�����N�̗��j �yyahoo���� �z�y�foogle���� �z
�y�� �z �y�C�Y�����s�m���Ɖ���ČR�R���̔؍s�E�E �� �ŐV�� �y�� �z �y�����v�����_�̑�В��i�������j�� �� �ŐV�� �y�� �z �y�A���^�}�c���ɁA���Ƃ��Ă��V�n�� �z �� �ŐV�� �y�� �z �y���ӂ�������{�ƍّ��� �z �� �ŐV�� �y�� �z �y�A�x�m�~�N�X�����ۖ@���̉����D�� �z �� �ŐV�� �y�� �z �y�A�x�m�~�N�X�E�s�s���Ȑ^�� �z�� �ŐV�� �y�� �z �y����lj��ɘa�E�������Ƃ̔敾�͊R���Ղ� �z�� �ŐV�� �y�� �z �y�č��E���[��������������łɏd��x�� �z�� �ŐV�� �y�� �z �y�|���������̍�������E�^�f�̐��� �z�� �ŐV�� �y�� �z �y�s�ꐮ���̎��オ����l����� �z�� �ŐV�� �y�� �z �yASKA�i���j�̖���ߕ߂̗��ɐ��ތ��͂̈Łi�|���^�f�j �z�y�� �z �y�n�ӊ�����́A���������^�f�Ő����ƂƂ��Ď��i �z�y�� �z �y����������������Ԉ��w���̓n�ӊ�� �y�� �z �y�j�]��@�ɍ݂�A�x�m�~�N�X �z�y�� �z �y���{�W�O�E�����_�ЂɎQ�q���� �z�y�� �z �y���Ȃ��������{�l�ɃA�x�m�~�N�X�̌��ʂ́H �z�y�� �z �y�A�x�m�~�N�X�͌ÓT���̍ĉ��ł��� �z�y�� �z �y�A�x�m�~�N�X�̒��g���ÂɌ����悤 �z�y�� �z �y�A�x�m�~�N�X�M�͍Ăт̈������H �z�y�� �z �y�A�x�m�~�N�X�i�o�σC���t�����v��j�ɕs������ �z�y�� �z �y���{���Z�E�̔����t�͂��� �z�y�� �z �y���{�����Ďn���E�A�x�m�~�N�X�ւ̌��O �z�y�� �z �y��}�ɓ]����������}�E�Đ��ւ̏��� �z�y�� �z �y���I���O��E�E���[��͑I�ׂ�̂��H �z�y�� �z �y���}�����ō���������U���I���Ɂu�E�����v �z�y�� �z �y�����~�܂��čl���悤�E�s�o�o������� �z�y�� �z �y����}�E���t�̉������������̎d�� �z�y�� �z �y��t�E�|���E�I�X�v���C�A��c�����̊O���͌����炯 �z�y�� �z �y�j�E�u���{�ېV�̉�v�̌��} �z�y�� �z �y��c���t�s�M�C�āE��c���F��ӌ��c�ƏO�@���U �z�y�� �z �y�\�������c������j�~����B �z�y�� �z �y����}�c���E����ł̗ǂ��q�V�����ƐS�� �z�y�� �z �y�s�i�����j�ߎ��E�����̉B���i������j �z�y�� �z �y����}�E��c�����͍Œ�̐����ł��� �z�y�� �z �y����}�E��c�����͍Œ�̐����k�U�l �z�y�� �z �y��ƌo�c�ɉ�����u�������O�v���Ă��� �z�y�� �z �y������v �̐����y�� �z �y�c���萔�팸���ɕ��\�� �y�� �z �y���ۋ����͂Ɩ@�l�ŗ��Čy���_ �̉��y�� �z �y�n�������E���B���� �̉������y�� �z �y�����} �E�吭��Ҙ_ �y�� �z �y�����̋^�f��Nj����� �����X�V�� �y�� �z �y���{�̐j�H�͑��v���H �p�[�g�T �z�y�� �z �y���{�̐j�H�͑��v���H �p�[�g�U ���t�{������b�̔����H �y�� �z �y���{�̌���Ə�����t�ւ̎��� �yyahoo���� �z�y�foogle���� �z
�y���z �y�l�������͖��h���ł͂Ȃ��̂��H �y���z �y������ꌴ���̊�@�͋������̂��H �y���z �y��ь����ĊJ�͂������Ȃ閵�� �y���z �y��C�g���t����n�k�E�u���C�n�k�ƎO�A���̋L�^�j�v �y���z �y��s�����^����n�k�̋L�^�j �y���z �y����n�k�L�^�E�N�\ �y���z �y����n�k�ƕl������ �C���f�B�A���R���Ȃ� �E�E�E�U�i����j�� �z �y���z �y���d�����������̃��A���^�C���̃u���O �z �y���z �y���\�L�̑�k�ЁE���{���{�́u���A�����ׂ��ׂ����H�v �y���z �y�������̓��k�����Ɛ����� �y���z �y���k��k�Ќ�̏̎^�������{�l �z �y���z �y�C���^�[�l�b�g�̋��Ђƒm��߂��������̎��� �y���z �y�p�\�R�����u���쎖�� �y���z �y�z���T�s�G���X�i�m���l�j�́u��̕ۑ��ƈ�`�q�v �z �y�� �z �y�A���J�����O���ʂƈ�ѐ��s�����_ �y�� �z �y���b�N�C�����ʂ̐S�����_ �y�� �z �y�l�b�g���[�N�O�����̗��_ �z�y�� �z �y�܂����N���ɂȂ錚�O��́u�����؎̂Ę_ �v�̐�] �z�y�� �z �y�펯�i���傤�����j�ƌ�����Ȍ��� �y�� �z �y�P���Ȏ咣�E�����v�����_ �� �ŐV�� �y�� �z �y�V���N���j�[�i�����s���j�̉�� �y�� �z �y�Ȃ��j�̓X�g�[�J�[�ɐ���̂��H �y�� �z �y�����ʁi����������j�̐S���������� �y�� �z �y�I���I�����\ ��p�슴���@ �z�y�� �z �y���i���ˁj�Ɠ��{�l �y�� �z �y������̗v�_���l���� �y�� �z �y�������Ȃ�鋻���̉�� �y�� �z �y�l�� �̐��Ɛ��_�̍l�@ �y�� �z �y�q��Ăƕ���̉�� �y�� �z �y��Ŋ뜜�i��E���{�l �y�� �z �y���q�����Ɛ��ւ̌����� �y�� �z �y�q�}�������Ɛ���g�� ���Ɩђ� �z�y�� �z �y�K���̍��E�u�[�^�������E�E�E���{�l�͍K���ł����H �y�� �z �y�x�G�����Ɠ��{�̓]�����̍l�@ �y�� �z �y���������E���{�ւ̊뜜 �z �yyahoo���� �z�y�foogle���� �z
�y�� �z �y�h���I�����i���キ�߂��Ă��ނ����j�̍l�@ �z�� �ŐV�� �y�� �z �y���]�ԑ��s���[���̐����g�[ �y�� �z �y�T�u�v���C�����[�� �y�� �z �y�K���ɘa �y�� �z �y�t���̐H�i�U��(���������j �y�� �z �y�o�u������ �Ƃ��̌�̕s���y�� �z �y�P��I�� ���lj�� �y�� �z �y���[�L���O�v�A�i�����n���w�j �y�� �z �y�u������Ð��x�v �E�������҈�Ð��x�i�����������ꂢ���Ⴂ��傤�����ǁj �y�� �z �y������卑 �E���{�̖��� �y�� �z �y���E�W�� ����y�� �z �y�����ɕ��S���|���Ȃ� �Ԏ����� �̏������@�y�� �z �y�u�����h�_�b �ւ̌x���y�� �z �y�O���Ƃ��ŗ���r�_ �̂܂₩�� �y�� �z �y�����ĐX������ �y�� �z �y�q�g���[�̑䓪 �����������݂̓��{�̗ގ��_ �y�� �z �y�B���Ԏ��̎��� �y�� �z �y�����i��l�j �̃A�}�[�C�����y�� �z �y�����卑�E���{ ����E�o������@�y�� �z �y�����o�g�c�� ���E�O���c�� �ւ̊뜜�y�� �z �y���x�����������Z�b�g �y�� �z �y���q��� ���̋�̍��y�� �z �y�m�g�j��� �̍l�@�y�� �z �y�j�������Q�� �����q���S����b �̂܂₩���y�� �z �y��҂̖��� (�j�[�g �}���̉e�Ɂj�y�� �z �y�h�L�������g������Ɠ|�Y �y�� �z �y��v�\��ȋ^�f�����H�̍l�@ �y���z�y��T�C�g�E�E�E�z �E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�y��i�Љ�z �E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�y��҃v���t�B�[���Љ�z �E�E�E�E�E�E�E�y�|���b���i�͂Ăȁj�z �E�E�E�E�E�E�E ���g�o��V�^���X�g �� �y*�z �L�[�{�[�h�̔ޕ��ɂ́E�E�E���̈�������X���������y*�z�ߋ��̌f���� �i�P�j
�@�y�ȉ����ē��z����䗗�������� �����̈ē��͉��L�̃��X�g����������B �y��i�����N���b�N�I�N���b�N�I�z ♥ ♥ �����œǂ߂�����������������
��������k�̏������X�g ♥ ♥ ♥ ♥ �y��������k�̍�i���X�g �z
�y*�z �Z�Ґl������ �i�S�j�������������������������������������������������������������� �ٔ������x�V���~���[�V���� ���@�s�@�́@�ف@�� �i��傤���Ⴍ�̂����j �������@��k�@�� ��������������������������������������������������������������
�y*�z �Z�Ґl������ �i�R�j�����������������������������������������Z�ҏ��� �i�P�j�u�����̓���v ��
��ɂ��Ă��̍Ȃ��� �� �������@��k�@��
����������������������������������������
�y*�z �������Z�ҏ��� �i�P�j�����������������������������������������Z�ҏ��� �i�P�j�u�A�C�h����T���v �������c�H����~�� �� �������@��k�@��
���������������������������������������� �y*�z �Љ�h�Z�ҏ����i�Q�j
�����������������������������������������Љ�h�Z�ҏ��� (2)
�u�����l�̎��i�����j�v ����R�������� �� �������@��k�@��
����������������������������������������
�y�����E����C���^�[�l�b�g��k ���e�z �y*�z �� �a�₩�ȗːJ �� (�Ȃ��₩�Ȃ�傤���傭�j �������@��k�@��
�����������������������������������������y�����E����C���^�[�l�b�g��k ���e�z �������������������������������������������������������������� ��@��@��@��@�`�@�L �� ���ƌ��̋��ԂɗL��� �� �i��߂Ƃ��̂͂��܂ɂ���āj ���@�S�@�Ł� �������@��k�@�� ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������k�@���{�ɒ��遟 �������@��k�@��
����������������������������������������
�������}�K�T�C�g��
�����������}�K�E�T���v���Ł�����
��k�̔��z���l�܂������e�ł��I
��������(���{�j�ٕ��V���[�Y�j��Z�쁁���������������ЂƂ�̃N�[�f�^�[�� �������@��k�@��
�����������������������������������������������}�K�T�C�g���u�������ЂƂ�̃N�[�f�^�[ }�E�E�E�E�E�E�E�E�i����j
�����������}�K�E�T���v���Ł�����
���Ɍo�c�҂̕��ɂ͖ڂ���E���R�̓��e�ł��B
���������������������������������������������ʂ̗����� �������@��k�@��
�����������������������������������������������}�K�T�C�g��
�����������}�K�E�T���v���Ł�����
�l�̐S���ĕ��G�ł��ˁB
���������������������������������������������ʂ̗����O�`��
�������@��k�@��
������������������������������������������{�Z�ҏW�@���ʂ̗����E�O�`}�E�E�E�E�E�E�E�E�i����j ���E�G�u�T�C�g���u���ʂ̗����O�`�v
��������(���{�j�ٕ��V���[�Y�j���쁁�������������̃X�T�m�E�`���� �������@��k�@��
�����������������������������������������������}�K�T�C�g��
�����������}�K�E�T���v���Ł�����
����B�ŋN�����A�����������B
��������(���{�j�ٕ��V���[�Y�j��܍쁁������������i���Ȃǂ�j�� �������@��k�@��
�����������������������������������������������}�K�T�C�g��
�����������}�K�E�T���v���Ł�����
�V�ːM���Ƃ��̍ō��̗����ҁA���q���G�B
��������(���{�j�ٕ��V���[�Y�j��l�쁁���������Εv�̐_�B�����ꁟ �������@��k�@��
�����������������������������������������������}�K�T�C�g��
�����������}�K�E�T���v���Ł����� �N�����ʂ�߂���v�t���A
��������(���{�j�ٕ��V���[�Y�j��O�쁁���������S�ŁE�R�� �������@��k�@��
�����������������������������������������������}�K�T�C�g�������������}�K�E�T���v���Ł����� ���͐̂̊��q����A
��������(���{�j�ٕ��V���[�Y�j���쁁���������`�i��j�̍��͗y���Ȃ聟 �������@��k�@��
�����������������������������������������������}�K�T�C�g��
�����������}�K�E�T���v���Ł�����
�ؗ��u�[���̌��_�������ɁE�E ���g�o�g�b�v�� �i��k�g�o�j���ɔ�ԁB
============================================================================��k�̕����y�����z�܂�����������k�y�����z�ł� ��������k �i�~���N���W���E�_���j��
��@�k�@���@���@�X
�y���̍�i�Q�͒��q����������k �i�~���N���W���E�_���j�̒���i�ł��B�z
���J�͂��Ă��܂����A���쌠 �͂����܂ł���҂ɂ���܂��̂ŁA��҂̗����@�I��i �ɑi���܂��B�n�� �ł���A
�� �i �� ��
��i(
�������J�� �j �������J�� �w�� �i�P�W�ցj�����E�t�� ��i��������
��i(
�����A�ڒ� �j �������J�� �w�� �i�P�W�ցj�����댯�ȓq���E���� ��i������
��i(
�����A�ڒ�
�j �������J�� �w�� �i�P�W�ցj���ʂ̗����E�i�i ��i������
��i
�Z���������J �Z���������J�� �w�� �i��ʍ�j���ƌ��̋��ԂɗL��� ��i������
��@�@�@�@�@�i �T���v�� �w�� �i��ʍ�j��k�@���{�ɒ��� �T���v��������
��@�@�@�@�@�i �T���v�� �w�� �i��ʍ�j�����̃X�T�m�E�`�� �T���v��������
��@�@�@�@�@�i �T���v�� �w�� �i��ʍ�j�`�̍��͗y���Ȃ� �T���v��������
��@�@�@�@�@�i �T���v�� �w�� �i��ʍ�j�S�@�Ł@��@���@�R �T���v��������
��@�@�@�@�@�i �T���v�� �w�� �i��ʍ�j�Εv�̐_�B������ �T���v��������
��@�@�@�@�@�i �T���v�� �w�� �i��ʍ�j�@�@���@��@�i���Ȃǂ�j�@�@�@ �T���v��������
��@�@�@�@�@�i �T���v�� �w�� �i��ʍ�j�������ЂƂ�̃N�[�f�^�[ �T���v��������
��@�@�@�@�@�i �T���v�� �w�� �����M�� �T���v��������
��@�@�@�@�@�i �T���v�� �w�� �����M�� �T���v��������
��@�@�@�@�@�i �T���v�� �w�� �����M�� �T���v��������
���̕��͂͏C���ł��B ��Җ{���E��ؕ��� �E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
�E
���Ȃ��́A
��Җ{�� �E��ؕ��� 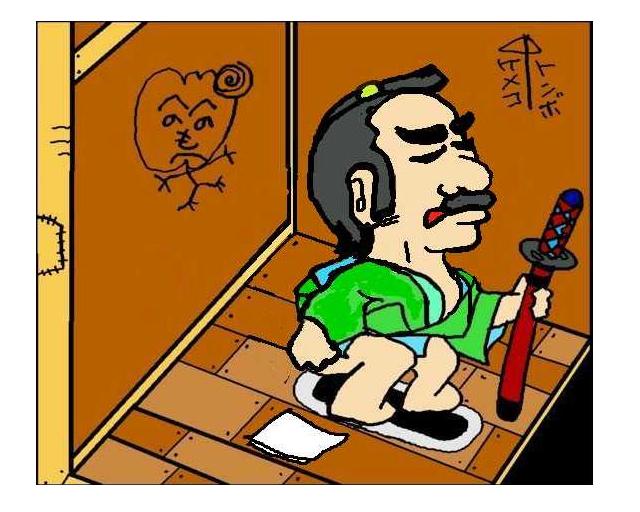 �y�����m�푈�̉����E�E���������E�����E�����Ύ����̉A�d�z��Җ{���E��ؕ����\���y�[�W�y�T�C�g�i�r�z�ɖ߂�B
�y�����m�푈�̉����E�E���������E�����E�����Ύ����̉A�d�z��Җ{���E��ؕ����\���y�[�W�y�T�C�g�i�r�z�ɖ߂�B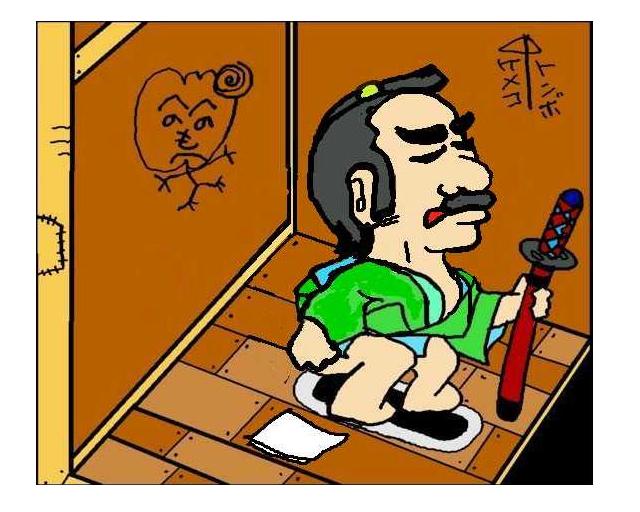 �y�����m�푈�̉����E�E���������E�����E�����Ύ����̉A�d�z��Җ{���E��ؕ����\���y�[�W�y�T�C�g�i�r�z�ɖ߂�B
�y�����m�푈�̉����E�E���������E�����E�����Ύ����̉A�d�z��Җ{���E��ؕ����\���y�[�W�y�T�C�g�i�r�z�ɖ߂�B